
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
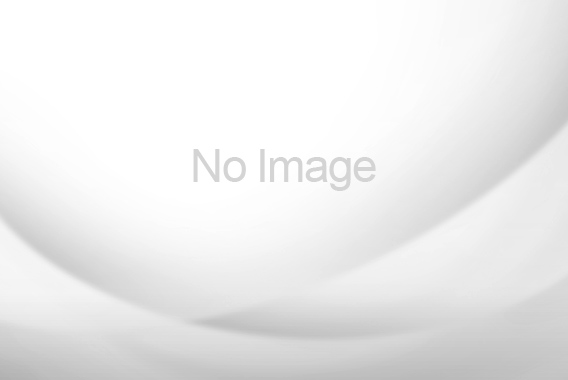
徳川家康の生涯を描くNHKの大河ドラマ「どうする家康」。話は進み、松本潤さん演じる家康は織田信長の上洛とともに京都に向かいました。
そして4月16日に放送された第14回「金ヶ崎でどうする!」で、家康は金ヶ崎の戦いに臨みました。「金ヶ崎の退き口」で知られるこの戦に関して、家康はどのような判断をしたのでしょうか。
金ヶ崎の戦いの話に入る前に、まず時代背景を押さえておきましょう。16世紀の半ば過ぎ、200年以上続いてきた室町幕府は危機に陥っていました。1565年に13代将軍・足利義輝が三好義継、松永久通らに暗殺されるという大事件が勃発。将軍の座は空位となり、相通じていたはずの三好氏と松永氏が次期将軍の擁立をめぐって対立し、都は混乱に陥ります。
義輝の弟・義昭は、兄の暗殺後に近江国(現・滋賀県)へ逃げ延びていました。この義昭に接近したのが、信長でした。1568年、信長は都を制圧すべく義昭を奉じて上洛します。その直後、三好三人衆に推されて14代将軍となった足利義栄が病没し、義昭が15代将軍に就任。信長は一気に政治の中枢へと近づきます。
信長は都の秩序を回復させるとともに、義昭体制と自らの権威を固めるため、諸将に上洛を命じます。しかし、越前国(現・福井県)の朝倉義景はこれに応じませんでした。そこで1570年4月、信長は越前の朝倉領に侵攻しました。信長軍は、朝倉景恒が守る手筒山城を攻め落とし、続いて金ヶ崎城も攻略。義景は北に向かい、木ノ芽峠一帯への退却を余儀なくされます。
勢いの止まらない信長軍がこれから木ノ芽峠を越え、義景の本拠地である一乗谷に向かおうというそのとき、事態を一変させる出来事が起こります。信長軍の浅井長政が朝倉方に寝返ったのです。
信長の妹・お市は、浅井長政に嫁いでいます。これは浅井の領地である北近江を押さえるための政略結婚だったのですが、信長にとって長政が義理の弟であることに変わりはありません。信長は最初にこの報告を受けたとき、虚報だとして信じようとしませんでした。しかし、同じ内容の報(しらせ)がいくつも入り、信長も信じざるを得なくなりました。
長政の裏切りに関する逸話としては、お市の方が信長に送った「小豆の袋」が有名です。両端を紐で結んだ小豆の袋は、信長が「袋の鼠」であることを示していると言われています。時代劇や大河ドラマでもよく描かれるシーンですが、後世の創作であると見られています。
長政が信長を裏切った理由については、朝倉と立てていた不戦の誓いを信長が破ったからとも、長政が朝倉と同盟を結んでいたからとも言われますが、真相は今もわかっていません。
朝倉方に付いた長政は、南から信長軍に迫ります。一方、北に逃げていた義景は南に引き返し、信長の軍勢は南北から挟まれる形になりました。
それまでは優勢だった信長軍も、これでは勝ち目がありません。信長は、長政を避けるため山側に進路を取ったうえ、南に逃げることになりました。そして退却戦を任されたのが、戦線に残った豊臣秀吉、明智光秀、池田勝正、徳川家康といった信長配下の武将たちです。
信長は秀吉、光秀に殿(しんがり)を務めるように伝えたものの、家康の陣には何も知らせることなく逃げていったと言われています。そして秀吉が家康の陣に来て、2人で殿を務めて戦ったということがのちの史料に記されています。これが「金ヶ崎の退き口」です。
残された家康としては戦わないわけにはいかず、ここでは他の判断は考えにくかったでしょう。しかし家康は、自分を置いて退却した信長から離れることはありませんでした。家康は、金ヶ崎の戦い以降も信長と戦を共にします。
金ヶ崎の戦いから2ヵ月後、信長は体制を立て直し、近江国・姉川で朝倉・浅井の連合軍と戦って勝利を収めます。この姉川の戦いに家康は参戦し、大きな活躍を見せています。
1575年には、亡くなった武田信玄の跡を継いだ武田勝頼と、信長・家康の連合軍が長篠の戦いに挑み、信長・家康連合軍が勝利。1582年には信長・家康の連合軍は武田領に攻め入り、勝頼を破って武田氏を滅亡に追い込みました。この直後、信長は本能寺で明智光秀に討たれます。家康は、信長の最期までともに戦い続けたことになります。
金ヶ崎の戦いで自分に何も言わず逃げ落ち、危険な退却戦に否応なく身を置かせた信長に対して、家康が信用を無くしても不思議ではありませんでした。しかし、おそらく敵対していた武田氏との力関係などから、家康は信長との関係を保ち続けたのでしょう。
家康は一般的なイメージとは異なり、意外と感情的になりやすい性格だったようです。それだけに冷静になることの大切さを知っていました。一時の出来事ではなく、長い目で見て判断する。これが、家康を天下人に導いた資質のひとつなのかもしれません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント