
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
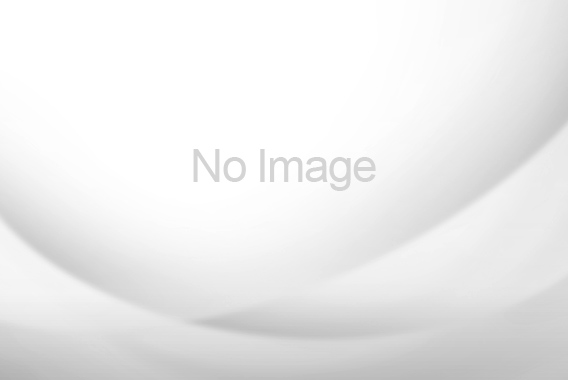
NHK大河ドラマの放送期間は、通常では1年。2023年1月に始まった「どうする家康」も中盤にさしかかってきました。6月4日と11日に放送された第21回、第22回で取り上げられたのは、徳川家康・織田信長の軍が武田勝頼率いる武田軍と相対した長篠・設楽原の戦い。初めて鉄砲が本格的に使われたことでも名高いこの戦には、どのようなドラマがあったのでしょう。
戦いの舞台となった長篠は、三河国の東部(現・愛知県新城市)にあります。ここは三河国と美濃国(現・岐阜県南部)、遠江(現・静岡県西部)を結ぶ交通の要衝であり、長篠・設楽原の戦いよりも前から、その領有をめぐって争いが繰り広げられてきました。
そこで鍵を握っていたのが、山家三方衆(やまがさんぽうしゅう)と呼ばれる三河東部の地方領主です。長篠から見て西の作手(つくで)は奥平氏、北西の田峯(だみね)は菅沼氏、そして長篠は田峯とは異なる菅沼氏が治めていました。しかしこの三家の力は決して大きくなく、三河東部に勢力を伸ばした大名にその都度、従っていました。
長篠の菅沼氏は当初、他の二氏とともに今川氏に従っていました。ところが桶狭間の戦いで今川義元が信長に討たれると、三河統一を進める家康の傘下に入ります。そして甲斐国(現・山梨県)の武田信玄が三河に侵攻して勢力を拡大すると、今度は武田氏の下に入りました。
そのような中、1573年に信玄が急死し、事態は大きく動きます。信玄の死を好機と見た家康は、武田に奪われた形になっていた三河を取り戻すため軍を進めました。中でも重要なのは、要衝に位置する長篠です。
1573年7月、菅沼氏が本拠とする長篠城に家康が攻め込みました。信玄亡きあと武田の家督を継いだ勝頼は、のちに武田四天王の一人に数えられた勇将・馬場信春を長篠城に向かわせました。しかし、戦いが始まってから2カ月たった9月、家康は長篠城を攻め落としました。そして、山家三方衆で最も力の大きかった奥平氏に娘を嫁がせて味方につけ、娘婿となった奥平信昌に長篠城の守護を命じました。
武田氏の跡を継いだ勝頼としては、これを見逃すわけにはいきません。武田の勢力を再び拡大するためには長篠の再奪取が必須。1575年、大軍を率いて三河に侵攻した勝頼は、三河北部にある足助城を攻略。その後は武田信豊、山県昌景と合流して長篠城に軍を進めました。長篠・設楽原の戦いの始まりです。
このとき勝頼の兵は1万5000。対して長篠城の守備隊はわずか500。長篠城は豊川と宇連川が合流する三角地帯にあり、川と崖に囲まれた堅固な城として知られていました。1573年に家康が攻め入ったときも、落城まで2カ月かかっています。奥平信昌も城の堅固さをもって必死に守りますが、兵力の差は歴然で、城の郭は次々に攻め落とされていきます。このままでは、落城は時間の問題。信昌は主君にあたる家康に援軍を送るよう書状をしたため、忍びの者に持たせました。
ここで、家康は決断を迫られます。東三河の要衝であり、武田氏との激闘の末手に入れた長篠城が、いつ攻め落とされるかわからない状況。すぐに援軍を出すというのが選択肢のひとつです。ただ、家康が動員できる兵力は約8000。城を守っている信昌の軍と合わせても、勝頼の兵力には及びません。
同盟を結んでいる信長に援軍を求め、その到着を待つというのがもうひとつの選択肢です。救援はせずに長篠城を断念するというのも手としてはありますが、実質、東三河を放棄することになるため、これは選びにくいものです。
明らかな劣勢の中、兵糧も減っていき、一日一日と城内は疲弊していきます。勝頼が城を攻め落とす前に、一刻も早く援軍を出したいところです。しかし結局、家康はそうはせず、信長に援軍を求め、その到着を待つという判断を下しました。
信長はこの頃、畿内での対応に追われ、決して余裕がある状況ではありませんでした。しかし、1万もの兵を従えて出陣します。2年前の三方原の戦いで家康は信長の援軍を得たものの、兵が少なく惨敗した苦い経験があり、十分な兵をすぐに出すよう信長に強く求めた節があります。
信長の援軍を得た家康は、長篠城の西にある設楽原で武田軍と相対しました。この戦いは従来、鉄砲を装備した近代的な家康・信長の軍が旧態依然とした武田の騎馬軍を破った、という解釈をされていました。近年は研究が進み、武田軍も鉄砲を持っていたものの、弾薬の量に差があったという見方がされるようになっています。
長篠・設楽原の戦いに勝利した家康は三河、遠江での勢力を確かなものにしていきました。長篠・設楽原の戦いが、戦国時代の分岐点とも言われる理由です。
ビジネスでは近年、スピードをもって事業を進めることが重要視され、即断即決・即実行が基本的なスタンスになりつつあります。多少準備が整っていなくても、すぐ実行に移すことが重要なケースも少なくないでしょう。
しかし、すぐ実行に移せば成功につながるわけではありません。準備が整っていないために失敗する可能性が高いと判断される場合は、準備が整うまで「待つ」ことが重要になります。
家康は、長篠・設楽原の戦いで長篠城を守る奥平信昌から援軍を求められました。城の状況を見れば、すぐにでも援軍を出すべきだったでしょう。しかし冷静に兵力の差を考えるとそこですぐ動くことは危険であると判断した家康は、信長の援軍を待つことにしました。もし家康が信長の援軍を待つことなくすぐに手元の兵を動かしていたら家康の運命は大きく変わっていたことでしょう。
即行動するのではなく、準備が整うのを待つ。ときにはこの判断が重要になることを、長篠・設楽原の戦いで家康は見せてくれています。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント