
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
武将の側(そば)に仕え、諸事をこなす家臣を近習(きんじゅ)といいます。戦国武将の多くが小姓衆、馬廻衆などの近習を側に置いていました。中でも最も大規模で組織化された近習団をつくり上げていたのは、織田信長でした。
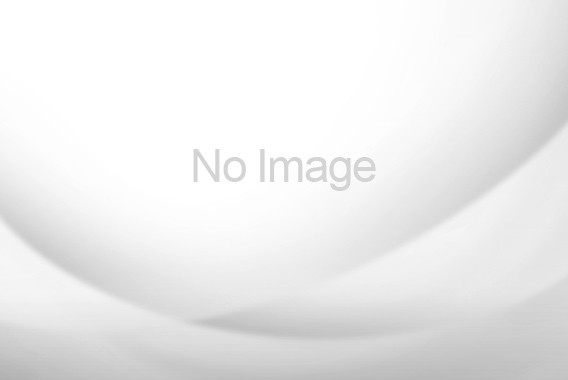 信長は、訪問客をもてなす者、信長の名代として使者の役割を果たす者、書状を作成する者、会議の取りまとめをする者など、さまざまな近習を置いていました。イエズス会の宣教師として来日していたフロイスは、岐阜城の信長を訪問したとき、100人以上の近習が広間にいたことを印象的に書き記しています。
信長は、訪問客をもてなす者、信長の名代として使者の役割を果たす者、書状を作成する者、会議の取りまとめをする者など、さまざまな近習を置いていました。イエズス会の宣教師として来日していたフロイスは、岐阜城の信長を訪問したとき、100人以上の近習が広間にいたことを印象的に書き記しています。
天下統一を掲げ、勢力を伸ばしていた信長の下では、版図(はんと/領土の意味)の拡大と家臣の増加により、多くの業務が発生していました。大規模な近習団をつくることで、そうした膨大な業務を処理していたのです。
信長は近習を重視し、諸部門の責任者ではなく、現場で諸事に当たっている近習を積極的に自分の側に置きました。そして近習に重要な情報を伝え、近習がどのようにその情報を処理したかを見ます。これが、信長の状況を判断する材料の1つになりました。
近習として側に置く者に関して、信長は身分にこだわりませんでした。典型的な例が蒲生氏郷(がもう うじさと)です。信長と敵対していた六角氏の重臣だった蒲生賢秀(たかひで)は、1568年の観音寺城の戦いで信長に破れ、息子の氏郷を人質として差し出します。信長は敵側が差し出した人質の氏郷が持つ資質を見抜き、武芸だけでなく儒教や仏教、茶の湯まで学ばせます。
こうした信長の期待に応え、氏郷は1569年の大河内城の戦いで初陣を勝利で飾ると、小谷城攻め、長篠の戦いなど、本能寺の変で信長が没するまで信長の下で戦いを続けました。信長亡き後の蒲生氏郷は、会津の大名となり同地の発展に寄与しました。その他にも越前国東郷を治めた長谷川秀一、越前国北庄の堀秀政といった近習から各地の大名となった有能な人材がいます。
信長のライバルだった武田信玄も近習を上手に活用していました。その象徴が奥近習のシステム。これは、近習の中から選抜した者を集めた一種のエリート集団です。信玄は奥近習に戦場の偵察から仕官志望者の面接、家臣の人事評価まで担当させていました。
奥近習には、信玄が重臣と開く秘密会議を傍聴することを許可したとあり、いかに奥近習を重く見ていたかが分かります。信玄の奥近習は、土屋昌続らのいわゆる奥近習六人衆のほか、徳川の大軍を2度にわたって破った名将・真田昌幸などを輩出しています。
戦国時代をけん引した信長と信玄が、ともに近習を重視した人材登用・育成システムを整えていたのは興味深いところです。そして、このシステムは現代のビジネスにも通じるものがありそうです。
企業のトップはそのすべてに責任を持たねばなりません。しかし、トップ個人の能力には限りがあります。会社が大きくなればトップを補佐する組織が必要です。そのためには判断を助け、手足のごとく動く必要があり、同じ情報に基づいていなければなりません。
信玄が重臣との秘密会議を奧近習に傍聴させていたのは、重要な情報を現場と共有することとともに、そのような場に同席させることで組織に大きく関わる人材であるとの自覚を持たせる意味もあったと思われます。
こうした人材は、指揮するセンスが磨かれ、経営者として大局観を養うことになるでしょう。それにより次代の経営を担う実力が養われます。戦国時代を代表する2人の武将がつくり上げた人材登用・育成システムは、現代のビジネスにおけるマネジメントのヒントになりそうです。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント