
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
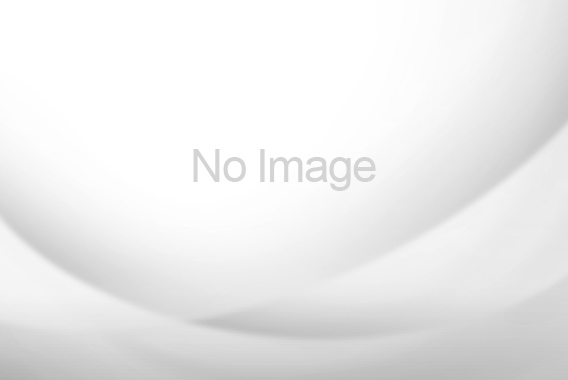
本拠とする甲斐(現・山梨県)から信濃(現・長野県)、駿河(現・静岡県)、遠江(現・静岡県)、三河(現・愛知県)へと版図を広げ「甲斐の虎」との異名を持つ武田信玄は、仏教に深く帰依した武将でした。
信玄は生涯で幾人もの僧を師としましたが、中でも大きな存在だったのが岐秀元伯(ぎしゅう・げんぱく)と快川紹喜(かいせん・じょうき)です。
信玄は1521年、甲斐国守護・武田信虎と大井夫人の間に生まれました。教育熱心だった大井夫人は、尾張(現・愛知県)の瑞泉寺にいた名僧・岐秀元伯を鮎沢にある大井氏の菩提寺・長禅寺に招き、幼い信玄の教育係とします。
聡(さと)かった信玄は、武士の子弟の教育に使われていた往復書簡集「庭訓往来」を数日で読み終えてしまいました。
それに飽き足らず、信玄は岐秀元伯から儒教の基礎教典である四書五経や兵法書「孫子」「呉子」などの教育を受け、政道、君子の心得、兵法、そして禅の教えを身につけます。信玄といえば孫子の兵法で有名ですが、それは幼き日の岐秀元伯の教育が基になっています。
長じて武将として活躍するようになってからも、信玄は岐秀元伯を師として敬い続けました。1552年に母・大井夫人が亡くなると、信玄は甲府に新たに長禅寺を創建し、岐秀元伯を迎えます。信玄は1559年に出家しますが、それまで名乗っていた晴信に「信玄」との法号を授けたのも岐秀元伯だといわれています。そして、1562年に岐秀元伯が亡くなるまで、師弟の関係が続きました。
岐秀元伯の後に信玄が深い絆を持った僧が、快川紹喜です。
快川紹喜は若い頃から俊才として知られ、美濃(現・岐阜県)で修行を重ねた後、京都の妙心寺に入山。2人は1554年に甲斐の恵林寺で初めて顔を合わせ、意気投合。1564年に信玄が甲斐に招きました。快川紹喜は仏門の師として、また相談役として信玄を支え続けます。
2人が知り合って間もない頃のこと。信玄は快川紹喜の器量を測ろうと、座禅を組んでいる背後に忍び寄り、刃を突き付けました。しかし、快川紹喜は泰然としてピクリともしません。そして一言言いました。「紅炉上一点の雪」。
これは中国の禅の問答集「碧巌録」に出てくる言葉で、元は「荊棘林(けいきょくりん)を透る衲僧家、紅炉上の一点の雪の如し」となっています。修行という荊(いばら)の道を行く僧には、燃え盛って紅くなった炉に一点の雪が舞い落ちるとすぐに溶け去るように、煩悩や執着といったものがさっとなくなるという意味です。
そして、このように付け加えました。「一軍の将が軽々しく刀に頼るようではいけません。大切なのは心の修養です。今後自ら刀を取るようなことがありませんよう」。
後の1561年、信玄は川中島の戦いで上杉謙信と相対します。このとき自ら武田の本陣に攻め入った謙信は、信玄に太刀で襲いかかりました。謙信が「刀で斬りつけられて死が迫った心境はどうだ」と言うと、信玄は刀を鉄扇で振り払い「紅炉上一点の雪」と答えます。
このエピソードは後の世の創作と見られていますが、快川紹喜との話が基になっていると考えられます。
信玄は領国経営に戦陣にと多忙な日々を送りますが、折に触れて快川紹喜の元に参禅に訪れ、周囲から臨済の教えを会得していると評されるほどになりました。
快川紹喜も信玄からの求めに応じて助言を与え、信頼と友情に支えられた関係は1573年に信玄が没するまで続きました。信玄の死は本人の意向により3年秘されていましたが、1576年に執り行われた葬儀は快川紹喜が務めています。
信玄の死後も、快川紹喜は武田家を支え続けました。しかし、自らと対立する勢力をかくまっているとの理由で1582年、織田信長が恵林寺を包囲し、火を放ちます。そして「心頭滅却すれば、火自ずから涼し」との有名な言葉を遺し、多くの僧と共に火に包まれました。
信玄は快川紹喜から多くの教えを受けましたが、その1つが「紅炉上一点の雪」に象徴される動じない心だったように思われます。
快川紹喜は「火自ずから涼し」のエピソードにも表れているように、炎の熱風に囲まれても動じなかった人物。出会って間もない信玄から刃を突き付けられたとき、この境地を「紅炉上一点の雪」の一言で快川紹喜は信玄に見せていました。
一軍の将、一国のあるじがささいなことで右往左往していては、的確な判断ができません。部下に不安を与えることにもなります。快川紹喜が自らの姿と言葉を通じて信玄に教えた動じない心は、現代の経営者やマネジメントに携わる者にも通じる上に立つ者のマインドセットとして、また人として生きる上で大切な心構えとして、今に通じる教えなのではないでしょうか。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント