
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
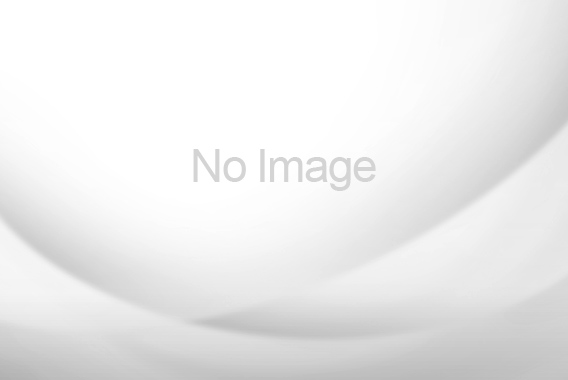
NHK大河ドラマ「麒麟がくる」は、新型コロナウイルスの影響により6月14日から放送休止になっていましたが、8月30日から放送が再開されました。ドラマの中では桶狭間の戦いが終わり、信長が勢力を伸ばしていく佳境に入っていきます。
応仁の乱の前後から室町幕府・将軍の権力が衰え、地方の有力大名が力を増していったことが戦国時代を招いた要因の1つでした。「麒麟がくる」で、権力が衰える室町幕府の中枢にいるのが、向井理さん演じる室町第13代将軍・足利義輝です。
義輝は1536年、12代将軍・足利義晴の子として、京都で生まれました。義輝は幕府のナンバー2のポジションである管領の細川晴元、そして細川家の家臣・三好長慶と戦いを繰り広げていました。戦いが不利な状況になると近江(現・滋賀県)に逃れ、京と近江の間を行ったり来たりする日々を送っていました。足利将軍の権威が落ちていたことが如実に分かる状況です。
義輝は1546年に父・義晴から将軍職を譲られますが、将軍となった後も細川・三好と対立する状況は変わりません。京から逃れることが増え、近江での日々が長くなります。義輝はこの頃、武芸に励み、剣豪として名高い塚原卜伝から免許皆伝を受け、剣聖と呼ばれる上泉信綱からも教えを受けたといわれています。「剣豪将軍・足利義輝」といった勇ましい呼び方を聞いたことがある方も多いと思います。
義輝がようやく京に落ち着いたのは、1558年のことです。近江の大名・六角義賢の仲介によって義輝は長慶と和睦し、京都へ戻ることになりました。京に入るのは、実に5年ぶりのこと。ここから、義輝は御所で幕府政治を再開することになります。
義輝が力を注いだのは、幕府の権威の回復です。義輝は各地の武将と友好関係を築き、幕府の存在を示そうとしました。
その手段の1つが、名前の一字を与える「偏諱(へんき)」です。義輝は、自分の名前の一部である「輝」の字、あるいは足利将軍家で代々使われてきた「義」の字を家臣や諸大名に与え、幕府・将軍の権威を示そうとしました。名前が知られている戦国大名では、「輝」の字を伊達輝宗、上杉輝虎(のちの謙信)、毛利輝元などが、「義」の字を三好義継、島津義久、最上義光などが使っています。
また、武将同士で抗争が起きたときは、積極的に調停に乗り出しました、武田信玄と上杉謙信、徳川家康と今川氏真、島津家と大友家など数々の抗争の間に入り、将軍の名の下に調停を進めることで幕府の権威を高めようとしました。
そのほか、幕府の財政長官である政所執事にも自分の親戚筋を充て、財政に関しても将軍の力が及ぶようにするなど、室町幕府・将軍の権威回復に努めています。
しかし、義輝も時代の流れを止めることはできませんでした。1564年に三好長慶が亡くなると、三好家の重臣・松永久秀、そして三好長逸・三好宗渭・岩成友通の「三好三人衆」らが将軍復権を進める義輝と対立を深めます。
1565年、久秀の息子・松永久通、そして三好三人衆の軍勢が義輝の御所を取り囲みました。その数、約1万の軍勢。対する義輝にはわずかな側近しかいませんでした。塚原卜伝から教えを受けた義輝は、この状況でも足利将軍家伝来の名刀を畳に刺し、次々に敵を斬り続けたといわれています。司馬遼太郎は、『国盗り物語』の中で、歴代の征夷大将軍の中で自ら刀を振るって戦ったのは義輝だけだろうと評しています。
しかし、圧倒的な軍勢の差は義輝にも覆すことができません。四方から三好・松永の兵に攻め寄られ、斃(たお)れました。その8年後、1573年に室町幕府は15代将軍・足利義昭でその歴史に終止符を打ちます。
今のビジネスに即して見ると、室町幕府は創業から230年を越える老舗の名門企業ということができます。父の跡を継ぎ、その大企業の13代社長に就任したのが義輝でした。しかし、義輝が社長になったとき、すでに名門企業の屋台骨は揺らぎ、厳しい状況に置かれていました。
現代の企業でも事業承継が大きな問題になっています。後継者がいなかったり、たとえ、いたとしても経営者に適していなかったりするケースも珍しくありません。しかし、名門企業“室町”の場合、後継者として義輝が存在し、将軍(社長)に適していたように思えます。
1558年に京に落ち着いてからは数々の抗争の仲裁に取り組み存在感を示していますし、武芸にも秀でた人物でした。しかし、大きく傾いていた“室町”という会社を復活させるには、すでに時機を逸していたようです。歴史に「もし」はありませんが、義輝のような存在が、少し前の時代に登場していれば、戦国大名の台頭を防ぎ、室町の運命は変わっていたかもしれません。
組織の力は失われ始めると、ある時点からその勢いが加速し、衰退に歯止めをかけることができない状況になることがあります。今、長い歴史を持ち、安定的に経営ができている老舗企業、大企業であっても油断はできません。難しいことですが、将来の危機を早く察知し、その芽を早めに摘むことができるリーダーが組織の存続に求められます。明らかな下り坂になった時点では、能力があるリーダーが指揮を執ったとしても、その流れをくい止めるのは非常に難しいのです。義輝と室町幕府の最期を見ると、そのことに思いを至らせずにはいられません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント