
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
新年明けましておめでとうございます。新しい年の到来を祝う風習は、日本では6世紀にはすでにあったといわれており、戦国武将も正月を祝っていました。
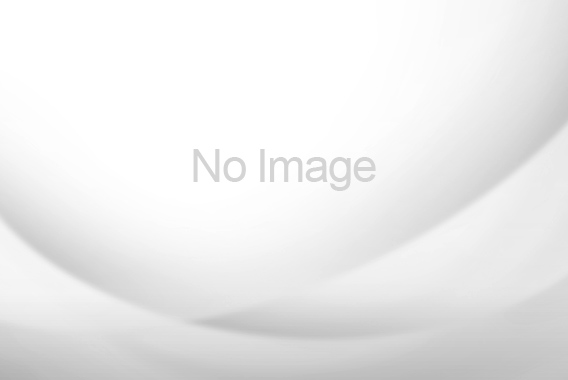
戦国時代の正月は、諸将が新年の挨拶に主君の元を訪れ、宴が開かれます。こうした新年の宴席で、織田信長の前に運ばれてきたお膳に箸が1本しか置かれていませんでした。信長は怒りをあらわにし、場が凍りつきます。
そこで声を出したのが、末席にいた豊臣秀吉でした。「これはめでたいこと。片箸で膳を平らげる、すなわち片っ端から諸国を平らげることを表しているのでありましょう」。この一言で信長は機嫌を直し、再びなごやかに新年を祝う席になったというエピソードが残っています。
私たちが正月を過ごす風習の中には、戦国武将と関わりのあるものが少なくありません。
正月の代表的な遊びの1つが、たこ揚げです。このたこは、武将と深い関わりがあります。戦国武将は、敵陣との距離を測るための測量器、のろし代わりの通信手段としてなど、さまざまな用途でたこを使っていました。また、土佐の長宗我部氏は攻城戦において糸の風切り音で敵を威圧したという話も残っています。
たこはこのように武士が戦(いくさ)のために使ったり、貴族が遊びとして使ったりするもので、江戸時代に入ってからようやく一般の町民が手にするようになりました。
正月に食べる雑煮も、戦国武将と関わりがあります。雑煮は元々、京都の公家が祝いの席で食していたものでした。それを武家が取り入れ、やはり江戸時代になって庶民に広まりました。グルメとして伊達政宗の雑煮には、アワビ、ナマコ、ニシン、ごぼう、角餅などが入っていたといわれています。
尾張国(現・愛知県)では名(菜)を上げるよう餅菜を入れ、ミソをつけないために汁はすまし汁で、城(白い餅)は焼かないようにするなど、戦国武将は縁起を担いだ雑煮で新年を祝いました。
正月、家の門の前などに門松を飾るようになったのは、室町時代のこと。当時の門松の竹は、上部を真横に切った寸胴型でした。それが現在のような竹の上部を斜めに切ったそぎ型になったのには、徳川家康が関係しています。
1572年12月、上洛しようと遠江国(現・静岡県)に侵攻した武田信玄に、家康が相対します。この三方ヶ原の戦いは家康軍が大敗し、家康は命からがら敗走。信玄はこの戦いの後、新年の挨拶として家康に歌を送りました。
「松枯れて竹類なきあしたかな」
松は、松平家の当主だった家康をさします。家康が滅びてこれからは竹(武田)が比類なく繁栄するという内容です。
これを見た家康は、怒りを込めて歌を返します。
「松枯れで武田首なきあしたかな」
松平は滅びず、明日には武田の首がなくなる、ということです。そして飾ってあった門松の竹を武田家になぞらえ、信玄の首を切るかのように家康は竹を斜めにそぎ落としてしまいました。その後、繁栄を見たのが家康だったのはご存じの通りです。そして家康にあやかって栄えるよう、門松の竹はそぎ型が使われるようになりました。
門松は、年神を家に迎えるために飾られるものです。そして松の内が過ぎて年神を見送ったら、お供えしていた鏡餅を割る鏡開きを行います。
鏡開きでは、刃物を使わず木づちなどでたたいて鏡餅を割る習わしになっています。この習慣も武士から来たもの。刀で餅を切るのは切腹を思わせ、縁起が良くないとされたことからこのような形になりました。また、割るという言葉も縁起が良くないため、「家運を開く」にかけて「鏡開き」と呼ぶようになったといわれています。
このように、正月の習慣のいくつかは縁起を大事にする戦国武将が関わっていました。雑煮を食べることも、門松を飾ることも、鏡開きも、すべて縁起担ぎの一種と考えることができます。
縁起担ぎは、非科学的でたわいない自己暗示のように思われるかもしれません。しかし、自分には神様が付いている、自分の運は開けるという自己暗示は、一寸先の情勢も定かではない戦国の世にあって自分を支える1つの力になったことを武将たちの縁起担ぎは示唆しています。
ビジネスの世界で、論理的な思考は不可欠です。さまざまな情報を元に論理的に考えることが成功への近道であることは間違いないでしょう。
しかし、戦国の世が少し先の情勢を見通すのも難しかったのと同じように、多様な要素が複雑に絡み合っている現代においても、たとえ論理的に考えても世界には不確実性が必ず残ります。そのような世界の中で判断を下すとき、縁起担ぎのような自己暗示は自分を支える1つの力になってくれるのかもしれません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント