
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
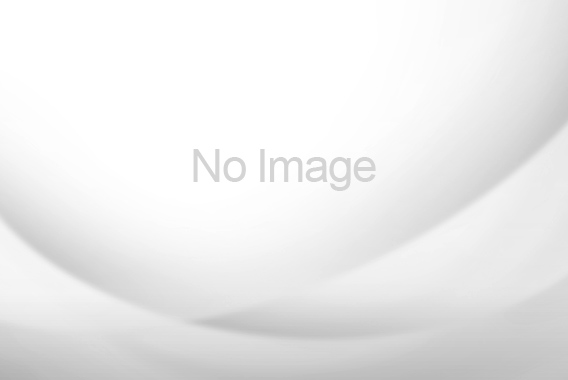
個性あふれる武将たちがしのぎを削った戦国時代。そこには各将の華々しい活躍とともに、数々の失敗がありました。そうした武将の失敗から現代の経営者やビジネスパーソンが学ぶべきことを考える「戦国武将の失敗学」シリーズ、第1回のテーマは「後継」です。
企業において、事業承継は大きな問題です。経営者が優秀で存在が大きいほど、誰に、いつ事業を継がせるのかが企業の命運を大きく左右することになります。これは、戦国時代の武将も同じでした。
後継に失敗した武将として名前が挙がるのが、上杉謙信です。謙信は約70戦して負け戦が2回だけだったといわれるほどの圧倒的な戦績を誇り、軍神との異名を持つ武将。武田信玄と1553年から5度にわたって戦いを繰り広げた川中島の戦いは有名です。1577年の手取川の戦いでは柴田勝家率いる織田軍を撃破し、その強さを改めて知らしめていました。
しかしその翌年、謙信は急死してしまいます。謙信は一生不犯で通し、正室も側室も置かなかったため実子がありませんでした。その代わり養子をもらい受けており、その中から跡を継ぐ者を探すことになります。
4人いた養子のうち、2人はすでに他家に入っていたため、候補は景虎と景勝の2人に絞られました。景虎は関東の名門・北条氏の出身。謙信が北条氏と同盟を結んだとき、関係強化のため上杉氏に入りました。一方、景勝は謙信の姉・仙桃院の子で、どちらも有力です。
景虎と景勝は家督をめぐって対立。家臣も景虎派と景勝派に分かれ、1578年、御館の乱に発展します。この戦いは当初景虎が優勢でしたが、景虎側に付いていた武田勝頼と景勝が和睦を図り、勝頼が戦を離れたことから戦況が変わり、景勝の勝利に終わりました。
景勝が当主となって後継者争いには決着がついたものの、家を二分しての激しい戦いは足掛け3年に及び、上杉家は疲弊。最強を誇った上杉軍は戦力を落とし、織田信長に攻め込まれて大きく領地を失い、衰退の一途をたどることになりました。
謙信の死は急に襲った脳卒中のためとされており、謙信自身も予期していなかったのでしょう。しかし実子がない中、いつ命を落としてもおかしくない戦国の世において、48歳という年齢になっても後継者を明確にしていなかったのは謙信の落ち度でした。
家臣の中には景虎派も景勝派もいたにせよ、謙信が景虎、景勝のいずれかを家督を継ぐ者として明確に指名していたら、家を二分して血を流して争うような事態を避けられた可能性は十分にあると思われます。
後継に成功しなかったという意味では、謙信のライバルである武田信玄も同じです。急死した謙信とは異なり、信玄は長く病を患っており、死が迫っていることを悟ったときに遺言をしました。
自分の死を3年間秘すことというのが有名ですが、後継についても言及しています。当時7歳だった信勝が16歳になったら家督を譲るので、それまでは勝頼に代理を申しつけるという内容です。
信玄の子が勝頼で、信勝は勝頼の子。本来なら、勝頼を後継としてもおかしくありません。しかし、勝頼は母方の諏訪氏を継いでいるため、他家の後継となった人間に家督を譲ることを避けたとも、そもそも勝頼という人物を評価していなかったともいわれています。
そして、思慮深くあること、信長や家康の運が尽きるのを待ち、むやみに戦に走らないこと、戦を挑まれた場合は甲斐(現・山梨県)の領内まで引き入れて戦うことと、勝頼をけん制する言葉を遺(のこ)しました。
しかし、勝頼は信玄の遺言にあらがうように、他国に侵攻して戦を仕掛けます。織田領である東濃(現・岐阜県)の明知城、徳川領である遠江(現・静岡県)の高天神城を攻め落としたまではよかったのですが、三河(現・愛知県)に侵入して信長・家康連合軍と相対した長篠の戦いで惨敗。その後の外交面での失策もあり、長篠の戦いから5年後の1582年、武田家は滅亡に至ります。
後継者選びは、「誰に」とともに「いつ」が重要です。謙信はこの決断を遅らせたばかりか、結局、誰を後継とするかを明確にしないまま世を去ってしまい、家を二分する事態を招きました。現代のビジネスにおいても、早めに指名して内諾を得ておけば本人もリーダーとなるべく準備ができますし、組織内でも方向性が定まり、大きな混乱を避けることができます。正式な就任は取締役会の承認など規定に沿って行うことになりますが、「次はこの人」というコンセンサスを早めに取っておくことの重要性を謙信の例は示唆しています。
また、事業を承継すると、新しい経営者は変革に向かいがちです。もちろん、長い間に習慣化されてしまった悪弊など、変えた方がいい点は積極的に変えるべきでしょう。しかし理念や先の経営者の思い、長年の経験に基づく判断など、受け継ぐべきものや敬意を払うべきものもあります。勝頼は、信玄の思いや判断を受け継ぐことなく、結果的に家を滅ぼす道をたどりました。
後継者選び、事業承継は現代の企業の大きな課題ですが、その難しさは戦国の世にもありました。豊臣秀吉も54歳のときにようやくおいの秀次に関白の座を譲り、その後秀頼が産まれると秀次を自死に追いやり、今度は秀頼に家督を譲るという混乱ぶりでした。このとき秀頼は6歳。大坂の陣を迎えたときも11歳で、強力なリーダーシップを発揮できるわけもなく、豊臣側は一枚岩にならないまま徳川家康と対峙することになりました。その結果はご存じの通りです。
後継者選びの大切さ、そして事業を承継することの難しさを、戦国武将たちのエピソードは教えてくれます。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント