
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
さまざまな戦国武将を取り上げてきました本連載ですが、今回は「最初の戦国大名」ともいわれる北条早雲を紹介します。
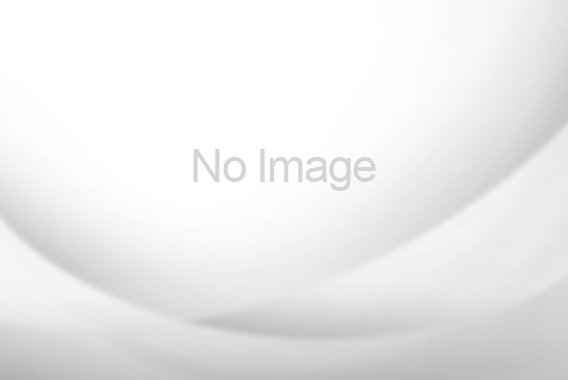 戦国大名とは、一般的に中央政府である幕府の支配から逃れ、実力で地方を支配し、支配地域を広げていった領主のことをいいます。15世紀末にそれを成した早雲は、戦国大名の先駆けと呼ぶにふさわしい存在です。さらに早雲は単に武力で支配を広げたわけではありません。そこには理想がありました。
戦国大名とは、一般的に中央政府である幕府の支配から逃れ、実力で地方を支配し、支配地域を広げていった領主のことをいいます。15世紀末にそれを成した早雲は、戦国大名の先駆けと呼ぶにふさわしい存在です。さらに早雲は単に武力で支配を広げたわけではありません。そこには理想がありました。
最初に北条早雲を紹介しますと書きましたが、歴史に詳しい方は「北条早雲」という呼び方が正確ではないことをご存じでしょう。早雲は「北条」とは名乗っていません。北条性になるのは息子の氏綱の代になってから。早雲自身は伊勢宗瑞(いせ・そうずい)と名乗っていました。しかし、この原稿では、なじみのある「北条早雲」を使わせてもらいます。
早雲の生年は1432年、1456年と諸説あります。出自についてもハッキリしていませんが、8代将軍・足利義政の申次衆を務めていた伊勢盛定の子として、備中国(現・岡山県)の高越城に生まれたという説が有力です。申次衆というのは、奏聞などを将軍へ取り次ぐ要職です。その関係で、早雲は京都で義政の弟・足利義視に仕えるようになります。
早雲が義視に仕えていた1467年、応仁の乱が起こります。足利家の後継問題に端を発した騒動は細川勝元と山名宗全の全面的な戦に発展し、京都を焼け野原にする大乱となりました。今でも、京都の人が「先の戦は大変だった」というときは、第二次世界大戦ではなく応仁の乱のことを意味するという話があるほど京都は壊滅的な打撃を受けます。
折からの飢饉(ききん)もあり、京都の街には餓死者があふれました。しかしこの状況を前にしても義視は保身に走り、有効な手を打てません。失望した早雲は、義視の元を去ります。
1483年、将軍の座を継いだ足利義尚の申次衆として再び足利家に仕えるようになりますが、いまだ京都は応仁の乱の尾を引いており、民が苦しんでいる状況は変わりません。民衆が幸せにならないこのような国でいいものか−−。このときの思いが、「最初の戦国大名」を生む背景になります。
結局、義尚の下も去った早雲は、妹が嫁いでいた駿河国(現・静岡県)の今川家に出仕しました。今川義忠の没後、今川家でも家督争いが起きますが、早雲はこの騒動を見事に収拾し、その功績により駿河の興国寺城を与えられます。
そして1493年、隣国である伊豆国(現・静岡県)にいた足利政知の長男・茶々丸を襲撃。伊豆国の覇権を奪い取ります。戦国時代の始まりとされる出来事です。これにとどまらず、早雲は1495年、大森藤頼を討ち小田原城を奪取。この小田原城は、室町末まで続く北条家五代の根拠地となります。早雲はさらに相模の豪族である三浦氏を攻め立て、滅亡に追い込み、相模全域を手中に収めます。
このように足跡をたどると権力欲にとらわれた地方領主が我欲のために支配地域を広げていったようにも見えますが、そうとは言い切れません。自分が力を及ぼす地域を広げ、民衆のためになる国を造る。早雲の統治の仕方を見ると、応仁の乱のときに感じたことを裡(うち)に秘め、理想の国造りに力を行使したように見えるのです。
早雲は、当時、五公五民や六公四民が当たり前だった税率を四公六民に下げました。つまり50%や60%から40%まで減税したのです。また、武将として初めて田畑の検地を実施。正確に把握した石高に基づいて年貢を徴収することで、領民の不公平感、不満をなくします。さらに、「不義不正を働く役人がいれば訴え出よ。その者を追放する」とまで言っています。これらは新田の開発を促し、結果的に税収が上がることになります。
早雲は民衆の健康にも気を配り、伊豆一帯ではやり病がまん延したときには駿府や京都から薬を取り寄せて治療に当たらせました。その他にも公共事業のための無償労働を廃止し、不作の年には穀類や資金を貸し出すなど早雲は民のための政治を貫きます。他国の人間が「我らの国も新九郎殿(早雲の通称)の国になったら」とうらやむほど、早雲は広く民衆の支持を集めました。
この早雲の善政が、家康の時代を迎えるまで五代にわたって続く後北条家の礎になったのはいうまでもありません。
早雲の姿を追っていると、起業家の姿に自然と重なってきます。足利家の幕府という巨大企業のやり方に納得できず、退職し、理想を実現するために会社を立ち上げた起業家の姿です。
幕府の支配下では働く民衆は必ずしも大切にされているとはいえませんでした。一方、早雲は相模一帯という自分の支配地域において働く民衆を豊かにするように施策を変え、モチベーションを上げることで、結果的に税収という利益を増やすことに成功します。また、福祉を充実させるなど当時の常識にはなかった革新的な方針を打ち出し、さらに民衆の支持を上げ、帰属意識を高めました。
領地の経営のためには働く人の満足度、幸福を高めることが最善である。当時の幕府を反面教師とし、早雲はこのことに力を尽くしたのではないでしょうか。
これは現在の企業経営にもまったく同じことがいえるように思えます。「ブラック企業」のように従業員を無理に働かせて、利益を上げる企業には未来はありません。長期的に経営を安定させたいのなら働く側の満足度を高める。このことを早雲から始まった北条家の隆盛は語りかけているのではないでしょうか。
戦国大名というと、民衆の迷惑を考えず戦に明け暮れていたイメージもあるかもしれません。しかし、その第一号といわれる北条早雲は、民衆の生活を豊かにした名政治家だったのです。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント