
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
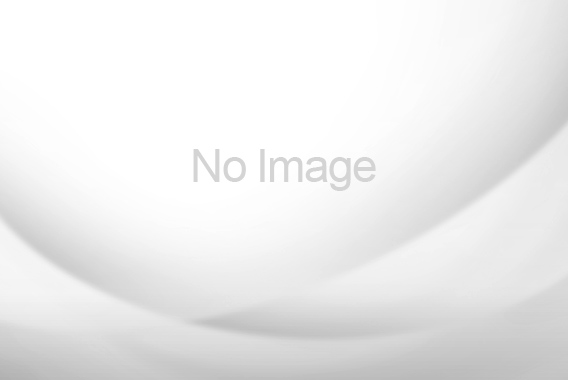
現代では、トラックや貨物列車を使っての陸上輸送が広く使われています。しかし、高速道路も鉄道もなかった戦国時代には陸上輸送に限界があり、大量の物資を運搬する際には海上輸送が主に用いられていました。
戦国時代初期の戦は、地方の豪族同士の勢力争いという側面が強く、遠方に大量の物を運ぶような場面は多くありませんでした。やがて有力武将が広域の覇権を争って戦うようになると、遠方まで大量の兵士、弾薬、武具、兵糧、あるいは軍馬などを運ぶ輸送力が重要な要素になります。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人の海上輸送を支え、大きな役割を果たしたのが瀬戸内の塩飽(しわく)水軍です。
塩飽水軍は、香川県と岡山県の間の備讃(びさん)海峡に浮かぶ塩飽諸島を拠点とする水夫たちで構成されました。彼らの本拠地は、塩飽諸島の中心に位置する本島(ほんじま)です。塩飽水軍はもともと、備讃瀬戸海峡から西寄りの能島・来島・因島を拠点とする村上水軍の傘下に入っていました。それが変わったのは、第一次木津川口の海戦後のことです。
石山本願寺をめぐって織田氏と毛利氏が戦った1576年の第一次木津川口の海戦では、「海賊」と恐れられた武将・村上元吉(むらかみもとよし)を擁する毛利軍に、織田軍が大敗を喫しました。
もちろん、これで黙っている信長ではありません。火矢を放たれた船が相次いで炎上したことが敗因の1つとなったことから、信長は志摩国(現・三重県)の九鬼嘉隆(くきよしたか)率いる九鬼水軍に鉄の装甲を施した鉄甲船の建造を命じます。それに加え、目を付けたのが塩飽水軍でした。
塩飽水軍はもともと村上水軍の配下にありましたが、信長が貿易港として栄えていた大坂・堺への入港を保証したことを契機に、信長との関係性を深めます。その後は兵や物資の運搬を担うなど、信長の石山本願寺攻めに協力。こうして迎えた1578年の第二次木津川口の海戦は、織田軍が勝利を収めます。以降、塩飽水軍は信長、そして信長の家臣である秀吉に仕えることになります。
1582年5月、塩飽水軍は秀吉の備中高松城の水攻めに協力しました。翌6月、信長が本能寺の変で明智光秀に討たれると、秀吉が光秀討伐に向かった「中国大返し」でも輸送に力を発揮します。備中高松(現・岡山県)から京都の山崎まで、約200kmを2万の兵を従えた大移動の裏には、塩飽水軍の存在がありました。
ここからは、秀吉の天下統一に伴走する形で塩飽水軍が活躍します。1585年には、秀吉の四国征伐に参加。1587年の秀吉の九州征伐でも船を出し、兵糧や軍馬などを大坂から薩摩に運んだ記録が残っています。
1590年の小田原攻めでは、籠城する北条側も攻撃する秀吉側も兵糧が鍵になりましたが、塩飽水軍が兵糧米を大坂から輸送して3カ月に及ぶ秀吉の攻撃を支え、天下統一実現の力となりました。
こうした一連の功績をたたえ、秀吉は塩飽水軍の船方衆650人に対して塩飽領1250石を与える朱印状を出します。これにより、塩飽は大名が頭に立つのではなく、船方衆が治める一種の自治領となりました。
秀吉は1598年に没しますが、秀吉の天下統一の過程を見ていた家康も塩飽水軍の力を無視するわけにはいきませんでした。1600年には秀吉と同じく塩飽領1250石を船方衆650人に与えました。
家康が豊臣家の滅亡を図った大坂の陣では、塩飽水軍が兵糧米を備中から堺に運び、家康を助けます。その後も大坂城の築城石、江戸城の修築石を塩飽から運搬する役割を担うなど、塩飽の船は徳川家を支え続けました。
塩飽水軍は類いまれなる技術力を生かし、巨万の富を築き上げました。時代の流れとともに役務の需要が減少した後、塩飽水軍たちは造船や建築で生計を立てるようになります。彼らによって建てられた神社や寺院のいくつかは、香川県や岡山県に今も残されています。
塩飽水軍のエピソードからは、大きく2つのことが学べます。1つは、大きなプロジェクトを成し遂げるには、基盤となる体制の整備が重要だという点です。兵士や物資を運ぶ戦国時代の海上輸送は、現代ではロジスティックに当たるものでしょう。ただ、視点を広くしてみると、体制づくりということになります。
秀吉が天下統一を進めるためには、四国征伐、九州征伐、小田原攻めが不可欠でした。そして、水軍を引き入れることでそれをするための体制をつくったと見ることができます。兵や兵糧などを運ぶ体制があって初めて、秀吉は天下統一を推し進められました。
企業で新規案件、プロジェクトを進めるときにも、そのための体制を整える必要があります。大事を成すためには、必要な体制を見極め、しっかり整えること。このことを、天下統一を進めた3人の武将の水軍にまつわるエピソードは示唆しているように思われます。
もう1つは、戦国の乱世を生き抜くための処世術です。いくら高い技術力を持っていても、その価値が他者に理解されなければ意味がありません。当時のキーマンたちの心をつかみ、時代が変わっても能力を発揮し続けた姿は、変化の激しい現代でも大いに参考になるでしょう。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント