
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
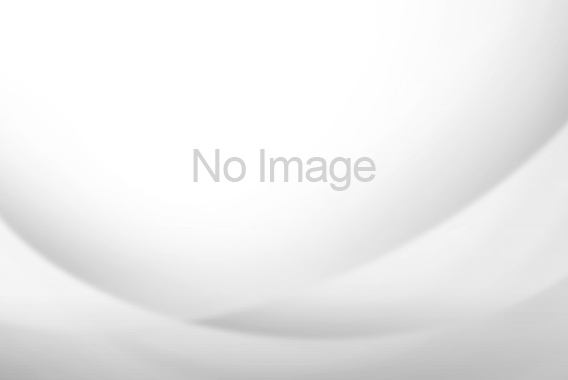
2020年1月に始まったNHK大河ドラマ「麒麟がくる」は、コロナ禍による中断を挟み、2021年2月7日放送の「本能寺の変」で幕を閉じました。本能寺の変で主役となったのは、織田信長を討った明智光秀であることは間違いありません。しかし今回は、京の都から離れた備中(現・岡山県西部)でこの変の直後に重要な役割を演じた小早川隆景に注目したいと思います。
小早川隆景は、1533年、安芸(現・広島県西部)から中国地方一帯に勢力を広げる毛利元就の三男として生まれました。元就の長男は隆元、次男は元春。隆景も含めたこの3人が、「一本の矢ではすぐに折れてしまうが、三本束ねれば簡単に折れない。三人で力を合わせて毛利の家を守るように」という有名な「三本の矢」の逸話に出て来る兄弟です。
長男の隆元は将来、毛利の家を継ぐことになるため、次男の元春は安芸の領主である吉川氏に養子として入りました。三男の隆景は同じく安芸の領主である竹原小早川氏を相続し、1550年には本家に当たる沼田小早川氏の家督を継承。水軍で知られる小早川氏の当主として、父・元就を支えます。
隆景の名を一躍高めたのが、1555年、厳島を舞台に元就と陶晴賢が戦った「厳島の戦い」です。隆景は自らの小早川水軍を率いて戦いに臨みましたが、それだけでは不利と見て村上水軍を味方に引き入れることに成功し、毛利軍の勝利に大いに貢献しました。
その後は元就の下で大内氏、尼子氏との戦いに加わり、1571年に元就が没すると、毛利の家を継いでいたおい・輝元の補佐役として兄の元春と共に各地を転戦します。
時代は、室町幕府が権威を失い瓦解に向かっていた頃。京を追われた将軍・足利義昭は、毛利家の領内にある鞆の浦(現・広島県福山市)に落ち延びます。義昭の強い要請もあって隆景は義昭が呼びかけた信長包囲網の一角となり、織田方と戦うこととなりました。
そして、運命の1582年。信長の命を受けた豊臣秀吉が、毛利家の配下である清水宗治の備中高松城(現・岡山県岡山市)に攻め入ります。しかし備中高松城は守りが堅く、秀吉軍もなかなか攻め落とせません。
そこで、軍師・黒田官兵衛の発案により秀吉は水攻めを敢行。近くの足守川をせき止め、備中高松城を水の中に孤立させます。窮地を知った隆景は輝元、元春と共に主力の3万の兵を率い、救援に赴きました。隆景らが到着すると、兵力は互角。膠着状態となり、秀吉は備中・備後(現・広島県東部)など5国の割譲と清水宗治の切腹を条件に毛利に和睦を提案します。
明智光秀が京都で信長に謀反を図ったのは、まさにこのときでした。
信長斃(たお)れるとの報を受けた秀吉は、情報が漏れないように道を遮断。自陣に対してもかん口令を敷き、毛利側に信長の死が知られないようにします。
秀吉は、京に向かって光秀を討つことを即決します。そのためには、背後から撃たれないよう、毛利との戦いをすぐに止めなければなりません。信長の死を隠したまま、秀吉は5国の割譲を3国の割譲に妥協した新たな案を毛利に提示。毛利側はこれをのみ、和睦が成立しました。
秀吉は光秀を討つため急いで京に兵を向けます。有名な「中国大返し」です。毛利側が信長の死を知ったのは、この頃だと言われています。隆景の兄・元春は秀吉にだまされたと怒り、追撃を主張しました。背後から襲えば、敵である秀吉に打撃を与えることができます。
しかし、隆景は首を縦に振りません。秀吉を追っても、すでに勢力を大きく伸ばしている信長・秀吉の勢を全滅させられるわけではない。毛利が信長の死を知りながら中国大返しを邪魔しなかったことをのちに秀吉が知れば、秀吉は恩を感じるであろう。何より、交わしたばかりの和睦を破れば、父・元就が毛利の家訓としていた「信義」にもとることになる......。
隆景は元春の説得に成功し、追撃させませんでした。
京に向かった秀吉は、山崎の戦いで光秀を討ち、その野望を打ち砕きます。そして隆景は秀吉の傘下に入り、秀吉の四国攻め、九州征伐などに参加。秀吉は隆景を非常に評価し、徳川家康や前田利家らと共に五大老の一人に任命しました。
また、秀吉の養子・羽柴秀俊を養子として迎え、家督を譲って小早川秀秋とするなど、秀吉と深い関係を結びます。そして、秀吉から与えられた筑前国(現・福岡県西部)に赴任したのち、地元の備後に移り、1597年に死去しました。
毛利の家は、先を見通すことにたけていたフシがあります。元就は次男・元春を吉川家に、三男・隆景を小早川家に養子に送り込みましたが、これはそれぞれ山岳戦に優れた家と水軍の家柄で、毛利が陸地戦にも海上戦にも対応できるようにすることを見越していました。
本能寺の変の報に接したとき、元春は秀吉追撃を主張したものの、隆景は兄の主張に反対しました。このとき、和睦の場に信長の死のことを一言も出さなかったとして、秀吉に怒りをあらわにした元春の感情も理解できます。しかし、隆景は父の「毛利の家は信義を守る」との家訓とともに、情勢を判断し、先のことを考えて「追撃ならず」との結論を出しました。
家督を譲った小早川秀秋は血こそつながっていませんが、やはり関ヶ原の戦いで東軍有利と判断し、豊臣方の西軍ではなく東軍側に付きます。これは養父の秀吉に対する裏切りとも見える行為ですが、結果的に小早川の家を存続させることになります。
人間は感情の動物です。ビジネスにおいても、感情に任せて判断を行ってしまうことがあり得ます。しかし、感情任せの判断は組織の将来という観点からは避けた方がいい。このことを、隆景は教えてくれているのかもしれません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント