
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
武将の象徴ともいえる城を造る名人からビジネスのヒントを考えるこのシリーズ。今回は、前回紹介した加藤清正と並んで築城の名人とうたわれる藤堂高虎をクローズアップします。
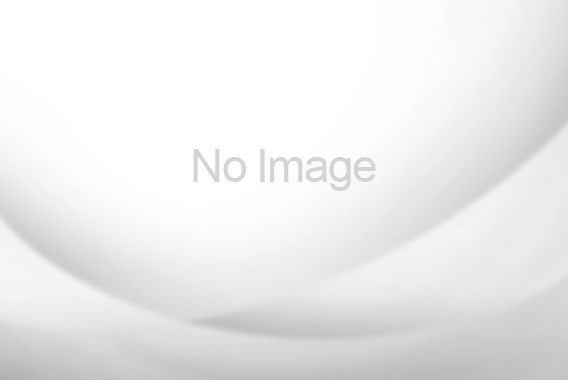
高虎は多くの主君に仕えた武将として知られています。浅井長政から始まり、阿閉貞征(あつじさだひろ)、磯野員昌、織田信澄と続き、豊臣秀吉の弟・秀長からは秀保、秀吉、秀頼と豊臣家の家臣となります。そして関ヶ原の戦いでは東軍に属して戦功を挙げ、家康からこれを認められて伊予国(現・愛媛県)で12万石を加増。伊予20万石の領主となりました。
高虎はそれまでも紀伊国(現・三重県)の赤木城、伊予国の宇和島城などで城の建築・改修に携わっていました。しかし築城の名人としての名を一気に高めたのは、伊予20万石の領主として1602年に築城を始めた今治城です。
今治城は、以降の城のスタンダードとなる画期的な城でした。その特徴の1つが、天守閣です。それまでの天守閣は望楼型が主流でした。望楼型の天守閣は、入り母屋造りの層を一層あるいは二層と積み上げ、一番上の層に望楼を乗せた形になっています。望楼型では入り母屋造りの屋根の真ん中を割って望楼を乗せているため、構造が複雑になります。そのため工事に困難が伴い、また風や地震に弱く、屋根裏のスペースが必ずできるため空間効率が悪いなどの欠点がありました。
そこで、高虎は新たな型の天守閣を創り上げました。同じ形の層を少しずつ小さくしながら積み上げていく、層塔型の天守閣です。入り母屋の破風は最上階の屋根にだけ付いている、シンプルな外観です。
屋根を割って望楼を乗せる望楼型と比べ、同じ形の層を積み上げる層塔型は構造が単純で、つなぎ目が少なく、強い造りにすることができます。また、材木を規格化し、プレハブのように事前に各層ごとに加工しておくことができたため、短い工期で費用を抑えられることにもなります。
関ヶ原の戦いのあと、新たに所領を与えられた大名が全国の任地で城を造り、「慶長の築城ラッシュ」と呼ばれる事態になります。そこで多く採用されたのが、効率的な層塔型の天守閣でした。以降、高虎の層塔型は天守閣建築の主流となっていきます。
今治城がその後の城のスタンダートになったのは、天守閣だけではありません。幅の広い堀も、その1つです。
それまでの城は、戦いのときに防御がしやすいよう、山城が多くなっていました。山城は山頂や山腹などに造るため、水を引くことが難しく、城にめぐらせる堀には深い空堀がよく用いられました。
それが徳川の世になり、領内統治に都合のいいよう、城は山地ではなく平地に多く造られるようになります。平城です。しかし、戦いになったときのことを考えれば、城から防御の機能を外すことはできません。そこで採用されたのが、幅の広い堀でした。
今治城は、瀬戸内海の海岸近くに位置しています。高虎は瀬戸内海の海水を引き入れ、最大70メートルもの幅を持つ堀を三重にめぐらしました。中心に位置する本丸は、堀に囲まれた島にあるようなイメージです。平地にある、幅の広い堀に囲まれた城というスタイルも、これを機に主流になっていきます。
高虎は築城だけに優れていたわけではありません。これからの時代、城は戦の場ではなく、町の中心となり経済の発展を担うべき存在となることを知っていました。そこで、城に隣接した地域に、碁盤目に街路を配して城下町を整備。職人や商人を誘致し、商工業の発展を図りました。
高虎は1611年、伊勢国(現・三重県)の津に移封されますが、彼の地でも手腕を発揮します。津には織田信包が建てた津城があり、これを近代的な城郭に改修。高い石塁を築き、天守閣には手を着けませんでしたが、層塔型の三重の櫓を東北と西北の隅に設けます。
そして、城の周囲に武家屋敷のエリアを設け、伊予から連れてきた商人を住まわせて伊予町とするなど、城下町の整備も進めました。また、町外れを通っていた伊勢神宮参拝のための参宮街道を城下に引き入れ、城の東に堀川を切り開くなど、伊勢音頭に「伊勢は津でもつ 津は伊勢でもつ」と歌われた津の発展の基礎を築きました。
関ヶ原の戦い以降、数千とも言われる城が新たに建てられる中、高虎の城はひとつの典型となりました。その理由は、その時代の必要性に的確、かつシンプルに応えていたからだと思われます。
従来の望楼型の天守閣は、意匠的には優れた面があったものの、空間利用の点でも普請の上でも効率的とはいえませんでした。無駄の少ない空間を早く、安くつくることができる層塔型は、新しい時代の城として、各地の大名の必要性にマッチするものでした。
また、幅の広い堀は、平地に造る城で防御を固めるためのシンプルなソリューションです。平地に造る平城は山城のように地形で守ることが難しくなりますが、だったら弓矢が届かないほどの距離を設ければいいという発想です。
そして、城に求められる役割が戦の拠点から町の発展の中心へと移りつつあったことを明確に意識し、城下町を整備しました。
高虎が生きたのは、戦国大名が覇権を争う戦国の世から、徳川が天下を治める世へと移り変わる時代でした。そして、時代が変わると新しい必要性、ニーズが生まれます。
高虎が生きたときほど劇的ではないかもしれませんが、今も常に時代は動いています。その中で生まれているニーズに的確に応えれば、それが新しい普遍となる。高虎の城はそのことを示唆しているように思われます。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント