
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
戦国武将は、多くの家臣を束ね、率いるリーダーでした。家臣が社員だとしたら、武将は経営者。豊臣秀吉の「秀吉株式会社」は、業界のトップに上り詰めたメガベンチャーともいうべき存在でした。「秀吉株式会社」を分析する本連載。第4回は「海賊停止令」を取り上げます。
前回紹介したように、秀吉は1588年に「刀狩令」を発し、農民や僧侶から刀などの武器を没収しました。そして同時に出したのが「海賊停止令」でした。
海賊というと、船を襲って積み荷を強奪する集団といったイメージがあるかもしれません。もちろんそうした海賊もいましたが、彼らは別の役割も果たしていました。
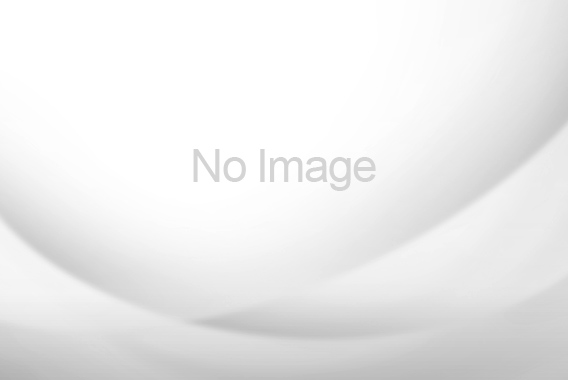
室町時代に行われた勘合貿易(日明貿易)において、室町幕府は沿岸の海賊に警備を依頼していました。こうした海賊衆は警固衆(けごしゅう)と呼ばれ、幕府から警固料を受け取っていました。平時は漁業を行い、必要に応じて貿易船の警備をしたり、札浦(関所)で通行料を徴収したり、自ら交易を行ったりするのが海賊でした。
その後、室町幕府の権威が揺らいでくると、各地の海賊の地位が相対的に上がってきます。そして戦国時代に入ると水軍として活躍する海賊が現れ、どの水軍を味方に付けるかで武将の命運を左右するほどになります。
有名なのが石山合戦です。天下統一に向けて勢力を伸ばしていた織田信長は志摩の九鬼嘉隆が率いる九鬼水軍を味方に付けます。
1576年、信長は敵対する大坂の石山本願寺を九鬼水軍と共に包囲しました。一方、石山本願寺は信長と対立する毛利輝元に助けを求め、輝元は瀬戸内の村上水軍を中心とした船団を組みます。
この時は毛利方の水軍の勝利に終わりますが、2年後に再び戦火を交えた時は大砲を積んだ鉄甲船を新たに建造した九鬼水軍が勝利し、信長は長年の敵となっていた石山本願寺を追い込むことになります。水軍の力が、決定的に戦局を左右したのでした。
1582年に信長が本能寺の変で斃(たお)れた後、四国、九州を平定して天下統一にまい進していた秀吉にとって、力を持った海賊は自らの勢力をおびやかしかねない存在でした。そこで出したのが「海賊停止令」だったのです。
この令は、次の3つを海賊に迫るものでした。
・豊臣氏に従って大名となる
・豊臣政権の大名の家臣となる
・武装を放棄して百姓になる
併せて、海賊に与えられていた警固料を廃止し、札浦における通行料の徴収、許可のない海外貿易などの活動も禁止しました。これによって、海賊は大名、大名の家臣、百姓のいずれかの身分になり、独立した存在である海賊は姿を消すこととなりました。
この「海賊停止令」には、いくつかの目的を見ることができます。1つ目は、一揆対策。当時は、海賊も一揆に力を貸すことがあり、「海賊停止令」によってそうした事態を防ぐ意図があったと考えられます。同時に出された「刀狩令」は、農民から武器を没収することで頻発していた一揆を防ぐ意味合いがありました。
2つ目は、秀吉が自らの勢力を増強する意味もありました。当時、秀吉はかなりの地域を自らの版図(はんと)としていたものの、関東の北条氏は軍門に降っておらず、奥州も平定したわけではありませんでした。大陸進出という大きな野望のためにも、軍事力を強めておきたいという事情がありました。
3つ目が、独立勢力の吸収による再編だったのです。それまで海賊は大名の家臣という立場ではなく、独立した集団でした。ある大名の下で戦ったとしても、別の大名にくら替えすることもあります。このような独立勢力を、自らの勢力下に置こうとしたのがこの令でした。
現代のビジネスシーンに置き換えると、これは、マーケットシェアを順調に伸ばしたリーディングカンパニーがM&Aにより力のある中小企業を吸収合併し、経営基盤を固めることに似ています。
海賊は、各地の有力大名と比べれば勢力は小さいものの、特に海戦での軍事力、海路での移動・輸送力は侮れないものがあります。もし一斉に敵方に付けるようなことがあれば、非常に厄介なことになります。
マーケットシェアの過半を取ったとしても、優れた技術や商品を持っている中小企業をコンペティターが吸収合併すると、形勢が一気に変わってくることがあり得ます。そうした事態を避けるのに一番いいのは、有力な企業を先に吸収合併してしまうことです。
秀吉は、天下統一に向けて、どこに所属することもない海賊の存在を重く見ていました。そこで「海賊禁止令」を発令し、海賊という有力中小企業を「秀吉株式会社」グループの飛躍、経営基盤の強化のために組み込んだわけです。法令は強力な軍事力を背景とした強権的なものでしたが、海賊をリスペクトしているからこそ、戦闘行為で傷つけることなくグループに引き入れたと見ることもできるように思います。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント