
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
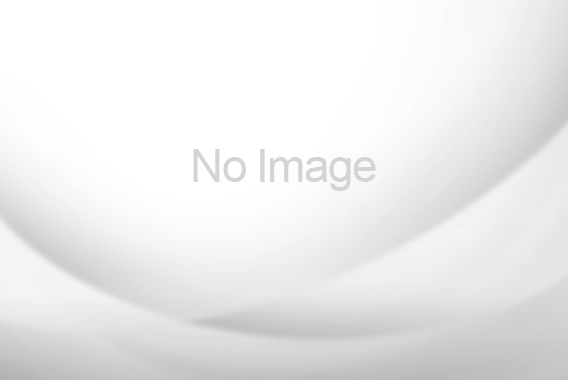
武田信玄、織田信長、豊臣秀吉……。戦国武将には強烈な個性を放っている人物が少なくありません。そうした中で異彩を放っているのが、九州の立花宗茂(むねしげ)です。宗茂はある意味、「普通」の人物。普通でも強い。普通だからこそ強い。そうした武将です。
立花宗茂は1567年、北九州の大名である大友宗麟(そうりん)の重臣・高橋紹運(じょううん)の長男として生まれました。
宗麟は一時、九州の半分を支配するほどの力を持ちましたが、1578年に耳川の戦いで島津義久に敗れ、以降、島津氏の勢いが拡大します。この島津氏に立ちはだかったのが、宗茂でした。1581年、宗茂は第二次太宰府観世音寺の戦いで立花道雪(どうせつ)とともに敵将の堀江備前を討ち、翌年の岩戸の戦いでも敵方の早良城を攻め落とすなど、早くからその才を見せつけます。
しかし、宗茂の名を高めたのは、1586年の島津氏との一連の戦いです。父・紹運は岩屋城の戦いで命を落としますが、宗茂は高鳥居城を落城させると、島津軍から岩屋城、宝満城を奪還。島津氏と対立していた豊臣秀吉の九州征伐を助け、秀吉から「その忠義、九州一、その豪勇も九州一」と激賞されます。そして、秀吉から筑後国(現・福岡県南部)に領土を与えられ、柳川城城主となりました。
関ヶ原の戦いでは、徳川家康から東軍に付くよう求められますが、秀吉への恩からそれを拒否。東軍の京極高次が守る大津城を攻め落とすなど戦功を挙げますが、西軍に付いたため、戦いの後に領地取り上げになりました。
しかし、宗茂の名声は広くとどろいていました。宗茂の武将としての力量と人望を耳にしていた徳川第2代将軍・徳川秀忠は、宗茂に謁見(えっけん)。陸奥国(現・東北地方北西部)に領地を与えます。
そして、宗茂は徳川方の将として大坂の陣に参戦。秀忠を補佐し、徳川の勝利に貢献しました。その功により再び柳川に領地を持つことを許され、1643年に生涯を閉じました。
宗茂は秀吉、家康から武将としての能力を高く評価され、戦国武将ファンの間でも「一番強かったのは、実は立花宗茂」との声が上がるほどです。しかし、宗茂は決して特別なことをしようとしたのではなく、普通であることを重んじた人物でした。
あるとき、息子の忠茂(ただしげ)が宗茂に軍法について尋ねました。宗茂は、「特別なことはない。日頃から下の者には子に接するように情をかけ、下の者から親のように思われていれば、下手な命令をしなくても思う通りに動いてくれるものだ」と答えたといいます。
同じようなエピソードは、徳川義直(よしなお)との間にもあります。義直は家康の九男で、尾張名古屋藩の初代藩主を務めた人物です。
義直も宗茂の戦歴を知っていますから、合戦の極意を宗茂に問いました。すると、宗茂は次のように答えました。「何も特別な軍法を用いているわけではありません。兵士にえこひいきせず、ひどい働きをさせず、慈悲をもって接し、多少の過失は見逃し、法に外れたら処する。私の高に応じているので大した俸禄(ほうろく)も出していませんが、それでも戦では命をかけて戦ってくれます」。
宗茂は武に秀でるだけでなく、茶道をたしなむなど、文化・芸術にも理解のある武将でした。茶道を通じて親しくしていたのが、同じ九州の武将である細川忠興(ただおき)です。
ある日、忠興は「あなたは、家中の統率で苦労したことがないと聞いている。いったいどのようにしているのか」と宗茂に尋ねました。
「私が良いと思っていること、悪いと思っていることを、家来や召し使いに言っているだけです。私が好むことしか家中の者はやりませんし、私が嫌うことはやりません。私がすることのまねをしますので、あれをしろ、これをやれと、いちいち指図しなくても大丈夫です」。これが、宗茂の答えでした。
宗茂の姿勢は、一言でいうと自然体。自分の軍功を誇るようなことも良しとしませんでした。「みな、戦場での働きは後になると大げさに言いたがるものだ。働きが足りなかったと思っているからこそ、そのように言うのだろう」と戒めています。
えこひいきしない。ひどい働きをさせない。慈悲をもって接する。ルールから外れたことをしたら罰する。何が良くて、何が悪いかという自分の基準をはっきりと伝える。宗茂が言っていることは、ある意味、どれも普通のことです。特別なことは何もありません。
リーダーの中には強烈な個性で引っ張っていくタイプもいますが、宗茂はそのようなタイプではなかったようです。性格も温厚でおだやか。普通で自然体のリーダーです。それだけに、リーダーとして普通であることの強さを感じさせてくれる武将です。それは取りも直さず、リーダーとして普通であること、普通に振る舞うことの難しさをも示しているのかもしれません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント