
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
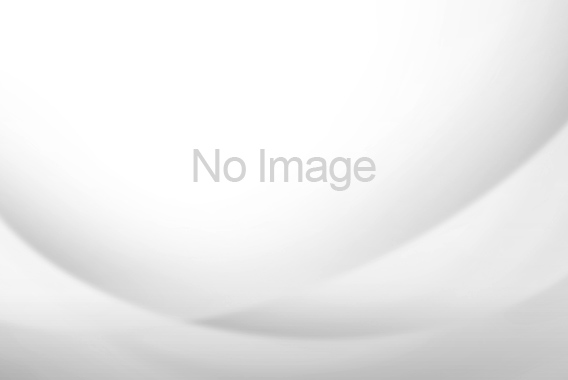
徳川家康の生涯を追うNHK大河ドラマ「どうする家康」。10月8日に放送された第38回と、10月15日の第39回では、秀吉の朝鮮出兵が取り上げられました。この朝鮮出兵に関する家康の動向を見ると、家康独自の大局観が浮かび上がってきます。
1587年、秀吉は九州に出兵し、島津義久ら九州諸将を服属させました。そして1590年に小田原の後北条氏を滅ぼし、全国統一を成し遂げます。全国を手中に収めた秀吉が次にもくろんだのが、明国の征服でした。
秀吉が明に狙いを定めた理由としては、国内安定のため諸大名の資源を浪費させようとした、あるいは諸将に与える知行地が足りなくなったため大陸にその地を求めたなど、諸説あります。また、この頃は南蛮諸国が東アジアに進出し、明の地位が相対的に低下していました。そこで秀吉は明に代わってアジアの覇権を握るという野望を持っていたと考えられます。
明に入るには九州から船で朝鮮へ渡る必要があります。そこで秀吉は経由地となる朝鮮に服属を命じ、軍を通行させるよう求めますが、朝鮮はこれを拒否。秀吉は、明への侵攻を目標とし、朝鮮出兵に踏み切ります。
1591年9月、秀吉は軍事動員の指令を出し、全国から兵が肥前(現・佐賀県、壱岐・対馬を除く長崎県)に集結。1592年3月に16万の兵が朝鮮に渡り、文禄(ぶんろく)の役と呼ばれる戦いが始まりました。
秀吉軍は当初、快進撃を見せ首都の漢城を陥落させますが、明からの援軍や朝鮮の義兵が決起すると物資の補給路が断たれ、苦戦を強いられるようになります。秀吉は明との和平交渉に入りますが、これは決裂。1597年、再び朝鮮半島に派兵し、慶長の役が始まりました。しかし翌年の1598年に秀吉が死去。家康を始めとする大老は諸大名に撤退を指示し、朝鮮での戦いは終わりを迎えました。
家康は五大老の1人に数えられる秀吉の側近でしたが、朝鮮での戦いに加わることはありませんでした。朝鮮に渡ったのは小西行長、加藤清正、鍋島直茂などの西国の武将で、家康や前田利家といった東国の武将は予備軍として肥前の名護屋に控えていました。そうした状況を別にしても、家康は朝鮮での戦いに積極的ではなかった様子がうかがえます。
秀吉が朝鮮に出兵するという話を伝えられたとき、家康は沈黙を貫き、家臣からこの戦いに参加するのかと3度問われてようやく「箱根は誰が守るのか」と答えたといいます。朝鮮への出兵を苦々しく受け止めたと思われるエピソードです。
文禄(ぶんろく)の役の苦戦を受け、1593年6月に肥前名護屋城で秀吉を前に会議が開かれました。議題は、秀吉が朝鮮に渡るべきかどうか、です。石田三成はすぐにでも朝鮮に渡るべきだと主張しますが、渡海によって秀吉に万一のことがあったら天下の一大事と、家康と前田利家はこれに反対。特に、家康は猛然と異を唱えたと伝えられています。
表向きは秀吉の安全を憂慮しての反対ですが、秀吉が朝鮮に渡れば、戦いが激化することは避けられません。家康が反対したのは戦禍の拡大を避けるためでもありました。
そして秀吉の死後、家康は朝鮮からの撤退を指示します。その後、家康が着手したのは、朝鮮との国交回復でした。1600年の関ヶ原の戦いに東軍として勝利し、江戸幕府を開いた家康は、諸外国と安定した関係を築き、その関係の上に貿易を行うことが幕府の安定につながると考えました。
秀吉の出兵以降、朝鮮とは国交が途絶えていましたが、家康は回復を申し出ます。朝鮮朝廷側は家康の和平の意向を確認し、1607年に国交が回復。対馬藩と朝鮮の貿易が再開されるとともに、朝鮮から日本を訪れる朝鮮通信使も再び始まりました。
また、オランダ船リーフデ号で漂着したウィリアム・アダムス(三浦按針)を外交顧問とし、1609年にオランダが、1613年にイギリスが平戸に商館を開いて貿易を開始します。また、朱印船貿易で東南アジアとの貿易を活発化し、「家康は戦争を行って占領しようとすることなく、諸国との貿易を希望するのみである」と評されるほど、平和に貿易を推進しました。
秀吉は明を制圧することで利益を得ようとしましたが抵抗に遭い、最後には自らの死でその道は永遠に閉ざされました。一方、家康は諸外国と融和的な関係を結び、貿易を活性化することで利益を得ようとしました。かつての戦いの相手であった朝鮮との国交を回復させ、明との関係修復にも努めました。
ビジネスでは、相手の利益になると同時に自分の利益にもなるWin-Winの関係が重要視されます。自分だけが利益になる関係では、一時的に大きな利益が得られることはあっても、その関係性は永続的なものではなくなるでしょう。このことは、顧客やパートナー企業、そして経営者と社員との関係においても当てはまります。
朝鮮出兵を通して家康の動きを見ると、家康は双方にとって利益になる関係が重要であると理解していたと推察されます。家康は国内政策においても、武家諸法度で武力的な制限を諸大名に課しつつも自治権を広く認めており、結果的に城下町を中心に各地の経済は発展しました。相手との決定的な対立関係を生まないことが、安定した江戸幕府の基盤になっています。
融和的な関係を築くことが、自らの安定につながる。このことが、家康の哲学の核になっているように思えます。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント