
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
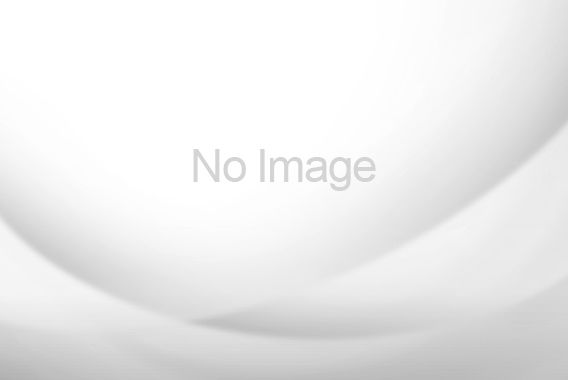
日本のチカラの源泉は中小の製造業の現場力にあるといわれる。小さな工場から生み出される精巧な部品が日本の製造業の発展を支えてきたことは間違いない。技術力において世界から高く評価される中小企業も多数存在する。これらの企業の強みを生かすために注目したいのがデジタルの活用だ。製造現場のデジタル化はどこから着手すればよいのかを考えてみたい。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目される以前から、製造業では「スマートファクトリー」というコンセプトが登場していた。ドイツ政府が提唱する「インダストリー4.0」を具現化した先進的な工場で、設計から製造、保守まで製造業の全ての業務をデジタル化して変革を推進するというものだ。
しかし、日本の製造業が一気にスマートファクトリーにシフトするとは見られていない。欧米的な発想が日本の製造業のやり方に合わないという側面も指摘されるが、何より日本の製造業の現場ではデジタル化自体が進んでいないのが現実だからだ。
多くの日本の製造現場にあるのは、モノを作り出す生産ライン、紙の製造指示書、原材料や部品だ。紙に書かれた情報を作業員が読み取り、原材料や部品を必要な分だけ生産ラインに投入し、求める部品や製品を生産していく。デジタルが活用されているのは、製造指示書を作成するためのエクセルシートくらいという状況も珍しくない。
こうした生産管理のやり方は多品種少量生産が求められる最近の製造業には不向きであり、変化への柔軟な対応も難しい。ニーズの変化に対応し製造指示書を作成する生産管理者に大きな負担がかかり、その結果、工場全体の作業に遅れが発生し、過度な残業に結びつくケースも多い。
この状況を打破するにはデジタルで製造業の現場力を強化するのが良いだろう。第一歩として、生産管理を含む周辺業務のペーパーレス化が着手しやすく、効果も得やすい。本格的な生産管理システムを導入しなくても、グループウエアなどのクラウドサービスを活用した進捗管理のペーパーレス化などから始められる。
そのためにはデジタル基盤の整備が必要になる。工場には安定して通信ができるビジネスWi-Fiを導入し、現場にはデジタル端末を配備するなどネットワークを介して情報を共有できる仕組みの構築だ。デジタル端末はタブレットやスマートフォンなど手軽な機器が豊富にある。中でも工場でも利用できる防じん・防水対策が施されたものを選べば安心だ。
現場の作業員がデジタル端末を使って進捗を逐次報告するようにすれば、状況に応じて変更指示を出しやすくなる。進捗状況と指示をリアルタイムに共有すれば、生産管理者の負担が軽減されるだけでなく、現場の作業員の確認ミスも削減できる。効果を実感しながら、デジタル化に取り組めるだろう。
生産管理業務のペーパーレス化の次に取り組みたいのが、IoTの活用だ。モノのインターネットといわれるIoTはセンサーから生産ラインの稼働データを自動的に取得し、ネットワークを介してそのデータを収集して分析する。これにより必要な人に必要なデータを提供し、工場全体の最適化を図っていくことができる。
しかし、既存の工場の設備には古いものも多く、データを収集できるセンサーを備えているケースは少ない。日本の製造業の現状を考えると、一斉に全てを新しい設備に入れ替えるのは現実的ではないだろう。
ただ、中小の製造業の中には、自社でデータを収集する仕組みを構築しているケースもある。例えば光センサーや磁気センサーを購入し、生産ラインに取り付けてモニタリングの仕組みを用意、このモニタリングデータをスマートフォンなどで共有し、生産性向上を実現している企業もある。
こうしたケースでもビジネスWi-Fi環境とクラウドサービスが活躍する。Wi-Fiを通してセンサーのデータを収集し、クラウドサービスで可視化すれば、人手を介さずリアルタイムな生産ラインの状況や工場の稼働状況を把握できる。人手不足に悩む製造現場にとっては大きなメリットだろう。
実際にデジタルを活用して大きな成果を挙げている事例にはいくつかの共通点がある。1つが、デジタルを活用できる環境が整備されており、取りあえずやってみようと決断できる経営者がいること、そして、若い人を中心にそれに応える活発なアイデアが出されていることだ。
生産現場の変革に終わりはないが、回り出せば自然に動き始めるものでもある。こうした機運が生まれる環境をつくり出すのが経営者の役割だろう。そのための一歩をぜひ踏み出してほしい。
執筆=高橋 秀典
【TP】
ビジネスWi-Fiで会社改造