
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
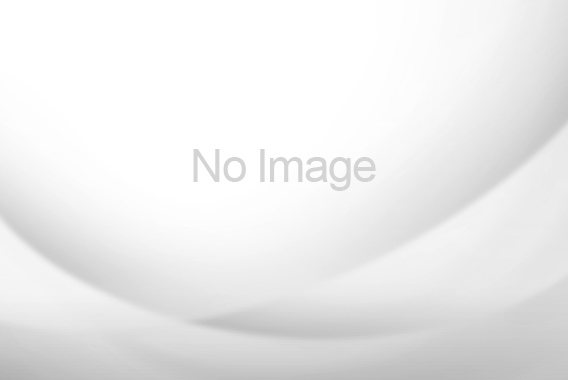
新型コロナウイルス感染症拡大防止策としてテレワークが推奨されたため、ビジネスWi-Fiを導入した企業も多いのではないだろうか。その後ウィズコロナへと移行し、最近ではオフィスに通勤する働き方にかなり戻りつつある。
そもそも新型コロナウイルス感染症拡大前の時点で、テレワークは働き方改革を進めるツールとして普及促進が図られてきた。ビジネスWi-Fiとテレワーク環境があれば働き方改革を大きく進められる。ここではウィズコロナ時代の新しい働き方である“ハイブリッドワーク”について考えてみたい。
3月13日にマスク着用の考え方が見直され、着用は個々の判断に委ねられるようになった。ウィズコロナの日々が本格的に始まり、通勤電車も以前のようにオフィスに通う人たちで混雑するようになった。新型コロナウイルス感染症拡大防止として多くの企業が導入したテレワークはもう必要ないのだろうか。
前述したように、テレワークは政府が働き方改革の一環として普及促進を図っていたものだ。テレワークによって介護や子育てなどフルタイムで働きづらい人たちの就業を促進し、場所を選ばずに働ける環境を整えて、人材不足の解消と業務効率を向上させる狙いがあった。
人材不足の解消と業務効率の改善は、ウィズコロナの時代であっても企業にとって重要な課題であることは間違いない。新型コロナウイルス感染症拡大の影響ですでにテレワークを導入しているのだから、そのノウハウの蓄積を無駄にせず、場所を選ばずに働けるワークスタイルの実現にもっと力を入れていくべきだろう。
場所を選ばない働き方をオフィス内で実現するカギとなるのがビジネスWi-Fiだ。この連載を読んでいただいている読者であれば理解しているものと思う。ビジネスWi-Fiを導入すれば有線ケーブルが不要になり、フリーアドレスが実現できるなど、メリットは多い。
このビジネスWi-Fiのメリットをさらに引き出すには、従業員に提供するPC環境についても工夫が必要だろう。これまで同様にデスクトップPCだけを提供しているのであれば、場所を選ばない働き方は実現できない。
デザインワーク、図面設計あるいは動画処理など、大画面のディスプレーに対する高速処理が可能なPCを求められる業務の場合、デスクトップタイプが必要かもしれない。そうではなく、文書やプレゼン資料の作成、表計算程度の業務であればノートPCでも対応できるはずだ。予算的に一度に入れ替えるのは難しい場合でも、リプレースのタイミングでデスクトップPCを順次ノートPCに変えていけば、結果的に大きな成果をもたらすことにつながる。
従業員の業務端末をデスクトップPCからノートPCに移行すれば、オフィス内で場所を選ばない効率的な働き方を促進できる。個室で集中して作業したり、会議室にノートPCを持ち込んで必要な資料にアクセスしたりしながら議論ができるようにもなる。特定の机に座る必要もないので資料を机にため込まなくなり、ペーパーレス化が進むというメリットもある。
さらに大きなメリットは、社内外での働き方がシームレスになる点だ。社外から社内のネットワークに安全にアクセスできるようなセキュリティ対策は必要だが、持ち運び可能なデバイスを使い、無線でネットワークに接続して仕事をするという作業自体は、オフィスにいても、社外にいても全く変わらなくなる。
こうした“ハイブリッドワーク”ができる環境を提供すれば、場所を選ばない働き方の実現につながる。在宅勤務もできるし、直行直帰もしやすくなる。従業員は通勤のストレスから解放され、最も効率的に働ける場所を選べるようになる。
従業員の働きやすさの促進も、企業としては重要なポイントになる。自社でサテライトオフィスを用意して働く場所の選択肢を増やしたり、街中や駅などにあるシェアオフィスやコワーキングスペースと契約したりして、より利便性の高い場所で時間を無駄にせず業務ができる環境を提供すれば、生産性向上にもつながる。
場所を選ばない働き方はモチベーションの維持や人事評価など、これまでとは違った経営課題をもたらす。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大対策としてテレワークを導入した多くの企業は、すでに対応を始めているはずだ。この経験を生かしつつ、さらに真剣に取り組みを進める姿勢が求められる。
ウィズコロナが本格化した今からが働き方改革の正念場といえるが、改革をどう実現するのか。改革の本質は労働時間の削減ではなく、労働生産性の向上にある。ビジネスWi-FiとノートPCの活用による場所を選ばない働き方への移行は、その実現に大きな意味を持つだろう。
執筆=高橋 秀典
【TP】
ビジネスWi-Fiで会社改造