
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
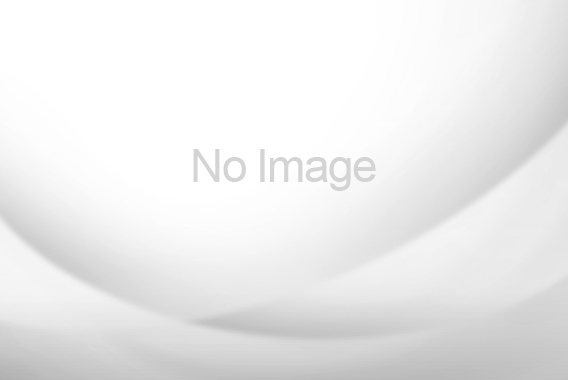
本連載ではビジネスWi-Fiの導入方法からビジネスへの活用までを1年間にわたってお伝えしてきた。初回は「主流はWi-Fi6に-新時代の到来」というテーマでWi-Fi6までのWi-Fiの変遷を取り上げた。Wi-Fi6対応機器が普及しつつある今、どんなメリットがあるのかを改めて考えてみたい。
既にビジネスWi-Fiを導入しているケースで、不満として挙げられる項目で多いのが、通信速度が遅い、通信状況が安定しないなどだ。通信が切断されてしまうと、業務やサービスにも支障をきたしてしまう。こうしたトラブルの原因の一つが電波干渉だ。実際に電波を調査してみると、周囲に複数のネットワークが混在しているために、速度低下やネットワークの遮断に結び付いている場合が多いという。
Wi-Fiに使われる通信規格は、5GHz帯と2.4GHz帯の2つの周波数の帯域がある。そのうち2.4GHz帯の電波は壁や障害物に強く、遠くまで届くというメリットがある一方で、電子レンジやIHクッキングヒーターといった家電やワイヤレスイヤホンなどのBluetoothにも使われており、電波干渉を受けやすいというデメリットもある。一方、5GHz帯の電波は壁などの障害物には弱いものの、電波干渉は受けにくいという性質を持つ。
Wi-Fi5が対応しているのは5GHz帯のみなのに対して、Wi-Fi6は5GHz帯と2.4GHz帯の両方の周波数帯に対応しているのが強みだ。両方の周波数帯を利用できるので、普段は使い勝手の良い2.4GHz帯を利用し、電波干渉が起きた際にはWi-Fi専用で電波干渉が発生しづらい5GHz帯に切り替えられる。しかも5GHz帯であれば、2.4GHz帯と比べてと比べて高速通信が可能になる。8Kや4Kといった高解像度の映像の配信も可能で、データ送受信にかかる時間が大幅に短縮される。
Wi-Fi6のメリットとして挙げられるのは電波干渉の回避能力や通信の速さだけではない。接続台数が多いため通信回線が混雑していても遅延が起こりにくく、接続先の消費電力を抑えられるのも大きなメリットだ。ここではそれを実現する新技術を紹介する。
混雑していても遅延を起こさないために採用されているのが「OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)」だ。日本語では「直交周波数分割多元接続」と呼ばれている。
OFDMAは同じチャネルで複数の端末を同時に通信できて、周波数を効率よく使えるようにする技術で、パソコンやプリンターなど多くのデバイスが接続されていても通信の順番待ちがなく、スムーズな接続を実現している。Wi-Fi6なら接続端末が多くてなかなかつながらないとイライラする場面も少なくなる。
接続先の消費電力、省エネを実現するのが「TWT(Target Wake Time)」だ。Wi-Fiの親機から端末にデータを通信するタイミングを調整し、パワーセーブを同期化させたり起動のタイミングをずらしたりして消費電力を抑制、スマホやノートパソコンなどデバイス側のバッテリー消費も抑えられるようにする技術だ。
セキュリティ面も強化されている。Wi-Fi6では2018年に登場したWPA3という最新の暗号化規格が採用された。最新技術によって暗号化に利用する鍵を生成し、パスワードが破られても暗号化が解除できない仕組みにより、高いセキュリティレベルを実現している。
Wi-Fiの規格は既に6世代目に入り、対応機器が増え、普及も急速に進んでいる。2022年9月2日には、総務省がWi-Fi6の拡張版である「Wi-Fi6E」の利用を可能にする電波法改正の省令を公布・施行した。Wi-Fi6EはWi-Fi6の2.4GHz帯、5GHz帯に加え、新たに6GHz帯の利用により、さらに高速通信を可能にした規格だ。
次世代の規格として「Wi-Fi7」も既に具体化している。今後も進化を続けるWI-Fiの最新技術をいち早く活用し、より安心で快適な通信環境を手に入れてビジネスを進化させていってほしい。
執筆=高橋 秀典
【TP】
ビジネスWi-Fiで会社改造