
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
2月に入ってウメの花の開花も見られるようになり、春が待ち遠しい時期となりました。執筆時点では平均気温が全国的に高いと予想されているため、もしかすると今年は春の芽吹きが早まるかもしれません。例年なら、まだまだ多くの植物は休眠状態。でも、実はこの時期にしか見られない植物たちの面白い表情があります。今回は身近に見られる植物を観察しながら歩いてみましょう。
厳しい冬が来る前に葉を落とす落葉樹。冬は枝だけのシンプルな姿になります。「冬枯れ」とはいっても、もちろん枯れているわけではなく、春に葉や花になる芽を枝先に付けて準備をしています。芽の形や大きさは種類によってさまざま。この時期に葉が落ちた跡の葉痕(ようこん)や冬芽(ふゆめ・とうが)をじっくり見てみると、動物の顔に見えるものもあり、とっても面白いんです。
その代表格がオニグルミです。九州から北海道まで広く自生するクルミ科の植物で、実は食用にもなります。そのツンツンと伸びた枝先にある葉痕を見てみると……まるでヒツジの顔のよう。頭の上には王冠のような形をした冬芽が乗っています。葉痕は平べったい顔だったり、瓜実顔だったりと、1つひとつ表情が違うのもポイントです。
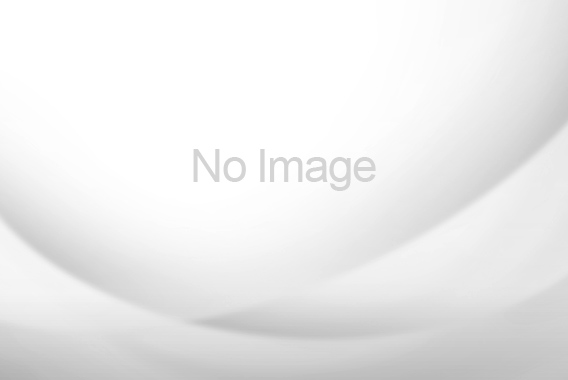
オニグルミの葉痕と冬芽(左)。枝先だけでなく、その下にもヒツジの顔のような葉痕が並んでいる。オニグルミの落ち葉の付け根(右)。乾燥していて分かりづらいが、凹凸が葉痕と一致する
ところで、どうして葉痕が顔のように見えるのか考えてみましょう。目や口や鼻のように見える部分は、春から秋の初めにかけて葉に栄養や水分を送っていた維管束(いかんそく)という管の跡なのです。秋になると、葉と枝の境目にコルク質ができて維管束を閉じ、葉を落とす準備が始まります。そして、準備が整うと、葉がポトリと離れるのです。あらかじめ傷口を塞ぐことで乾燥や病気から木を守っているのですね。
ほかにもツヤツヤのあめがかかったような赤い冬芽にハートや三角形の葉痕を持つトチノキ、丸い帽子のような冬芽とにっこり笑顔の葉痕がかわいいセンダン、ガクアジサイ(葉痕が遠くを見つめる顔のよう)、サンショウ(サルに似ている)、つる植物のクズ(パンダのよう)など、身の回りで見られる植物にも面白い表情の葉痕・冬芽があるので、ぜひ、見つけてみてください。そして、お気に入りの葉痕・冬芽が見つかったら、それがどのように芽吹き、葉を広げて落葉するのか、一年を通して観察するのも楽しそうです。
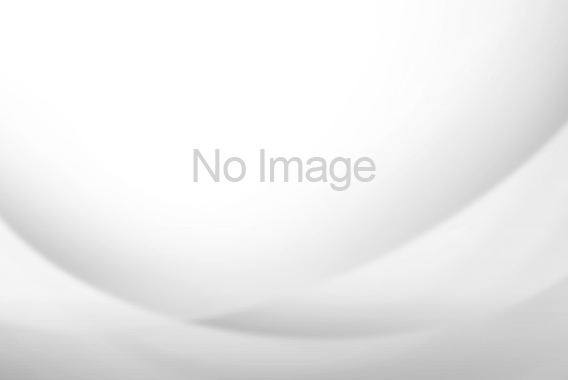
赤くて大きなとんがり帽子の冬芽はトチノキ(左)。細かい毛が密集したセンダン(右)
さて、真冬に咲く花は少ないですが、温暖な地方ではツバキやサザンカが有名です。赤くて大きな花が目を引きますね。それに対して、ほとんど人の目に触れることなくひっそりと咲く花もあります。カンアオイ(ウマノスズクサ科)です。
千葉や静岡など、比較的温暖な山地の林床で見られる多年草で、下草が枯れている中、カンアオイの葉は冬でも濃い緑を保っているので見つけやすいでしょう。葉がアオイ(葵)に似ているのが名前の由来ですが、その白い斑文が美しい葉をそっとかき分けて根元を見ると、3片に分かれた地味な花を見ることができます。正確に言うと、花びらのように見えるのは萼(がく)が筒型になったもので、その奥に雄しべや雌しべが入っています。

カンアオイの葉(左)と土に埋もれるようにして咲く花(萼片・右)。筒状の部分に雄しべと雌しべが入っている
それにしても落ち葉や地面に埋もれるように咲いていて、色も地味では、受粉を助ける虫も来てくれないように思います。でも、カンアオイの仲間であるタマノカンアオイは、萼をキノコに擬態させ、独特な匂いでハエの仲間を誘い、受粉に利用しているのだとか。これも生き残る作戦なのですね。
地域にもよりますが、カンアオイの花期は秋から春にかけてと比較的長いです。林床でカンアオイの葉を見つけたら、そっと根元をのぞいてみましょう。風変わりな花を見られるかもしれません。
面白い植物をもう1つ。雪山を歩いているとよく目にするのが、寒さに耐えているシャクナゲ(ツツジ科)です。ツツジ科の植物のような常緑広葉樹は、落葉広葉樹や針葉樹に比べると寒さに弱い種が多いのですが、日本の山岳地帯に生育するハクサンシャクナゲは雪が深く積もり、寒いときにはマイナス20℃を下回るような、とても厳しい環境で越冬をします。
その秘密はまず、気温が下がってくると葉を下向きにし、ストローのように細く丸めること。これによって雪が積もりづらく、枝を守ります。そして、小さく丸めることで葉の露出面積を少なくして風や乾燥、温度変化による影響を抑えているのです。さらに葉の水分を減らすことで細胞内の濃度を高め、容易に細胞が凍らないようにしています。寒さが厳しい所に生えるシャクナゲほど、葉を小さく丸めるんですよ。
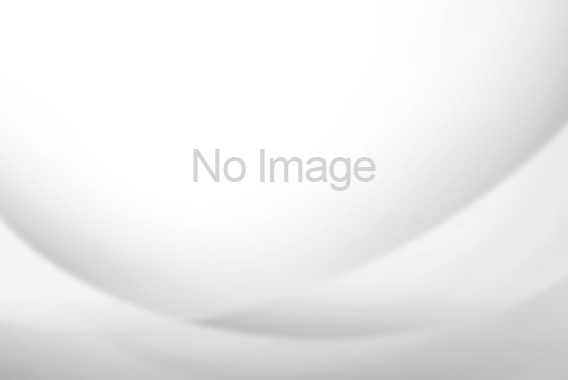
越冬するハクサンシャクナゲ(左)。しおれているように見えるが、春になるとちゃんと復活する。寒さが緩むと葉を広げ、夏の初めに花を咲かせるハクサンシャクナゲ(右)
また、葉の上に付いている芽には、葉や花となる組織が入っていますが、それが凍り付かないよう、芽の中に氷をためるスペースを持っているのだとか。寒いときには葉や花となる細胞の水分を、成長に関わらない部分に追いやり、そこに氷ができることで大切な細胞が凍り付かないように工夫されているのです。
日本の亜高山帯に生えるハクサンシャクナゲは、世界に多くの種類があるシャクナゲの中でも、特に耐寒性が強いといわれています。元々は中国雲南省やチベット南部など常春気候で湿度も高い地域で暮らしていたシャクナゲですが、長い をかけて次第に厳しい環境にも適応したことで、日本の山でも生きられるようになったそうです。
今回紹介した植物は、近所の自然公園や植物園でも観察ができます(温暖な地域ではシャクナゲの葉は丸まらないことも)。また、観察会やガイドツアーを開催している植物園やビジターセンターもあるので、専門家から教えてもらうのもいいですね。雪があったり、寒かったりすることから冬は山へあまり行かないという人も、身近な場所で、冬を過ごす植物たちに目を向ければ、きっと新しい発見がありますよ。
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ