
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
山についてのさまざまな話題を紹介する「人生を輝かせる山登りのススメ」、第17回は、山に関連した面白い言葉をいくつか紹介しましょう。
紅葉が進み、すっかり市街地まで下りてきました。この秋は美しい紅葉を楽しみに、物見遊山へ出掛けた方も多いのではないでしょうか?野山へ気分転換で遊びに出掛けることを「物見遊山」といいますが、もともとは仏教用語です。修行を終えた僧がさらなる修行のために、他の山(寺)へ行くことを意味します。
例えば「比叡山延暦寺」、「高野山金剛峯寺」のように、寺院には○○寺という名称のほかに、山号という称号を持っています。どうして寺院に山号があるのでしょうか。仏教は大陸から渡ってきた信仰ですが、それ以前にあった土着の信仰とも結び付いたと考えられています。その1つとして、日本古来の山岳信仰も大きく影響したとも。
寺院は修行の場所としてふさわしい山の上に建てることが多く、寺名と山名(山号)の両方で呼ばれるようになったのですね。ちなみに山号は、実際にある山の名前とは関連性がないこともあります。
さて、そんなお寺のお坊さんも走るといわれる師走が間近となり、これから何かと忙しい時期となります。担当している仕事が納期を迎え、「胸突き八丁」に差し掛かる人もいるかもしれません。物事の正念場、がんばりどころの意味を持つ「胸突き八丁」という言葉は、富士登山が由来だということをご存じですか。
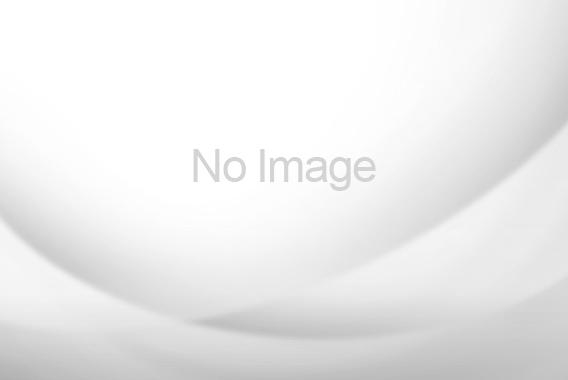 登ったことのある人は、よく分かると思いますが、富士山は山頂に近づくほど傾斜が強まり、空気も薄くなって、登るのがキツくなります。特に八合目からが難所で、次の一歩を踏み出すのもつらいほど。山頂を目前にリタイアする人が多いのもこのためです。このように、山頂まであと八丁(一丁が約109mなので、八丁は約872m)の登りが胸を突くように苦しいということからきているのです。
登ったことのある人は、よく分かると思いますが、富士山は山頂に近づくほど傾斜が強まり、空気も薄くなって、登るのがキツくなります。特に八合目からが難所で、次の一歩を踏み出すのもつらいほど。山頂を目前にリタイアする人が多いのもこのためです。このように、山頂まであと八丁(一丁が約109mなので、八丁は約872m)の登りが胸を突くように苦しいということからきているのです。
そこで、山頂まで872mがどの辺りなのかを、国土地理院の電子国土WEBの地形図で計測してみたところ、八合目の上部、「本八合目 胸突江戸屋(上江戸屋)」と「御来光館」の間でした。
「胸突き八丁」は、富士山の信仰登山が大流行した江戸時代には使われていた言葉と想像しますが、今も昔も、富士登山の苦しさは変わりないのかもしれませんね。
忘年会などで飲み会が続くと、同僚に飲みに誘われたとき「うちのかみさんが最近、口うるさくて」なんて、穏便に断ったりしますね。このように夫が妻のことを「かみさん」といいますが、これも「山」と縁のある言葉です。
かみさんの「かみ」は「神」で、神様のなかでも特に「山の神」のことを指しています。ですから、年配の方は「長年連れ添った口うるさい妻」という意味で、奥さんのことをそのまま「山の神」なんて言ったりもしますね。
山の神様は女性であることが多いのですが、豊かな恵みを生む一方、噴火や土砂災害をもたらしたりと、神様を怒らせると災いも起こります。つまり、怒ると怖いものの例えとして使われるようになったのです。
奥さんのことを「山の神」というと、一見、皮肉にも聞こえますが、根底には、日本人が古くから山に対してそうであるように、恐れながらも、敬う気持ちがあるのかもしれません。
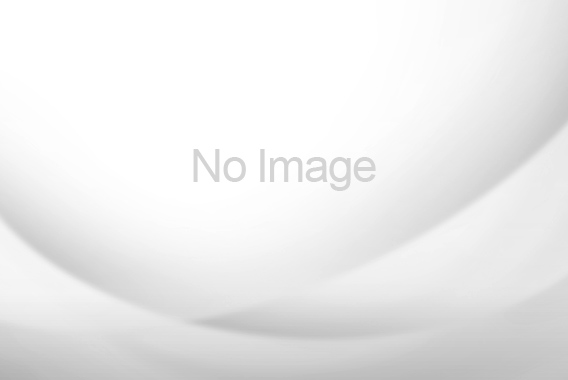 さて、Biz Clipの記事のように、話題が多岐にわたることを「四方山話」といいますが、これは日本ならではの言葉だといえると思います。日本は山国で、どの地域にも山があります。四方八方(四面八面、よもやも)からの話が、「四方にある山」と重ねられてできた言葉だからです。
さて、Biz Clipの記事のように、話題が多岐にわたることを「四方山話」といいますが、これは日本ならではの言葉だといえると思います。日本は山国で、どの地域にも山があります。四方八方(四面八面、よもやも)からの話が、「四方にある山」と重ねられてできた言葉だからです。
ちなみに、ここで1つ四方山話をしますと、宮城県角田市には四方山(しほうざん・272m)という名の山があます。展望台からの見晴らしが良く、東には牡鹿半島や金華山、西は蔵王連山を見ることができます(角田市ホームページより)。展望の良さから付けられた名前かもしれませんね。
「人生を輝かせる山登り」では、これからも山のさまざまな話題、それこそ「四方山話」をお届けしたいと思います。
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ