
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

平成から令和へ。新しい時代を迎えた5月、皆さんはいかがお過ごしでしたか?私は、4月末から5月初めにかけて、長崎県にある対馬の山に登ってきました。長崎県は「日本一島の数が多い県」で、対馬市は島の89%を山地が占める「日本一名前の付いている山の数が多い市町村」なのです。一方で、昔から「国境の島」としての重要な役割を担ってきました。今回はそんな対馬の山に登りながら、島独特の自然と国境の島としての歴史に触れてみたいと思います。
対馬は九州と韓国の間にある対馬海峡に浮かぶ島です。「浮かぶ」とはいっても、南北約82㎞、東西約18㎞で、東京23区や琵琶湖よりも大きな面積があります。福岡県の博多港から高速船やフェリーが出ていますが、対馬までの航路は約130㎞。一方、島の北端から韓国までは直線距離50㎞ほどの国境の島です。
対馬は、かつては大陸とも日本列島とも陸続きで、後に孤島となったと考えられています。そのため、大陸系生物のツシマヤマネコ、日本本土系生物のツシマテンが同地に生息するなど、大陸と日本、両方の動植物が見られる特殊な環境にあります。
対馬の特長として、山好きの私が見逃せないのが「日本一山の数が多い」という部分。東京都23区を含む日本の市町村は1741ありますが、その中で名前の付いた山の数が最も多いのが対馬市なのです(山と溪谷社刊『日本の山を数えてみた』による)。対馬市には177もの山があり、同率第2位の栃木県日光市、新潟県阿賀町の129山を大きく上回ります。
地形が複雑でもともと小ピークが多い対馬の山々。名前の付いた山の数が多い理由は、山城や海からの目印として山が利用されてきた歴史があり、名前がないとどの山を指しているのか分からないからではないか、と推測されています。
さて、私は博多から夜行フェリーに乗り、早朝に対馬に降り立ちました。港で対馬観光物産協会の西護(にし まもる)さんと待ち合わせをし、ここからは西さんに案内していただきます。
まずは対馬のシンボル的な山、白嶽(しらたけ・518m)に登りました。白嶽は島の南部にあり、石英斑岩の巨大な岩峰が2つ突き出す、特徴的な山容です。そのため、古くから信仰の対象となってきました。
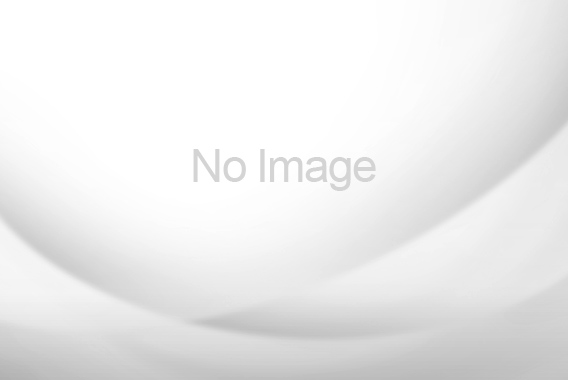
麓から見ても白い岩峰が目を引く白嶽(写真奥)。岩峰の左が雄嶽で右が雌嶽
登山口からしばらくは植林の中に続く道を登り、1時間ほど行ったところで白嶽神社の鳥居をくぐります。この先は聖域として森が保護されてきたため、シイやカシなどの原生林が残っています。道の周囲に大きな木がうっそうと茂り、霊山の雰囲気が漂っていました。西さんによると、人の手が入らなければ、福岡、長崎などの都市部を含め、九州の大部分はこのような照葉樹林の森に覆われていたのではないか、とのことでした。
鳥居からさらに1時間ほどで山頂直下まで登ってきました。2つの岩峰の間には白嶽神社が祭られています。ここから西側の岩峰、雄嶽へ向かいます。高度感のある岩場を慎重に登ると、360度の絶景が広がる雄嶽の頂に立ちました。
そこはまさに大パノラマ。もう一方の岩峰・雌嶽と、その向こうにはリアス式海岸の浅茅(あそう)湾が見渡せました。そして、よく見ると足元からスッパリと切れ落ちた岩壁にはタンナチョウセンヤマツツジがかれんな花を咲かせています。
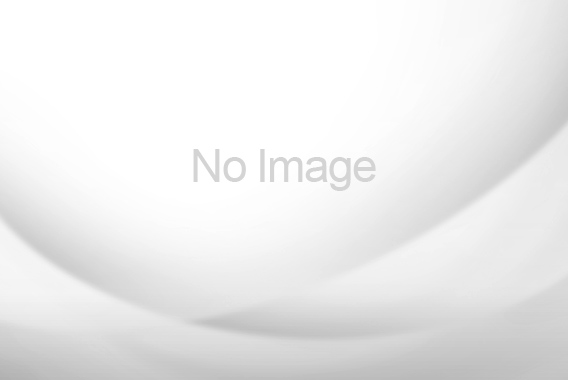
現在も神域として人の立ち入りが禁止されている雌嶽。シンボリックな形だ
タンナチョウセンヤマツツジは済州島(韓国)に分布するツツジで、日本では対馬でしか自生していません。ピンク色のかわいらしいこの花こそが、大陸とつながっていた証拠の1つです。海面の上昇により、対馬や日本列島が現在の形になるよりももっと大昔からの生き残りであると西さんからの説明を受けて、とても感慨深かったです。
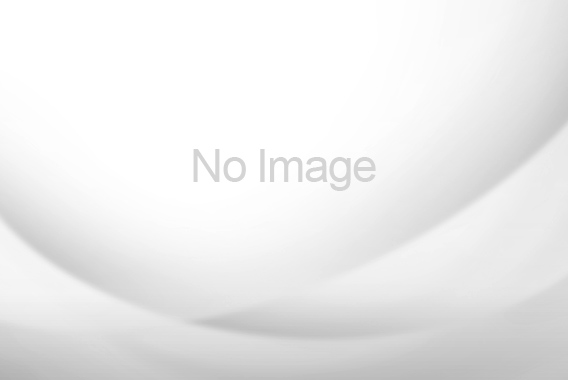
雄嶽山頂に咲くタンナチョウセンヤマツツジ。奥には島の山とは思えないほど山並みが続く
白嶽を後にした私たちは、今度は少し北に位置する城山(276m)に登りました。ここは金田城(かなたのき)といわれ、山名からも想像がつく通り、山城があった場所です。登山口から1時間ほどで山頂に立つことができます。
遊歩道を歩くと、長大な石塁を目にしました。戦国時代の石垣かなと思ったのですが、西さんのお話では、なんと今から1350年も前に築かれたものだそうです。
時は古代、天智天皇の即位前、中大兄皇子時代に遡ります。朝鮮半島西岸にある白村江の戦(663年:はくそんこう/はくすきのえのたたかい)で、日本は唐・新羅(しらぎ)の連合軍に大敗します。その後、唐・新羅からの侵攻に備えて急きょ造られたのがこの金田城で、今も当時の石塁が残っているのです。日本の黎明(れいめい)期から対馬は防衛の最前線だったのですね。

西暦667年に築かれた金田城の石塁。大きく崩れることなく、当時の形をよく残している
さらに歩くとコンクリート製の古い建物跡がありました。今から約110年以上前、日露戦争直前に旧日本軍が築いた砲台跡です。ロシアと緊張状態にあった日本は、対馬に18カ所(昭和を含めると31カ所)もの砲台を造り、ロシアとの戦いに備えました。城山にあるものもその1つです。今、私たちが歩いてきた遊歩道も、元は軍用路だったのだとか。でも、実際にはここでは戦いにならず、砲台は一度も使われることがなかったと聞いてホッとしました。
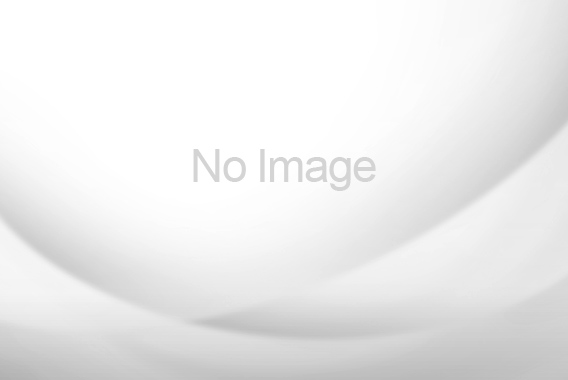
城山にある砲台の跡。日露戦争の直前、浅茅湾を囲むように砲台が造られた
対馬にはこの他にも、鎌倉時代に元寇(げんこう)の戦場となった小茂田浜、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に築いた山城跡が残る清水山(210m)があるなど、時代ごとに歴史の節目で大きな役割を果たしてきた場所があります。
今回、対馬の山を歩いて、国境の島が担う国防の歴史と宿命をひしひしと感じました。私たちが平和に暮らせるのも、それぞれの時代に命がけで国を守ってくれた人たちがいるからなのですね。新しい時代への移り変わりに、平和であることに改めて感謝の気持ちが湧いた山旅でした。
今回は島の南側の山を巡りましたが、また機会を見つけて、今度は北側の山を訪ね歩きたいと思っています。対馬の自然や歴史に興味がある方は、ぜひ対馬観光物産協会のホームページをご覧ください。

城山の山頂からは、はるか遠くに朝鮮半島を望めた。左右の岬の間にうっすら山並みが見える
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ