
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
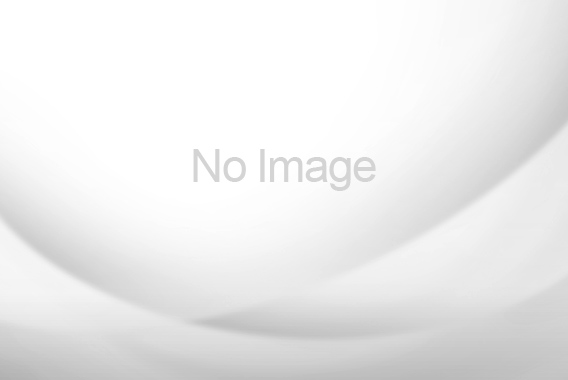 ふかふかの新雪を踏みしめて、しんと静まった針葉樹の森を歩いたり、空気が澄んでどこまでも見渡せそうな景色を楽しんだり……。神々しさがあって、特別な登山が楽しめるのが雪のシーズン。そんな冬の山を1日楽しんだあと、冷えた体をほかほかの温泉で温めるときほど、幸せを感じる瞬間はありません。
ふかふかの新雪を踏みしめて、しんと静まった針葉樹の森を歩いたり、空気が澄んでどこまでも見渡せそうな景色を楽しんだり……。神々しさがあって、特別な登山が楽しめるのが雪のシーズン。そんな冬の山を1日楽しんだあと、冷えた体をほかほかの温泉で温めるときほど、幸せを感じる瞬間はありません。
雪山で緊張していた気持ちと、ほどよく疲れた筋肉を緩め、心からリラックスできます。体を温められる上に汗も流せてスッキリ。登山と温泉はとっても相性がいいのです。下山後の温泉を楽しみに、山に登るという人もいるのではないでしょうか。
今回はそんな、登山後に寄れる山麓の温泉を、泉質と効能(適応症)とともに紹介します。環境庁自然環境局は療養泉(温泉のうちでも特に治療の目的に供しうるもの)について、掲示用泉質として11種類に分類しています。その中で主な泉質と実際の山の温泉を見てみましょう。
水1kg中に含まれる溶存物質量が1g未満、かつ泉温が25度以上の温泉をいいます。日本の温泉で最も多いのがこの単純温泉。刺激が少なく、湯あたりしづらいので、誰でも親しめるのが特徴です。
 雪山初心者でも気候の条件さえよければ登ることができる那須・茶臼岳。その山麓にあるのが、大きな天狗の面が掛けられた湯で有名な北温泉や、大丸温泉、弁天湯(栃木県)。これらは単純温泉で、長湯したくなるやさしいお湯です。このほか、妙高山山麓の妙高温泉(新潟県)、修験道の中心地である大峰の洞川温泉(奈良県)も単純温泉。由布岳の西側にある由布院温泉(大分県)は温泉成分により全国でも珍しい、美しい青色の温泉が楽しめます。
雪山初心者でも気候の条件さえよければ登ることができる那須・茶臼岳。その山麓にあるのが、大きな天狗の面が掛けられた湯で有名な北温泉や、大丸温泉、弁天湯(栃木県)。これらは単純温泉で、長湯したくなるやさしいお湯です。このほか、妙高山山麓の妙高温泉(新潟県)、修験道の中心地である大峰の洞川温泉(奈良県)も単純温泉。由布岳の西側にある由布院温泉(大分県)は温泉成分により全国でも珍しい、美しい青色の温泉が楽しめます。
木曽御岳温泉(御嶽山/長野県)、塩原温泉郷(那須岳/栃木県)などには、天然の保湿成分といわれるメタケイ酸を含む温泉があり、肌のキメがさらに細かくなりそう。美肌効果を得るならメタケイ酸を100mg/1kg以上含む温泉を選ぶといいでしょう。
単純温泉のうち、pH8.5以上のものをアルカリ性単純温泉といいます。アルカリ性の温泉に入ると肌がぬるぬるするのが特徴。皮膚の古い角質層が取り除かれて、肌がきれいになるので「美人の湯」といわれています。尾瀬檜枝岐温泉(会津駒ヶ岳/福島県)、足尾温泉(庚申山/栃木県)、七沢温泉(丹沢/神奈川県)、箱根湯本温泉(箱根/神奈川県)などがあります。
「温泉」というと多くの人がイメージする、卵が腐ったような独特の臭いを持つ硫化水素を含むのがこの硫黄泉。硫黄泉に含まれる硫黄は肌から吸収されやすく、皮膚の血流がよくなります。切り傷、ニキビ、慢性的な皮膚疾患のほか、糖尿病や動脈硬化症といった生活習慣病によいとされています。
八幡平に近い後生掛温泉(秋田県)には火山風呂(気泡浴風呂)、箱蒸し風呂、泥湯、蒸気サウナなどがあり、さまざまな方法で温泉を楽しめるのでお奨め。ほかに豪雪地である八甲田山の酸ヶ湯温泉(青森県)や、中房温泉(燕岳/長野県)、雲仙温泉(雲仙岳/長崎県)、霧島新湯温泉(霧島連峰/鹿児島県)などがよく知られています。
二酸化炭素も皮膚から吸収されて、毛細血管を拡張させるといわれています。炭酸飲料と同じく飲泉すると爽快感があるので食欲が増し、胃腸の調子を整える効果があるそうです。
二酸化炭素泉は国内でも珍しく、泡の湯温泉(飯豊連峰/山形県)、湯屋温泉(御嶽山/岐阜県)、長湯温泉(くじゅう連山/大分県)などが知られています。
ラジウムやラドンなどを微量に含む温泉で、痛風や動脈硬化症、高血圧症などに効果があるとされ「万病の湯」とも称されます。
瑞牆山、金峰山の登山口に近い増富温泉(山梨県)が知られ、五頭温泉郷(五頭山/新潟県)、三朝温泉(三徳山/鳥取県)などにも足を運ぶ方がおられるかもしれません。有馬温泉(六甲山/兵庫県)の銀泉は、希少な二酸化炭素泉と放射能泉を併せ持つ源泉として重宝されています。
単純温泉に次いで多いのが塩化物泉。文字通り、塩分を含んだ温泉です。塩化物泉に入ると深部体温が上昇し、湯冷めしにくいのが特徴です。
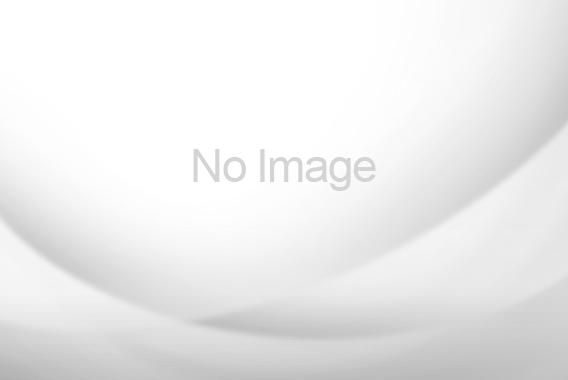 代表的な塩化物泉が、南アルプス・塩見岳の麓にある鹿塩温泉(長野県)で、15~25g/kgも成分を含む濃い温泉。温泉水を煮詰めて塩が作られているほどです。夏油温泉(焼石岳/岩手県)、奈良田温泉(農鳥岳/山梨県)、有馬温泉(金の湯、六甲山/兵庫県)などにも塩化物泉があります。体を芯から温めたい時によさそうですね。塩化物泉の適応症は切り傷、やけど、慢性婦人病、慢性便秘などです。
代表的な塩化物泉が、南アルプス・塩見岳の麓にある鹿塩温泉(長野県)で、15~25g/kgも成分を含む濃い温泉。温泉水を煮詰めて塩が作られているほどです。夏油温泉(焼石岳/岩手県)、奈良田温泉(農鳥岳/山梨県)、有馬温泉(金の湯、六甲山/兵庫県)などにも塩化物泉があります。体を芯から温めたい時によさそうですね。塩化物泉の適応症は切り傷、やけど、慢性婦人病、慢性便秘などです。
塩化物泉と同じく、水1kg中の溶存物質量が1g以上の温泉(塩類泉)には、硫酸塩泉と炭酸水素塩泉があります。硫酸塩泉には旭岳温泉(大雪山/北海道)、須川温泉(栗駒山/秋田県)、法師温泉(平標山/群馬県)などが、炭酸水素塩泉には峩々温泉(蔵王/宮城県)、高峰温泉(浅間山/長野県)、小谷温泉(雨飾山/長野県)、えびの高原温泉(霧島連山/宮崎県)などがあります。
ひとくちに「温泉」といっても、このようにさまざまな泉質があり、適応症も多岐にわたります。その療養法は温泉ごとに違うので、詳しくは各温泉の指示に従いましょう。ちなみに、登山後の疲労回復、登山者の悩みに多い慢性的な膝痛、腰痛や、打撲、捻挫の効能はどの温泉でも期待できるようです。
登山という非日常的な環境で思い切り体を動かし、おいしい空気を吸って、帰りに広々とした浴槽で疲れた体をゆっくり癒せば、相乗効果で気持ちのリフレッシュ度もより高まることでしょう。泉質やその適応症をちょっと意識して、登山と温泉をセットで楽しんでみてください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2015年12月)のものです
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ