
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
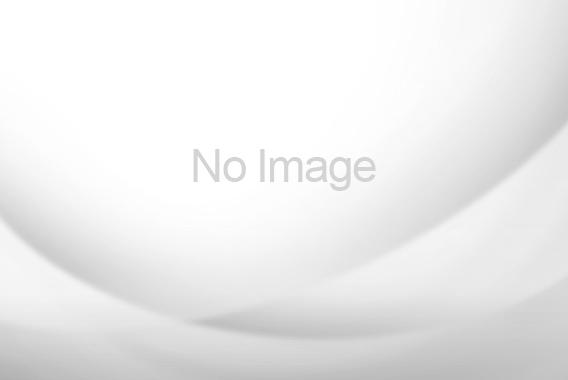 日本人にとって最も親しみのある山、富士山。環境省の調査によると、登山シーズンである7月上旬~9月中旬(ルートによって違いあり)の短い間に、毎年30万人前後もの人が登っています。本格登山ができる山で、夏にこれだけの登山者を集めるところはほかにありません。でも、それほど多くの人が訪れる山でありながら、登山を趣味とする人の中には富士山にまだ登ったことがないという人も意外にいるのです。
日本人にとって最も親しみのある山、富士山。環境省の調査によると、登山シーズンである7月上旬~9月中旬(ルートによって違いあり)の短い間に、毎年30万人前後もの人が登っています。本格登山ができる山で、夏にこれだけの登山者を集めるところはほかにありません。でも、それほど多くの人が訪れる山でありながら、登山を趣味とする人の中には富士山にまだ登ったことがないという人も意外にいるのです。
その理由を聞くと「変化が少なくて面白くなさそう」「観光登山の人が多く、雰囲気がほかの山と違う」「激混みしている」など。「富士山は眺める山で、登る山ではない」といわれることさえあります。しかし富士山は、本当に登山対象としての魅力が低い山なのでしょうか?
富士山の標高は言わずとしれた3776m。第2位の北岳(山梨県)は3193m、第3位は奥穂高岳(長野県・岐阜県)と間ノ岳(山梨県・静岡県)が同じ標高で3190m、第5位の槍ヶ岳(長野県・岐阜県)は3180mです。2位と3位の差がわずか3m、3位と5位の差が10m、2位以下はいずれも僅差。それに比べ、富士山と北岳の差は583mもあります。富士山が日本の山の中で、ダントツに高いのが分かるしょう。富士山は標高において、まさしく揺るぎない日本一の山なのです。
しかも富士山は独立峰で、近くに高い山がありません。登るごとに展望が開け、足元には登ってきた登山道と、大きく広がる裾野のはるか向こうに町や、山並みが見渡せます。その開放感にあふれた景色はほかの山では味わえないでしょう。富士は、昔は不二とも書かれていたといわれますが、現代に至ってもなお唯一無二の山なのです。
富士山の魅力といえば、誰もが思い浮かべるその美しさ。蝦夷富士(羊蹄山)、出羽富士(鳥海山)、伯耆富士(大山)、讃岐富士(飯野山)、薩摩富士(開聞岳)など日本各地に「ふるさと富士」といわれる、富士山になぞらえた山が数多くあります。郷土の山を富士山に見立てるほど、日本人に浸透した「美」の対象です。
関東、中部地方の山に登ったとき、山頂から広く見渡せる展望から真っ先に見つけたくなるのが富士山だと思います。不思議なことに自分の足で登った山は、登る前と見え方がまったく違ってきます。登る前は、漠然と山の形しか見えていなかったものが、実際に登ると細部までよく見えるようになるのです。山麓を覆う緑の色の違い、尾根や谷などの地形、稜線の細かな凹凸など、登る前に気づかなかった細部まで視線がいくようになるのは、無意識にも歩きながら植生の変化に気づいたり、地形を感じ取っていたりするから。
夏のシーズン直前なら、夕暮れ直後に浮かぶ真っ黒なシルエットの中、小さくともる山小屋の灯り。冬なら山頂部から青い空に舞い上がる雪煙......。いずれも、きっと富士山に登った経験のある人でないと、目がいかない富士山の風景です。自分の足で富士山に登れば、ほかの山から、または山麓から眺める景色としての富士山ももっと見え方が違ってくるかもしれません。
これから富士山に登ろうとしても、残念ながら5合目以上の登山道はすべて9月中旬に閉鎖されてしまいました。そこで、山頂をめざす登山は来シーズンに預けるとして、この秋はまず、富士山の魅力をもう一歩踏み込んで知る山麓のハイキングに出掛けてみませんか?
 富士山は5合目以上ばかりが注目されがちですが、吉田口の1合目から5合目までの道、富士山の中腹を歩くお中道(河口湖5合目~大沢崩れ)、宝永山と宝永火口など、山麓にもさまざまなハイキングコースがあります。これらのコースは、秋になっても積雪前なら歩くことが可能。5合目から上は森林限界のため、溶岩が露出し植生の変化に乏しいですが、山麓は豊かな自然に覆われています。樹林帯が美しくこれからは紅葉も楽しめますし、樹齢数百年と考えられるカラマツの大木に出会うこともあるでしょう。
富士山は5合目以上ばかりが注目されがちですが、吉田口の1合目から5合目までの道、富士山の中腹を歩くお中道(河口湖5合目~大沢崩れ)、宝永山と宝永火口など、山麓にもさまざまなハイキングコースがあります。これらのコースは、秋になっても積雪前なら歩くことが可能。5合目から上は森林限界のため、溶岩が露出し植生の変化に乏しいですが、山麓は豊かな自然に覆われています。樹林帯が美しくこれからは紅葉も楽しめますし、樹齢数百年と考えられるカラマツの大木に出会うこともあるでしょう。
また、石仏や社など、古くから信仰の対象とされた山の痕跡を訪ねるハイキングは、夏の富士登山とはまったく違う表情に触れることができます。第2回でも書きましたが、山頂に登るだけが登山ではありません。日本一の山、富士山に登り親しめば、登山の楽しみもさらに幅が広がるでしょう。
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ