
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
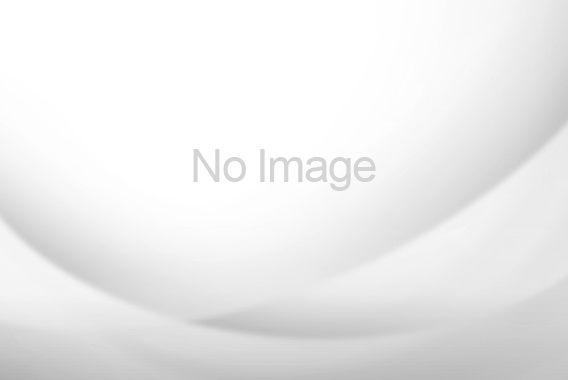 山登りの大きな魅力は、山頂に立つ満足感を得ながら、素晴らしい景色を見ることだけではありません。今回は別の魅力を紹介しましょう。舞台は、長野県のとある山の麓。山頂をめざす山登りとはちょっと違う、「夢中になれておいしい山」の楽しみ方です。5月末に行った少し変わった山行の様子をお伝えします。今年は春の山菜のベストシーズンは過ぎてしまいましたが、これからのシーズン、自分ならではのスタイルで山を楽しむヒントにしていただければと思います。
山登りの大きな魅力は、山頂に立つ満足感を得ながら、素晴らしい景色を見ることだけではありません。今回は別の魅力を紹介しましょう。舞台は、長野県のとある山の麓。山頂をめざす山登りとはちょっと違う、「夢中になれておいしい山」の楽しみ方です。5月末に行った少し変わった山行の様子をお伝えします。今年は春の山菜のベストシーズンは過ぎてしまいましたが、これからのシーズン、自分ならではのスタイルで山を楽しむヒントにしていただければと思います。
私が所属しているクライミングクラブの仲間、10人と長野県栄村へ来ています。いつもは岩壁をよじ登っているメンバーですが、今回の目的はクライミングではありません。初夏の山の幸を楽しむこと。そう、1泊2日で山菜採りをしに来たのです。とはいっても、よそ者が山に入って勝手に山菜を採るのはNG。メンバーの知人である地元の方に案内していただき、採ってもいいポイントへ連れて行っていただきました。
平地が少ないこの土地では、作物を育てるのが難しく、昔から生活の糧として山菜採りをしていたそうです。周辺では雪解け直後からフキノトウ、ユキザサ、コシアブラ、タラの芽、コゴミ、ワラビなどいろいろな種類が採れます。これらの山菜は時期によって収穫できる種類も少しずつ違うもの。案内していただいた高橋さんは、山に咲いている花を見ることで、今はどの山菜が採れるのか見当を付けているそうです。
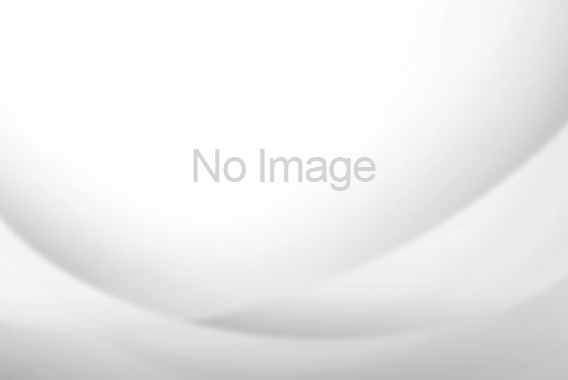 林道沿いにはピンク色の花を付けたタニウツギが咲いていました。この花が咲くころはタケノコがよく採れるとのこと。そこでタケノコにターゲットを絞って、たくさん採れそうなポイントへ向かいました。高橋さんの言うタケノコは、スーパーなどで売っているタケノコとは別もの。ネマガリダケ(チシマザサ)という、山に自生するササの一種です。
林道沿いにはピンク色の花を付けたタニウツギが咲いていました。この花が咲くころはタケノコがよく採れるとのこと。そこでタケノコにターゲットを絞って、たくさん採れそうなポイントへ向かいました。高橋さんの言うタケノコは、スーパーなどで売っているタケノコとは別もの。ネマガリダケ(チシマザサ)という、山に自生するササの一種です。
今年の冬は暖かく、積雪量が極端に少なかったことが影響して、どの山へ行っても季節の進むのが例年よりだいぶ早いなと感じます。この地方でも例外ではないようです。いつもならまだ雪が多く残る沢でも、全部消え、例年ならまだ時期を迎えないはずのウドが、早くも背丈を超える高さにまで生長していました。
でも、地元の方の読みはピッタリ。ネマガリダケの群生地へ行くと、山菜採りもベテランの山岳会の先輩がさっそくタケノコを数本見つけました。「私も!」とばかりにササのヤブをかき分けながら後に続きますが、これが、なかなか見つかりません。見つけられても50cm以上伸びていて、固くなってしまったものか、採るのもはばかられる細いものばかり。
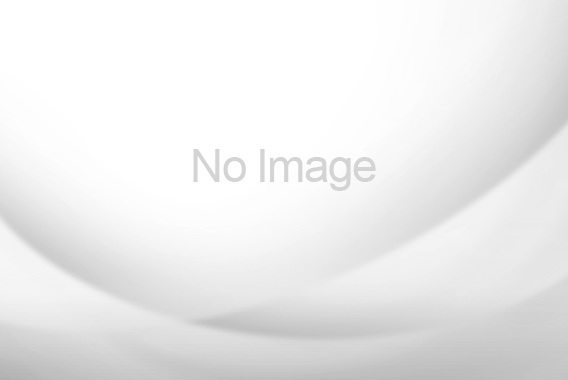 仲間の「わぁ、よく見るとここにも、あそこにもある」という歓声に焦りを感じていると「ほらほら、足元に立派なのがあるじゃない!」と言われる始末。言われて足元を見ると、靴のすぐ横に直径2センチメートルほどもある、立派なタケノコがニョキッと頭を出していました。まさに、灯台下暗し……。山菜採りって簡単なようですが、目が肥えていないと見つけることも難しいものなのですね。
仲間の「わぁ、よく見るとここにも、あそこにもある」という歓声に焦りを感じていると「ほらほら、足元に立派なのがあるじゃない!」と言われる始末。言われて足元を見ると、靴のすぐ横に直径2センチメートルほどもある、立派なタケノコがニョキッと頭を出していました。まさに、灯台下暗し……。山菜採りって簡単なようですが、目が肥えていないと見つけることも難しいものなのですね。
そんな私も20分ほどヤブをかき分けていると、徐々にコツをつかみ始めて、「タケノコの目」もでき、ちょうど食べごろのものを見つけられるようになりました。私が編み出したコツを3つ紹介しましょう。
1つ目は、姿勢をなるべく低くして地面ギリギリまで視線を落とし、斜面の下からヤブの上を見上げること。そうするとまだ伸びきっていないタケノコがよく目に入るようになります。2つ目はむやみに歩き回らないこと。ありそうな場所では動かずに目を凝らして周囲をよく見るほうが効率的です。そして3つ目は、太いネマガリダケの株を探し、その根元を中心に探すことです。
今回は、夢中になっているうちに、1時間足らずで数十本のタケノコを採ることができました。採ったタケノコは近くの山小屋へ持ち帰り、みんなでわいわいと話をしながら皮をむきました。そして衣を付けて天ぷらにしました。
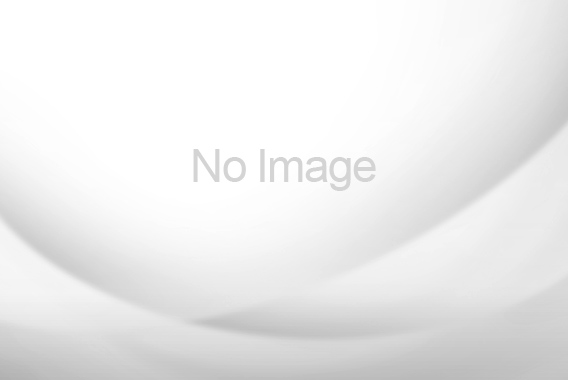
揚がった先からメンバーで順番につまみ食い。アツ、アツ、アツと言いながら口に運びました。これが最高においしいんです。根元の方はコリコリ、先はホクホクの食感。噛むと焼きとうもろこしにも似た香ばしさが広がり、やさしい甘みも感じました。
1日山を歩き、その山の水を飲んで、そこにあるものをいただく……。私にとっては、山そのものを体に取り込んでいるようで、幸せを感じました。山頂をめざさなくても、仲間とともに山に親しむ。こんな山の楽しみ方もかけがえのないものです。
さて、夜は更けましたが、山の幸を囲んだ宴会、まだまだ盛り上がっているようですので、そろそろ仲間のいる席に戻ります。また来月、お会いしましょう!
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ