
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
2018年11月山梨県南部にある七面山(しちめんざん)で修行登山をしてきました。修行とはいっても滝行などの苦行はなく、山に登り、山上の宿坊・敬慎院(けいしんいん)に一泊するという、ハードルの低いものです。山岳修行にはどんな意味があるのか、今回は七面山登山の体験を通してお伝えします。

身延山地と天子山地の奥に富士山を望む(七面山・富士山遥拝所)
今回の修行登山に選んだ七面山は、富士山と南アルプスの間にそびえる標高1989mの山です。東には日蓮宗総本山の身延山久遠寺(みのぶさん・くおんじ)があり、七面山は日蓮宗の経典・法華経の守護神である七面大菩薩を祀(まつ)る信仰の山として、身延山と共に崇められてきました。古くは、日本古来の山岳信仰と仏教が融合した修験道の行場(ぎょうば)でしたが、鎌倉時代に日蓮宗の開祖・日蓮が当地に来たことにより法華経の教えが広まり、後に一般の人々にも登拝(とうはい)されるようになったそうです。

標高約1700mにある敬慎院。車道はなく、ここへは歩いてしか行くことができない
七面山は信者でない人も登詣(とうけい)することができます。私は東山麓の登山口から表参道を登りました。信者は白装束で登拝しますが、私たちはいつもの登山ウエアでまったく問題ありません。
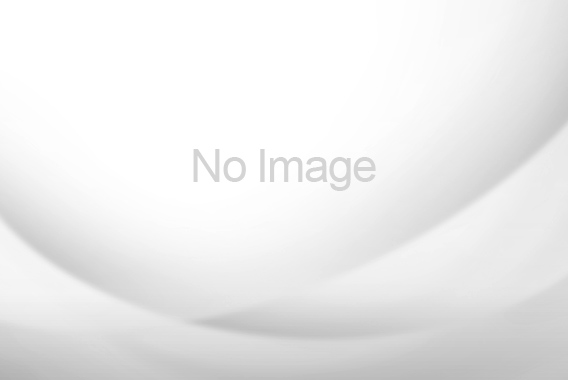
白糸の滝には女人禁制を解いたお万の方の像が立つ
ちなみに表参道の登山口近くには美しく流れる白糸の滝があり、そこにお万の方の像が立っています。お万の方は徳川家康の側室で、熱心な法華経信徒でした。当時、七面山は女人禁制で、女性の入山は許されていませんでしたが、お万の方は白糸の滝で何日も身を清めた上で登拝を成し遂げたそうです。信仰の山の多くが明治時代の廃仏毀釈まで女人禁制を貫いてきたことを思うと、かなり早くから禁制が解かれていた山だといえるでしょう。
さて、表参道登山口の標高は約500m。ここから標高約1700mにある七面山本殿の敬慎院(けいしんいん)をめざします。標高差1200m、山慣れた人にとってもなかなかハードなコースです。
参道はよく整備されていて歩きやすいのですが、一定の傾斜が延々と続きます。道のりには一丁(約109m)ごとに丁目石が置かれ、五十丁の敬慎院までそれを数えることを励みに登っていきます。丁目石の中には江戸時代中期・元文三(1739)年の日付が刻まれたものもあり、歴史の長さを感じられるでしょう。
三十丁を過ぎたあたりから私も足が重くなってきました。道中は時折、木々の間から富士山や甲府市街を望める程度で、道は変化に乏しく、まさに修行の道です。登山口を出発してから約4時間、最後は足を引きずるようにして歩き、やっと敬慎院に到着しました。敬慎院は山上にあるとは思えないほど大きく、立派な建物が並んでいます。
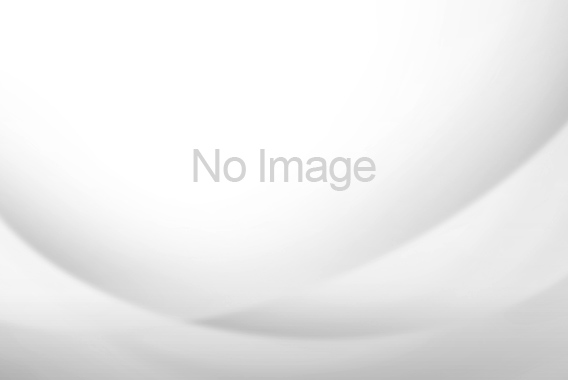
整備されて登りやすいがなかなかキツイ表参道
すぐ東側に富士山遥拝所(ようはいじょ)があり、そこへ行くと身延山地、天子山地の奥に堂々とそびえる富士山の大パノラマが広がります。ここまであまり展望に恵まれない道だっただけに、一気に爽快な気分となるでしょう。
この景色だけでも十分に見応えがあるのですが、ここからのご来光は富士山と共に拝むことができ、格別です。さらに彼岸の中日には富士山頂から日が昇る、いわゆるダイヤモンド富士が見られる特別な場所。富士山から昇った太陽の光は遥拝所のそばにある随身門を通り、本堂を真っすぐに照らすというから驚きです。この場所が聖地として大切にされてきたことに、誰もが納得するでしょう。
ご来光を拝むには宿坊も営む敬慎院に泊まるのがオススメです。朝夕の精進料理をありがたくいただき、僧侶と共に勤行(ごんぎょう)に参加してこそ、山岳修行体験も充実したものになるからです。
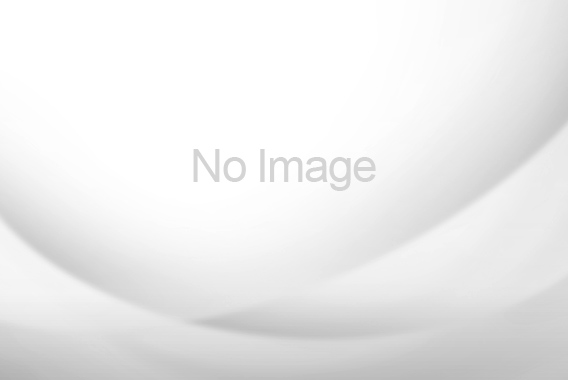
七面山・富士山遥拝所からのご来光。彼岸の中日には富士山頂から日が昇る(写真は11月17日)
また、敬慎院の奥にある一の池は龍の姿をした女神・七面大菩薩(七面天女、七面大明神とも)が棲(す)むといわれています。この池は風のない静かな日に、突如として龍を思わせる波紋が現れることがたびたびあるとか。私が行ったときは、池は静まり返り、残念ながら波紋を見ることができませんでしたが、運が良ければそのような霊的体験もできるかもしれません。
信者たちは敬慎院から来た道を戻る人がほとんどですが、登山者ならばそこから約1時間の七面山山頂まで行きたいもの。山頂は木々に囲まれて展望はありませんが、カラマツ林の雰囲気がいい道です。山頂からさらに南へ40分ほど進むと、南アルプスの山並みが見渡せる希望峰に立つことができます。
さて、以前私が参加した講演会で、身延山武井坊住職の小松祐嗣さんに山岳宗教についてのお話を伺ったことがあります。それによると、自らの足で苦労して山に登り、神仏を拝むことは、日ごろ知らず知らずのうちにためてしまったこだわり(心の垢)を落とし、身を清める意味があるのだそうです。言われてみれば、私も登山をすることで気持ちをリセットできたり、心が軽くなったりする体験を何度もしています。
ご自身の修行と趣味を兼ねて山々を走るという小松さんは、走る間は余分なことを何も考えない状態を続けるように努力していらっしゃるそうです。ただ山を走るという無心の行為に極限に集中できたとき、自分の存在が消え、山と一体になったかのような不思議な感覚になるそうです。これはマインドフルネス(瞑想(めいそう))にも通じると思うのですが、誰でも多かれ少なかれ、山に登っている間(特に苦しいとき)に無心になっていることがあると思います。それが心の解放につながり、仏教的にいうと修行になっているのかもしれませんね。
宿坊の敬慎院は通年泊まることができます。しかし、これからの季節に七面山に登る場合、登山道には雪が積もり、山慣れた人向き。軽アイゼンなどの滑り止めを用意し、防寒対策も万全にした上で出掛けてください。信仰の山は全国各地にありますし、宿坊も数多く存在します。それらを組み合わせて、みなさんもぜひ、修行体験をしてみてください。
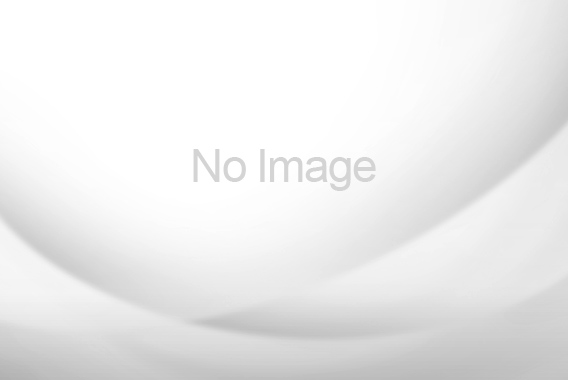
敬慎院の食事はシンプルな精進料理。煮物がとてもおいしい
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ