
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
えとの山を訪ねるのは“遊び心のある山の登り方”として、登山者に人気です。えとの山とは、山名に十二支に数えられる動物の字が使われている山のこと。その年の初登山をえとの山にしたり、各えとの山の最高峰に登ったり、年賀状の図柄にしたりと、いろいろな楽しみ方が考えられます。今回は、もうすぐやってくる来年のえと、「牛(丑)」の山に注目してみましょう。

北アルプスの中心部にある赤牛岳。牛の山の最高峰だ
来年のえとである「丑」の字を持つ山はありませんが、牛岳、牛伏山、牛首山など「牛」の山は全国各地にたくさんあります。『日本山名事典』(三省堂)によると、その数は96山。十二支の中で、午(馬・駒)の201山、辰(龍・竜)の195山に次いで3番目と選択肢も多いため、比較的訪れやすいかもしれません。
牛の字を含んだ山名が多いのは、農業が中心だった昔の生活では牛が身近な動物だったからかもしれません。それぞれの山名の由来を調べてみると、「牛が寝そべっている形に似ている」「牛の首筋のように細く切れ落ちた尾根」など、牛の姿になぞらえたものが多いようです。ちなみに午(馬・駒)や辰(龍・竜)の山名が多いのも農耕中心の日本の文化が影響しているといわれています。中でも辰に関しては、雨乞い信仰の神様とされる竜神と関連すると考えられています。
北海道には「鬼斗牛山(きとうしやま)」「於兎牛山(おそうしやま)」「背谷牛山(せたにうしやま)」など、牛の字を含んだちょっと変わった山名がたくさんあります。中には「喜登牛山(きとうしやま)」という、いかにも登ってみたくなるような名前の山も存在しています。
なぜ北海道に牛の山が多いのかというと、アイヌ語の読みに漢字を当てはめたからだそうです。動物の「牛」でははなく、アイヌ語で「〇〇な場所」「〇〇がたくさんある場所」という意味の「ウシ」が由来だといいます。前述の「キトウシ」はアイヌネギ(ギョウジャニンニク)が群生する所、「オソウシ」は滝がある所を意味しています。「ウシ」という表記のままなのが日本百名山で唯一のカタカナ表記の山、北海道の中央部に位置する大雪山系の「トムラウシ山」です。「トムラウシ」も、ミズゴケが多い所というアイヌ語由来だそうです。

トムラウシ山(2141m)は大雪山国立公園内にあり、登山難易度の高い天上の山
たくさんある牛の山の中でも最高峰は、北アルプスの「赤牛岳(あかうしだけ、2864m/長野県・富山県)」。大山脈・北アルプスの中央部に位置し、最も登りづらい山の1つです。登山ルートは長野県側の高瀬ダムから烏帽子小屋、野口五郎岳、水晶岳を経て赤牛岳に登り、読売新道から黒部ダムへ下山するコースや、富山県の折立または岐阜県の新穂高温泉から雲ノ平や高天原温泉を経由するコースなどが考えられますが、いずれも3泊4日以上が必要となる上級者コースです。
西側にある高天原から見上げる赤牛岳は、その名の通り山肌が赤っぽい巨大な山で、本場アルプスのチロル地方の山を思わせる美しさを持っています。南側の水晶岳からは、のびやかな稜線の奥に三角形のピークが見え、重厚で存在感のある山です。歩いても歩いても、なかなか黒部湖にたどり着かない読売新道の長い下りと共に、私の記憶によく残っています。
関東地方なら、群馬県高崎市の牛伏山(490.7m)は山頂付近まで車道が通っていて、本格登山をしない人も親しめる山です。山頂部は自然公園(※1)として整備され、展望台からは浅間山や赤城山、日光連山などの大パノラマが広がります。
※1:牛伏山自然公園
https://www.city.takasaki.gunma.jp/kankou/nature/ushibuse.html
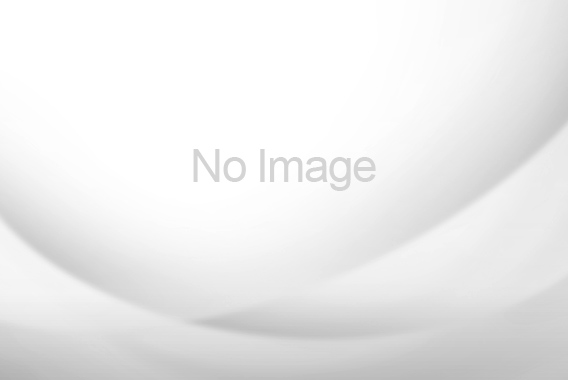
牛伏山頂上付近の爽快な風景
関西地方なら、京都府亀岡市の牛松山(636m)は、登山口から1時間半ほどと手軽に登れておすすめ。「丹波富士」の別名も持つ、形の美しい山です。近くには明智光秀が本能寺攻めの際に通ったとも、愛宕神社に参詣するために通ったともいわれる「明智越」もあり、合わせて歩くのも楽しそう(※2)です。
※2:牛松山ハイキングと明智越えハイキング
https://www.kameoka.info/course/standard/ushimatsuyama.php
https://www.kameoka.info/course/standard/akechigoe.php
みなさんの近くにはどんな牛の山がありますか? 私は来年こそ、長い山名で知られる「牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま、1990m/山梨県)」に登ろうと思っています。ここから眺める富士山は、旧500円札のデザインに使われたほどの絶景で、深緑か紅葉の時期に晴天を狙って出掛けたいです。
喜登牛山ではありませんが、新しい丑年・2021年は、山に登る喜びをたくさん感じられる年になりますように。
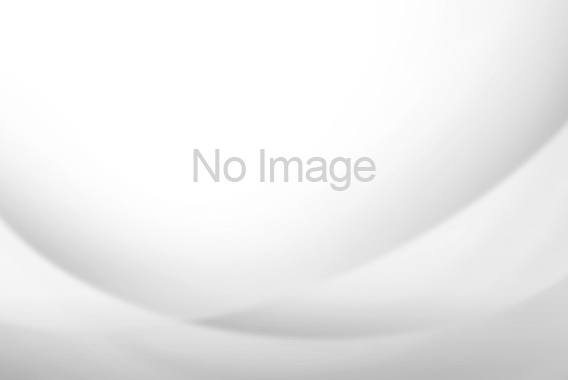
富士山の眺めが素晴らしい牛奥ノ雁ヶ腹摺山
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ