
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
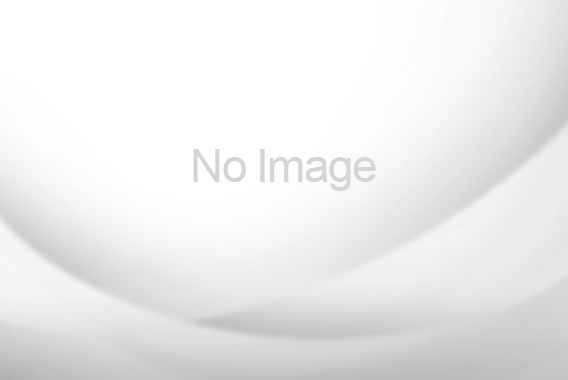 新緑が街に広がり、気温の高い日も多くなりましたが、日本アルプスなど標高の高い山ではまだ冬の装いです。春の山は、気象が変わりやすいことに加え、発達した低気圧が通過した後は一時的に冬型の気圧配置が強まり、急に天候が荒れることがあります。そんなとき、登山者の判断材料に気象データは欠かせません。今回は気象情報の利用ポイントについてお伝えします。
新緑が街に広がり、気温の高い日も多くなりましたが、日本アルプスなど標高の高い山ではまだ冬の装いです。春の山は、気象が変わりやすいことに加え、発達した低気圧が通過した後は一時的に冬型の気圧配置が強まり、急に天候が荒れることがあります。そんなとき、登山者の判断材料に気象データは欠かせません。今回は気象情報の利用ポイントについてお伝えします。
春は移動性の高気圧と低気圧が交互にやって来るのが特徴で、天候も数日ごとに晴れたり崩れたりを繰り返します。ゴールデンウイークに山へ出掛ける計画を立て、出発が迫るこの時期、まさに気象情報をチェックしている人も多いでしょう。
これまでにも、2009年4月26日に北アルプス後立山連峰の鳴沢岳付近で、3人の登山者が暴風雪の中、低体温症で死亡したり、12年5月4日には同じ山域の小蓮華岳で6人が低体温症により一度に亡くなったりなど、数年ごとに大きな気象遭難が起きています。これらの教訓もあってか、登山前の気象確認が欠かせないことは既に登山者にも広く知られていて、多くの人が気象情報に敏感になっているように思います。
登山者がよく利用しているWebサイトの1つに、日本気象が運営する気象サイト「てんきとくらす」があります。気象関連のさまざまな情報サイトがある中で、登山者に分かりやすいという点が特に人気を集めているようです。

てんきとくらす■紫外線や熱中症などの季節に応じた健康予報や洗濯情報など、生活に密着した情報を掲載。また、天気予報や防災情報(台風、地震、津波)では最新の情報がチェックできる
http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/
行楽地の天気予報をまとめたページがあり、その中の「高原・山」という所を開くと、実に細かく山名が表示されます。私が数えたところ、全国の人気の山が1700カ所近く載っていて、それぞれの山(麓の街)の気象情報を見られるようになっています。
このサイトの最大の特徴は、3段階で見られる「登山指数」です。登山をするための快適さをA(登山に適している)、B(風または雨が強く、やや登山に適さない)、C(風または雨が強く、登山に適さない)で公表しており、便利に使えます。
そもそも、山の天候は複雑で、麓と山中では天候が大きく違うことも珍しくありません。一般的な天気予報と、実際の山の天気は異なることも多く、登山前に一般的な天気予報をチェックするだけでは不十分です。かといって、天気図などから自分で山の天気を予測するのは非常に難度が高い。
結局、どのように気象情報を見ればいいかよく分からないという人にとって、この「登山指数」の表示は大変分かりやすいものだと思います。気象情報を見ることをより身近にしたという点において、画期的だったといえるかもしれません。しかし、知っておいてもらいたいのは、こうした情報はあくまで計測地点を基にしたデータを自動計算して発表されているものだということです。
近年、気象衛星の精度が上がり、予報の信頼性が高くなっています。それでも、地形や日照が複雑に影響を与える山岳地帯では、予測不能な気象変化をすることがよくあります。
遭難という最悪の事態を避けるためにも、気象判断は登山者にとって大切なもの。それを、機械的な判定に頼って「Aだから明日は安全だ」と思い込んだり、「Cなのに山へ行くなんてもってのほかだ」などと他の登山者を批判したりするのは、少々安易に過ぎるかもしれません。
精度が増した気象情報が手軽に得られるようになって、さらに登山の快適さまでも判断してくれるようになった中で、私が気になっているのは、登山者自身で考えること、判断することがおろそかになっているのではないかということです。
情報を集めることは大事です。けれども、それ以上に大事なのは、集めた情報を材料にして自分で判断するということではないでしょうか?
先に紹介したサイトの「登山指数」を利用するのにも、判定をそのまま自分の判断にすり替えるのではなく、どうして「A」になっているのか、「C」になっている原因は何だろうかといったように、自分なりに分析するヒントにしてみるといいでしょう。日ごろ、そのように気象情報を見ることで、知識が身に付き、ある程度は自分でも予測できるようになってきます。
私は登山の際に「ヤマテン」という有料(月額300円)の気象情報を利用しています。ヤマテンは山岳専門の気象予報士が、各山域の地形や気象パターンなどを考慮して発表する予報サービスです。

ヤマテン■山岳気象予報士によるオリジナル予報が見られるサイト(有料:月額300円)
https://i.yamatenki.co.jp
ヤマテンのいいところは山岳専門の予報であることに加えて、その山域ごとの天気概況が毎日見られること。天気概況のコメントと天気図を照らし合わせて見ているうちに、どうしてその予報になるのか、どのような天気図のときに注意しなければならないかなど、おおよその天気のパターンが分かってきます。
月に1度しか登山をしない人にとって、月額300円は高いと感じるかもしれませんが、毎日、山の天気解説を得られ、それを元に山の気象を勉強できると思えば、価値は高いかもしれません。自分の行動に役立てるために限りあるコストを使ってデータを得るという姿勢は、山に限らず普段の生活にも応用できると思います。ぜひ試してみてください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年3月31日)のものです。
【関連キーワード】
てんきとくらす
http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/
てんきとくらすのカテゴリ「行楽地の天気」→「高原・山」
http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/ka_type.html?type=15
ヤマテン
https://i.yamatenki.co.jp
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ