
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
初めての山へ行くと想像してみてください。みなさんは、その山の難易度をどのように確認していますか?
ガイドブックで調べる、行ったことのある人に直接聞く、インターネットで登った人の感想を読むなど、いろいろな方法がありますね。山の遭難事故の多くは力量不足から起こるので、計画段階で自分の力量に合った山選びをすることがとても重要です。でも、初心者にとっては、その山が本当に自分の体力・経験で登ることができるのか考えるのは難しいもの。そこで役立ててもらいたいのが「山のグレーディング」です。
2017年12月17日、都内で中央四県サミット「山のグレーディング活用セミナー」が行われ、私も参加してきました。この日、定員50人のプログラムが午後に2回行われたのですが、年末の多忙な時期にもかかわらず、どちらも満員となる盛況ぶり。いかに山のグレーディングが登山者の関心を集めているのかが分かります。
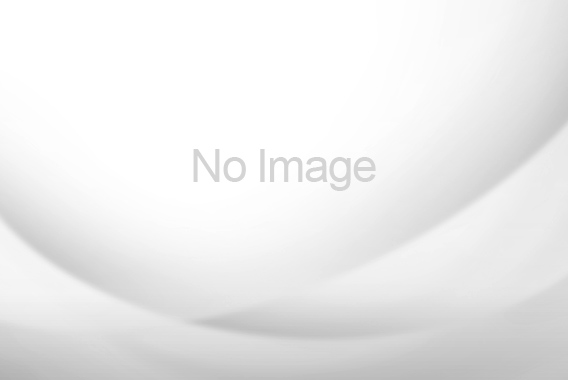
グレーディング活用セミナーの様子。見事に満席、みな講師の話に集中しています
山のグレーディングとは、登山ルート別の難易度評価のことで、有名山岳の人気ルートを体力度と技術的難易度別にまとめたものです。2014年に長野県が初めて県内の102ルートについてグレーディングを行いました。続く2015年には、新潟県、山梨県、静岡県の3県で284ルートのグレーディングが公表されました。その後、岐阜県、群馬県、栃木県の3県で242ルートも加わり、2017年12月現在、7県で合計628ルートのグレーディングが以下の行政HPで公開されています。それぞれのリンク先からグレーディング表を開けますので、ぜひ見てみてください。
・山梨県:123ルート
・長野県:102ルート
・群馬県:85ルート
・栃木県:82ルート
・静岡県:82ルート
・新潟県:79ルート
・岐阜県:75ルート
(以上、ルート数順)
グレーディング表は縦軸が「体力度」で、数字1~10の10段階(数字が大きいほど体力が必要)で評価されています。横軸は「技術的難易度」です。こちらはA~Eの5段階(Aは危険箇所が少ない山で、Eに近づくほど険しく技術的に難しい)に分けられています。

群馬県「山のグレーディング」リーフレットから引用(一部抜粋)。専用ページからダウンロード可能です
セミナーでは、主催した4県(長野・新潟・山梨・静岡)のグレーディング表が配られ、説明後に、自分が今年登ってみたいルートがどのグレードに該当するか、各自で表を見ながら確認する方法が紹介されました。
さて、実際にグレーディング表を見てみましょう。例えば、富士山のスバルライン五合目からのルート(山梨県)は夏に15万人以上の人が訪れる、富士山で最も一般的な登山道です。登山経験がまったくなく、中には日ごろ体を動かす習慣がないという人も見受けられます。しかし、山梨県のグレーディング表では体力度は5、技術度はBとなっています。これは、登山中級者向きの南アルプス北岳(広河原からのコース・山梨県)や、北アルプス常念岳、白馬岳(ともに長野県)と同じグレードで、初心者向きのコースでは決してないことが分かるでしょう。富士山は、実は登山中級者向きで、誰でも登れる山ではないのです。
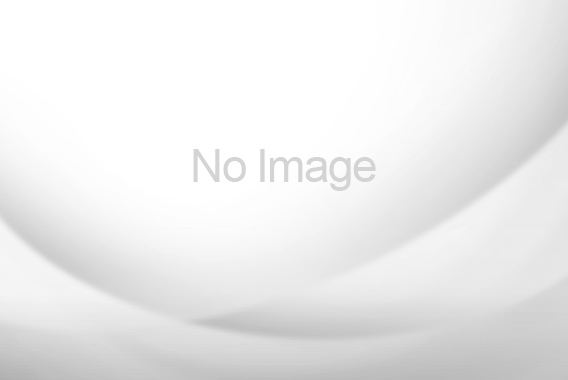
山梨県「山のグレーディング表」から引用(一部抜粋)。専用ページからダウンロード可能です
みなさんも今までに登ったことのある山をグレーディング表で確認してみてください。初心者のうちに登っていた山が意外にグレードの高い山だったということがあるのではないでしょうか?今まで登った山のグレードを改めて確認しておくことは自分の力量を知ることにもつながり、今後の登山計画のヒントになると思います。
グレーディングは計画の際に役立てるものと心得ましょう。特に近年は、中高年者の遭難事故が増えています。過去の経験はかつてのものとして、現在の体力や能力に見合った登山ルートを選択してください。高い山へ登れたからエライとか、グレードの低い山にばかり行っていて恥ずかしいということは決してありません。それぞれが自分の力量にあった山登りをすればいいのです。
山のグレーディングセミナーで講演を務めた長野県山岳総合センターアドバイザーの杉田浩康氏は、「登山は段階を踏むことが大切。自分の力量以上の山をめざすときは、体力を付けるトレーニングをしたり、グレードが低めの山で経験を積んだりなどして、登山者としての力量を高め、山とのマッチングを図ってほしい」と話していました。
登山は天候に大きく影響されます。雨の日は滑りやすく視界も悪いことが多いので、難易度は通常よりも上がりますし、まして雪が積もれば同じ山でも様相はまったく変わります。
2018年3月中には、山形県のグレーディングが公表される予定で、さらに近々、県単位ではないのですが、四国の石鎚山(高知県と愛媛県)の登山ルートがグレーディングに加わる見込みです。これからも日本全国で順次、グレーディング化が進み、さらに登山計画がしやすくなることを期待したいところです。
みなさんも今年の登山計画を立てるときに、ぜひグレーディング表を参考にし、安全登山に役立ててください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年12月30日)のものです
【関連キーワード】
長野県
信州 山のグレーディング
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/gure-dexingu.html
新潟県
新潟 山のグレーディング
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminsports/1356812341916.html
山梨県
山梨 山のグレーディング
http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/shintyaku/grading.html
静岡県
静岡 山のグレーディング
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-210/shisetu/yamagrading.html
岐阜県
岐阜 山のグレーディング
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/bosai/sangaku/11115/grading.html
群馬県
群馬 山のグレーディング
http://www.pref.gunma.jp/01/g3500213.html
栃木県
栃木 山のグレーディング
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/yama/yama.html
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ