
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
コマツ相談役 坂根正弘氏
「スマートコンストラクション」事業を推進し、オールドエコノミーとニューエコノミーの融合に挑むコマツ。IoTで「ダントツ」を極め、「コマツでないと困る」度合いを高めることで選ばれ続ける存在に。新たなビジネスモデルの“肝”であるパートナー(協力企業)との連携もさらなる深化をめざす。
──いよいよ2016年がスタートしました。坂根さんは今年をどのように展望していますか。
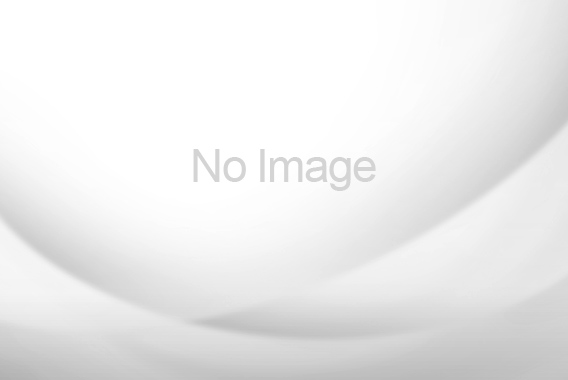 坂根:マクロな視点で言うと、今年2016年を含めて向こう3年ぐらい「日米欧時代」になると見ています。日本経済も良くなるでしょう。20年の東京五輪・パラリンピック辺りまでは良い状態が続くかもしれない。08年のリーマン・ショックの後は、日米欧の状態が悪すぎました。中国1国が良く、それに引っ張られて資源国など新興国経済も良くなりました。今はその反動が来ています。
坂根:マクロな視点で言うと、今年2016年を含めて向こう3年ぐらい「日米欧時代」になると見ています。日本経済も良くなるでしょう。20年の東京五輪・パラリンピック辺りまでは良い状態が続くかもしれない。08年のリーマン・ショックの後は、日米欧の状態が悪すぎました。中国1国が良く、それに引っ張られて資源国など新興国経済も良くなりました。今はその反動が来ています。
ただ大きなトレンドとしては「新興国時代」に進んでいます。3年前から下落傾向の中国経済もポテンシャルを考えれば再び拡大する余地があります。世界のマネーは先進国と新興国の間を行ったり来たりしますから、日米欧時代の後にはまた新興国時代がやって来るでしょう。
五輪後の日本は厳しいかもしれません。大きなイベントが終わって需要が減る上に新興国へ向かう波が来ますから。ダブルパンチです。それまでの3~4年が勝負となります。アジア戦略を強化し、かつ構造改革を推し進めて体質を強化しておかないと。
──コマツは現在、IoT(インターネット・オブ・シングズ、モノのインターネット化)を活用した「スマートコンストラクション」事業を強力に推進しています。この取り組みも次世代をにらんだ改革の一環ですか。
坂根:その通りです。コマツはブルドーザーや油圧ショベルなど建設機械を製造するオールドエコノミーの代表的企業ですが、ニューエコノミーを取り入れ、融合することで新しいビジネスモデルをつくり上げつつあります。ものづくりやメーカーが進むべき方向性を示す取り組みだと自負しています。
建設現場に関わるもの全てをICT(情報通信技術)でつなぎ安全で生産性の高い現場を創造しようというのがスマートコンストラクションのコンセプト。例えば、ドローンや建機に搭載したカメラなどを活用し、短時間で現況を測量し、現在の地形の精緻な3次元データを作成する。施工完成図面と3次元データを重ね、ある地点の土壌を何センチ削れば良いかといった情報を建機に配信する。ICTを搭載したブルドーザーや油圧ショベルを制御しながらその通りに仕上げるというものです。
建設業者は作業負担を大幅に削減できます。ICT建機の導入現場数は、既に全国1000カ所を超えています。
──坂根さんの経営スローガンの1つである「ダントツ」を極める取り組みですね。
坂根:日本の欠点は「平均点主義」と「自前主義」。ここから脱却しなくてはいけません。一番大事なのはビジネスモデルの構想力です。経営とはヒト、モノ、カネという限られた資源を有効に使って顧客価値を創造しながら最大限の収益を継続的に生み出すことです。
満遍なく取り組んでいたらグローバル競争に勝てません。自分たちの強さは何か、今の市場や顧客は何を欲しているかを見極め、市場、事業、商品・サービスを選択し集中することが出発点です。
そのビジネスモデルを実現する際に自分たちの技術が強いならそれを使えばいい。そうでないなら世の中にある技術を探してくる。まずはトップ自らビジネスモデルづくりに関与し、社内外の技術を結集することです。
──コマツは社名が表すように小松市(石川県)というローカルに根付きつつグローバルに展開し、オールド製品を扱いつつ最先端のビジネスをつくり上げています。こうしたハイブリッドな経営ができるのはなぜですか。
坂根:我々の製品に対する顧客の欲求とバリューチェーンが極めて幅広く、それに応えているうちに結果的にグローバル化もニューエコノミーとの融合も果たしたということでしょう。
例えば、チリやオーストラリアの鉱山では今、高精度GPSで位置を測定し自動走行する無人ダンプトラックが稼働しています。コマツは鉱山内の情報ネットワーク敷設やシステム運用も請け負っています。転落事故や崖崩れの危険がある鉱山で安全に作業したいというユーザーの要望に応えた結果です。
企業価値とはステークホルダーからの信頼度の総和。中でも一番大事なのは顧客で、こういうビジネスができれば「コマツでないと困る」と感じる度合いが高まり、選ばれ続けることができます。
──これまでコマツの強さは協力企業に支えられてきた面も大きいと思います。コマツだけがダントツを極めるのではなく、そうした協力企業と共にレベルを上げるために、どんなことに気を使っていますか。
坂根:コマツがめざす新しいビジネスモデルの“肝”はオールドエコノミーにもあります。1センチ、2センチ単位で施工しようと思っても、その通りに動く建設機械の確かな技術がなければ、それを実現できませんから。コマツの製品を構成する部品や部材の大半は協力企業が作っています。こうした会社が担う部分は非常に大きいのです。
そういう協力企業と連携を深めるには、とにかく信頼関係を築くことに尽きます。コマツは長年密接に取引している協力企業164社を束ねた組織「みどり会」を結成していますが、彼らに対しては「同じ船に乗る仲間」という意識を持ち、様々な対応をしています。
コマツは「下請け」という言葉は一切使いません。協力企業との取引は世間相場より良い条件を設定するよう努力しています。リーマン・ショックの時には、資金調達に苦しむ協力企業と一緒に銀行を訪問し交渉したこともあります。世代交代を念頭に協力企業の社長の息子さんがコマツで働いたり、当社内のビジネススクールで学ぶ機会も設けています。
──手厚いサポート体制ですね。
坂根:コマツの価値観や心構え、行動指針などを明文化した「コマツウェイ」も共有し、日々の仕事に落とし込もうと心がけています。結局、製品が市場に出た後の全ての責任は我々が負う訳ですから、本来セイムボート(同じ船)なのです。最近問題となっている多重構造による品質や雇用の問題でも、この価値観がベースにあるかどうかが問われているのだと思います。
──今日、経営者に求められる役割は大きくなるばかりです。どんなアドバイスがありますか。
坂根:これからの経営者は、自分で考え、決断できるタイプでなくてはやっていけません。選択と集中を進めるということは、必ず社内のどこかの利害に反します。「絶対にこの一回限りの大手術で健康体に戻れる」といった確信なしに社員を引っ張れない。ビジネスモデルづくりのオールドエコノミーとニューエコノミーの融合だってそうです。
物事には必ず本質があります。トップはその本質を見極め、データで裏付けを取り、自信を持って「これ」と思う道を突き進んでほしいですね。
日経トップリーダー 構成/小林佳代
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年1月)のものです
執筆=坂根 正弘(さかね・まさひろ)
1941年生まれ。島根県出身。63年大阪市立大学工学部卒業、コマツ入社。89年取締役、90年小松ドレッサーカンパニー(現コマツアメリカ)社長、94年常務、97年専務、99年副社長を経て2001年社長就任。就任直後、創業以来初の赤字に直面。構造改革を断行し、翌期にはV字回復を遂げる。07年会長、13年より現職。経団連副会長、産業競争力会議議員、経済産業省総合資源エネルギー調査会会長などを歴任。著書に『ダントツ経営』『ダントツの強みを磨け』(日本経済新聞社)、『「経営」が見える魔法のメガネ』(日経BP社)など
【T】
トップインタビュー