
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ウェルカム代表 横川正紀氏
食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」をはじめ、さまざまなブランドでライフスタイルを提案するウェルカム。横川正紀代表は「感性」という価値基準をブランドの基礎に置く。

(写真:丸毛 透)
――横川社長にとって、ブランドとはどういう存在でしょうか。
横川:社内的には、ブランドとは「信頼の形」だと言っています。自分たちのコミットメント(約束)を守っていること、自分たちが「こうあるべき」と考えていることに対して忠実に向かっていることへの見返りとして、周りから信頼を得る。その信頼がブランドになっていくんだと。
もう一方で、ブランドは「人格」だ、とも言っています。人間でいえば「自分らしさ」ですね。「らしさ」を1人ではなくて複数の人間や、時に複数の企業で協力してつくり上げていくわけです。そのとき、家でいうと家訓のような、ブランドとしての約束事、譲れないことを明確に持って──英語でいうと“ビジョン”なんでしょうが──その掲げたことに対して、自分で自分に嘘をつかないことが一番大事だと思いますね。
ビジネスをしていると、「時間がない」とか「お金がない」といったストレスがよくあります。そのときに「これでいい」で終わらせずに、「これがいい」という選択をどれだけ徹底できるかが大事だと、いつも社内で言っているんです。もちろん、変にこだわり過ぎて無駄なデザインやコストをかけたりしてはいけないとは思いますが……。
最後は「存在意義」だと思うんですよ。我々のような業種の企業が無くなっても、人々が生きていけないわけではない。けれど、無くなったら残念だ、と思ってもらえる存在にならないと、ビジネスをしている意義がないですよね。仮に大きな利益が出たり人気があったりしても、人々からそういう思いを持ってもらえない限り、ブランドとはいえないのではないかと思います。
――社内に対しての働きかけが重要だというお話だと思うのですが、その辺を社内で明文化したものはあるのでしょうか。
横川:我々のミッションを「感性の共鳴」という言葉で表現しています。おそらくロボットがどんなに進化しても、感じる心というものは人間にしか持てない。感性を持っていることが人間の豊かさなんです。そして、感性は人と共有できる。「共感」ですね。
ブランドごとに厳しいルールがあるわけではないんですが、ガイドラインというか、指針は持っています。例えば「DEAN & DELUCA」では「フード・イズ・ザ・ヒーロー」。食はそれ自体が美しいものだから、それ以外のデザインはシンプルであるべきだ。逆にいうと、美しい食をちゃんと選び、見極める力が必要で、その食が生まれる背景まで含めてお客さまにきちんと伝えていくことが大事だよ、と。
そこまで軸が決まると、DEAN & DELUCAに関わるあらゆる行動が、1つの方向に導かれていくんです。もちろん若干の振れ幅というか柔軟さは必要ですが。
同じように「TODAY’S SPECIAL」には「食と暮らしのDIY」という軸があって、お客さまへの手紙のようなメッセージがあるんです。「地球の一生を1年と捉えると、人間の一生は0.8秒でしかない。人生は短い。だから今日という日を大事にしよう。新しいものを追うだけじゃなくて、いいものは大事に、少し足りないものは工夫をして、時にはDIYもしてみよう」といった内容です。こう考えると、料理も一種のDIYだし、最近は手紙を書いて送るといった行為もあまりしなくなりましたが、これも考えようによってはDIYです。
こうした軸があれば、店づくりから商品選び、プロモーションから人材採用まで、進むべき方向が見えてくるんですね。そうなると、同じ考えに共感してくれるスタッフが集まってくる。ある種のコミュニティーになるんです。すると、そのコミュニティーに共感してくれるお客さまが集まってくれる。共感が結果として売り上げになってくるわけです。
――以前、「好き」という価値基準が大事だというお話をお聞きしましたが、それが感性や共感につながっているんですね。
横川:「人、モノ、コト」、我々の場合は「人、モノ、コト、場所」かもしれませんが、それくらいのエレメンツに分けて、僕らはこういうことが好きだ、嫌いだ、という基準をブランドごとにある程度言葉にしてはっきりと持っています。結局、「こうありたい」と思うのは、それが好きだからですよね。好きという感性を共有する人が次第に集まり、そこへお客さまも来てくれる。好きなことがいつもそこにあるから、信頼関係が生まれる。ファンになってくれる。結果としてブランドが生まれる。そういうことだと思うんですよね。
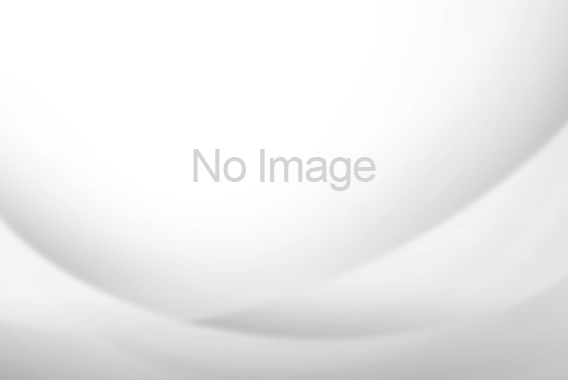
食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」(写真)のほか、インテリアショップ「GEORGE’S」やDIYをテーマにした「TODAY’S SPECIAL」などを展開する。近年はデザイン、ブランディングのコンサルティング業務も手掛ける
――共感が集まるところにブランドが生まれる、ということですね。
横川:共感を集めること、もしくは集まる仕組みをつくること、それがブランディングなんでしょうね。
デザインという言葉もそうですけど、ブランディングって外来語ですが、海外からこの言葉が入って来たから初めてそれをスタートさせたということではなく、日本でもずっと昔からやってきたことだと思うんです。たまたま、それをブランディングと呼ぶんだ、ということを知っただけで……。実際に江戸の時代から続くブランドはたくさんありますし、その人たちがやってきたことは、今でいうブランディングだと思うんですよ。
ただ、世の中でいうブランディングの方法論は、時代が変われば合わなくなることはあるはずで、そこは気を付けないといけないなと思っています。
――ブランドを育てていこうとするときに、デザイナーやクリエーターに経営者として期待することは?
横川:これはスタッフ全員にいえることなんですが、自分の価値基準で考えようということですね。「自分は本当は好きじゃないけど、会社の仕事として考えるとこうだよね」といった判断はやめよう、と。
ただし、自己満足でもいけない。プロダクトもグラフィックも店舗デザインも、お客さまと関わって初めて完成するわけじゃないですか。そこを見ずして、自己満足で終わるのが一番危険。よくあることですが、「デザインはこうあるべきだ」「デザインとしてはこれが美しい」と言っても、お客さまが「分かりにくい」と言うんなら、その仕事は不十分だということです。
お客さまの言うとおり、営業の言うとおりにつくれというわけではありませんよ。例えば営業はこういう課題を解決したいと思っているけど、それをフワッとした言葉でしか表現できない。そこをくんで、具現化したり可視化したりするのがデザイナーの仕事です。非常に高いハードルかもしれませんが、デザインってそういうものだと思います。
日経デザイン /編集長 花澤 裕二
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年7月)のものです
執筆=横川 正紀(よこかわ・まさき)
1972年東京生まれ。2000年に株式会社ジョージズファニチュア(現・株式会社ウェルカム)を設立。CIBONEやGEORGE’Sなど複数のライフスタイルブランドを展開。同時に併設するカフェをきっかけに食との関わりを深め、2003年にニューヨーク発DEAN & DELUCAの日本での展開をスタート。2007年以降は六本木の国立新美術館のミュージアムショップ「スーベニアフロムトーキョー」をはじめ、公共施設やコンセプトストアのディレクション業務、内装設計、コンサルタント業務なども積極的に行う。その後も、2012年に食とくらしをテーマにした「TODAY’S SPECIAL」をオープンするなど、衣食住の垣根を越えた新たな試みを重ねて「味わいあるくらし」を提案している。2016年に株式会社ウェルカムと株式会社ディーンアンドデルーカジャパンは「株式会社ウェルカム」として合併した。
【T】
トップインタビュー