
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
オガールプラザ社長 岡崎正信 氏
岩手県紫波町は、人口3万3000人ほどの小さな町だが、全国から視察が絶えない。地元建設会社の2代目専務が奮闘し、補助金に頼らない地域再生を成功させたからだ。けれど、実家に戻って約4年、もんもんと過ごした過去もある。その停滞を、いかに打破したか。
──岡崎さんは、岩手県紫波町のオガール地区で推進してきた開発プロジェクトの成功で今、地域再生の旗手として注目されています。それと同時に、地元の建設会社、岡崎建設で、創業者の息子として専務を務める、中小企業の2代目という顔も持っています。
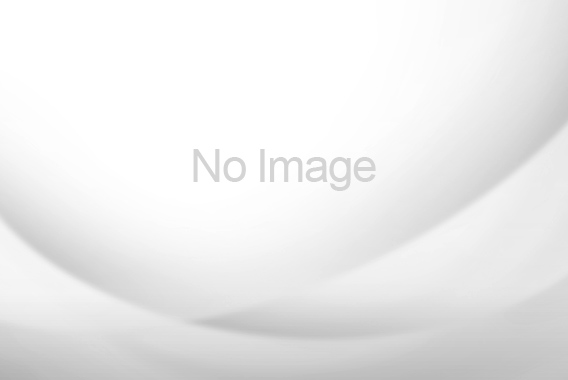 岡崎:岡崎建設は、この「オガールプロジェクト」から1円の工事も受注していません。けれど私がこの事業に、2007年から注力してきたのは、巡り巡って岡崎建設のためになると考えたからです。
岡崎:岡崎建設は、この「オガールプロジェクト」から1円の工事も受注していません。けれど私がこの事業に、2007年から注力してきたのは、巡り巡って岡崎建設のためになると考えたからです。
岡崎建設は、売上高10億円を超える程度です。このような小さな地方の建設会社が飯を食っていくにはまず、町が元気でなくてはなりません。町が元気であるとは、結局のところ、地価が上がることだと私は考えます。地価を上げれば、人口が減っても、税収を増やせます。だから自治体がインフラの整備やリニューアルにお金を使える。結果、建設会社に仕事が生まれます。
実際、紫波町の住宅地の公示地価は15年から2年連続で上昇しました。岩手県全体では15年連続ダウンなので、なかなかの健闘です。
オガール地区に12年、最初に完成させた複合施設「オガールプラザ」は、基本的に補助金を使っていません。私が社長を務めるオガールプラザ(岩手県紫波町)が、その運用や管理を担っていますが、16年5月期は営業利益900万円を出し、266万円を納税します。約400万円の地代を町に払った上でです。
──ゆくゆくは岡崎建設の後を継ぐのですか?
岡崎:いえ、弟も実家に帰ってきたので、彼に任せたいと思います。そもそも亡き父は、息子たちに後を継がせない方針でした。
1986年、私が中学1年生の時、父は建設会社を立ち上げ、土木工事を主力に急成長させました。その父が、私にはっきり言ったのです。「おまえは発注者側に行った方がいい」。要は、公務員か公営企業の職員になってほしいのだと。そこで私は大学卒業後、旧・地域振興整備公団に就職しました。
その2年後、父が急逝し、母が社長になりました。その後、地方の建設業界がどんどん弱り、岡崎建設も銀行から「いつ息子は帰ってくるのか」と言われていると、漏れ聞くようになりました。
折しも、私は公団での仕事に退屈していました。やることはおおむね横並びで、競争心をあおられない。ならば、たった一度の人生だし、リスクを取ろうと。岩手に戻り、家業の経営に携わることにしました。それが2002年です。
──いざ帰ってどうでしたか。
岡崎:まあ、ひどい状況ですよね。一番驚いたのは、同業者の会合などで「もっと陳情して仕事をつくらなくては」といった議論ばかりを聞くことでした。私は前職で、日本にはもう社会資本整備に投資するお金がほとんどない現実を、目の当たりにしていました。つまり、私たちの業界は、お金を持っていない人に「お金をくれ」とお願いしようとしているわけで、このままではダメなのは明らかです。
しかし、そこで自分が何をすべきかとなると、なかなか見えてこない。最初の4年くらいは、ただ、もやもやと悩んでいました。
──その停滞から、どうやって脱したのですか。
岡崎:もがいていたら、出会いに恵まれたのです。盛岡青年会議所の役員をしていた06年6月、以前にお付き合いがあったエコノミストの藻谷浩介さんを講演にお呼びしました。食事をしながら、今の状況などを話すと「それなら、根本さんの話を聞け」と言う。東洋大学で産業や地域の再生を専門にしている根本祐二教授のことです。
すぐに東洋大学大学院の秋入学の枠に応募し、岩手から東京に通う日々が始まりました。全部の授業を最前列で聞くと最初に決めていました。そうやって話を聞いた最初の先生が、都市再生プロデューサーの清水義次さんです。この講義がとてつもなく面白く、私の人生を変えました。
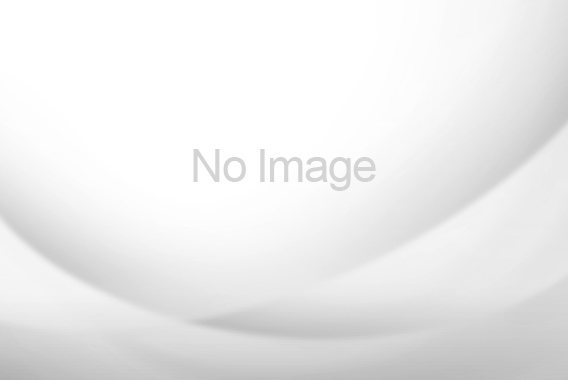 もともと紫波町には、財政難で塩漬けになった広い公有地がありました。そこに、当時の町長が「岡崎建設の息子が東京に通って、地域再生の勉強しているらしい」と聞きつけ、私に持ち掛けたのです。この土地を何とかしよう、と。
もともと紫波町には、財政難で塩漬けになった広い公有地がありました。そこに、当時の町長が「岡崎建設の息子が東京に通って、地域再生の勉強しているらしい」と聞きつけ、私に持ち掛けたのです。この土地を何とかしよう、と。
そこで清水さんと建築家の松永安光さんとタッグを組み、2泊3日の合宿で、開発のマスタープランをつくりました。これがオガールプロジェクトのスタートです。
──何が一番の成功要因だったと思いますか。
岡崎:商業を軸に据えなかったことでしょう。多くの地域再生プロジェクトでは、「まず商店街の復活だ」などと、補助金を使ってイベントをしたりなどしますが、必ずと言っていいほど失敗します。
商業では町のにぎわいは取り戻せないのです。もっと普遍的な集客装置が必要なのです。
ヨーロッパには、それがあります。どんな小さな町でも、中心には必ず教会があり、その前の広場に連なるように、商店やカフェが並びます。教会という普遍的な集客装置が商業を支えています。
では、現代の日本に、教会に代わり集客装置をつくれないか。学校や役所といった公共施設にはポテンシャルがあります。ただ、敷地がしっかり区切られ過ぎて、教会の広場のように人が外ににじみ出ない。ここを変えればいい。
「オガールプラザ」には、集客装置となる施設として図書館があります。その前に、遊歩道が走る広場があります。地域の人たちが図書館に寄った後、ぶらぶら散策すると、その先に、地元で採れた野菜などを売る「紫波マルシェ」やカフェが現れる。そんな仕掛けです。
つまり、ウオーキングで健康を維持、増進しながら、おいしくてヘルシーな食が楽しめる。これは、今の日本人が理想とするライフスタイルです。おのずと人が集まり、テナントのお店ももうかります。
──今後は、どんな活動に力を入れますか。
岡崎:オガールプロジェクトが計画する施設は、来年には、ほぼすべて完成します。その先は、まだあまり具体的には考えていません。
最近は、自治体向けのコンサルティングもしています。この仕事で私がこだわりたいのは、成果報酬型の契約です。分かりやすいのは、私が提案した開発で固定資産税の税収が増えたら、その何%かをいただくといった形でしょう。
町づくりが税収増につながらなければ再投資できず、建設業界に仕事が生まれません。私の原点は「建設会社のせがれ」です。自分を育ててくれた岡崎建設の人たちが、幸せに生きられる経営や社会の形をつくる。それが使命です。
日経トップリーダー 構成/小野田鶴
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年9月)のものです
執筆=岡崎 正信(おかざき・まさのぶ)
1972年岩手県生まれ。95年旧・地域振興整備公団に入団。2002年退団し、岡崎建設入社。04年専務就任。08年東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻で修士号取得。07年から岩手県紫波町の公有地を開発する「オガールプロジェクト」に着手。同プロジェクトで建設した施設の運用などをするオガールプラザ、オガールベース、オガールセンターを設立し、それぞれ社長に就任。内閣官房地域活性化伝道師を務め、地方自治体向けのコンサルティングも手掛ける。
【T】
トップインタビュー