
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
サラヤ 代表取締役社長 更家悠介 氏
サラヤは創業以来、時代が抱える社会問題の解決に深く関与し、社業を発展させてきた。今、注目されている「持続可能な開発目標」(SDGs)にもいち早く取り組み、実現に向けて積極的な活動を続けている。バランスを取るのが難しいとされる社会貢献とビジネスを両立させるポイントは何か。代表取締役社長・更家悠介氏に話を伺った。
――創業の経緯とこれまでの歴史について、伺わせてください。
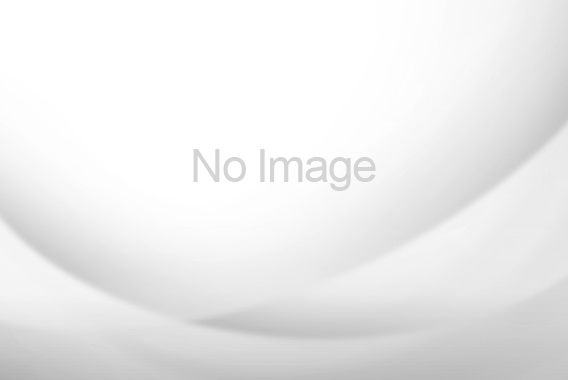
社会貢献とビジネスの両立について語る更家社長
1952年に私の実父である更家章太が創業しました。更家家は三重県熊野市で代々、林業を営んでいたのですが、父は大阪に出て、現在の会社の前身である「三恵薬糧」を立ち上げました。
当時、日本では衛生状態があまり良くないことから、伝染病である赤痢が流行し、社会問題となっていました。その予防のために手洗いが必要ということで、父はヤシ油を原料にした植物性せっけんに殺菌成分を配合した手洗いと殺菌・消毒が同時にできるディスペンサータイプの液体せっけん「シャボネット」を開発しました。これがサラヤの最初のヒット商品になります。
その後、水の冷たさから手洗いせっけんの売り上げが低迷するので、冬のシーズン対策も兼ねて、うがい薬とうがい器も手掛けるようになりました。折しも当時は、四日市市や堺市といった工業地帯などで大気汚染が社会問題となっていました。そうした公害対策として、学校や工場などで、当社の製品が次々と採用されたのです。サラヤが提唱する“夏は手洗い、冬はうがい”が定着していきました。
――創業当時から社会問題の解決とビジネスが密接につながっていたのですね。その後の、小売り分野への事業拡大を説明していただけますか?
業務用で販売していた洗剤への小売りニーズが高まり、原料のヤシ油にちなんで、家庭向けに「ヤシノミ洗剤」として1971年に発売しました。当時は、石油系洗剤による河川の汚染や富栄養化が社会問題になっていました。それを少しでも防ぐため、植物原料であるヤシ油を使った当社の洗剤が環境への負荷が少ないということで注目されたのです。
競合洗剤よりも価格は高かったのですが、少しずつロイヤルカスタマーが付いてくださるようになりました。そうした方々が常にサポーターとして買ってくださるようになったのです。こうして、病院・企業向けに加えて小売り分野でも、安定した業績を残せるようになりました。
――現在御社では、衛生・環境・健康の3つのキーワードを事業の柱とされています。それについて解説していただけますか?
最初の事業である手洗いは“衛生”、次にヤシノミ洗剤で“環境”とつながります。それに“健康”が加わったのは、1990年代、低カロリーの天然派甘味料「ラカント」を開発したことがきっかけです。これは高度成長期に増加した糖尿病の予防という点から社会的ニーズがあるのではないかと考えて研究した商品です。
衛生・環境・健康はお互いに深く関連しています。例えば、手洗いもうがいも健康であることも予防の1つ。環境を守ることも同様に健康に役立ちます。そこで3つをまとめて事業の柱と位置付けました。
――御社は「手洗い」からスタートして、非常にうまく事業の幅を広げ、売り上げを増やしておられます。成功のポイントはどこにあると考えますか?
“手洗い”というチャネルを活用しながら、世の中の変化に遅れることなくお客さまのニーズにお応えできているということになるのでしょうか。おかげさまで、売り上げは創業以来、景気の変動などがある中で、なだらかな右肩上がり傾向です。多少の無理はしても、大きな無理はせず、事業を続けてきました。
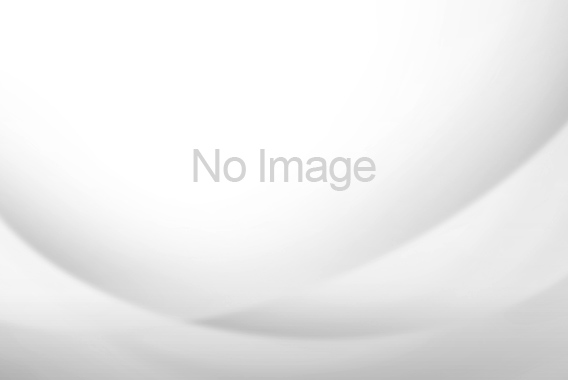
サラヤでは衛生・環境・健康を柱に、多彩な商品を開発している
――御社のビジネスの特徴は、創業以来、社会的な問題の解決に深く関与していることにあると思うのですが、ビジネスが社会貢献としてできることについてどのようにお考えでしょうか?
社会的な問題は、経済を持ち込まないと解決しないのではないでしょうか。いくら政府など公的部門が援助をしても未来永劫(えいごう)、継続するのは難しい。となると、どこかでビジネス的な手法が持ち込まれないとサステナブル(持続可能)になりません。当社はいろいろなNPO(非営利団体)とお付き合いがあります。NPOは利益を考えずに社会的課題に取り組み、企業は利益を考えて取り組みますが、共有できる目的もあるし、協力もできます。これからの企業はそういう社会性の中に、自らを置き直してみることが、自身のサステナブルにつながる可能性が非常に高いのではと思います。
――社会に必要とされることで企業自身が継続できる、逆に言えば社会に必要とされない企業は長続きしないということでしょうか?
そうですね。社会に必要なものをつくっていけば必ず売れていくと思います。もちろん、たくさん売れるかどうかは別ですし、競争もあるでしょうから、よりよく良いものをつくるように工夫していくことは必要でしょう。私は長く売れ続けていくのは社会的に必要とされる商品の方だと思います。
――社会貢献ということでは、御社はSDGsへの取り組みを強化されています。どのようなスタンスで取り組まれていらっしゃるのでしょう?
SDGsは国連がつくったグローバルな目標です。そのために新しいことをやるだけでなく、現在、行っている企業活動を、SDGsというフレームワークに当てはめ、発展させていこうと考えています。自社の活動の意味を確認しながら、SDGsそのものが正しいかどうかも含めて、持続可能な世界をめざして、社員の皆さんと共に考えていこうというのが当社のスタンスです。
SDGsを規制ではなく、ビジネスチャンスと捉えること。発想としてはSDGsの目標を達成する際には、ビジネスチャンスが出てくるので、それを早く見つけて実現化するということです。目標のシーズやニーズに合わせて自社のビジネスを変えていく、というプロセスで取り組むと展開が早くなるかもしれません。何事もポジティブシンキングで前向きに変化を考えていくことが必要です。
――御社は国内のみならず、国外にも多数の拠点をお持ちです。事業を展開される上で今後、情報化の推進が欠かせないと思いますが、どのように取り組まれているのでしょうか?
おっしゃる通り、今後の事業展開に情報化の視点は欠かせません。当社は今後、衛生・環境・健康すべてのフィールドにもっとイノベーションを起こしたいと考えています。その時のポイントの1つが情報通信です。
例えば当社では、衛生に関するイノベーションとして、スーパーマーケットなどにある冷凍食品ケースの温度を自動管理するシステムを開発・提供しています。人の手で計って記録するよりも正確で、24時間対応が可能です。コストパフォーマンスの良さが評価され、導入していただけるケースが増えています。
また、グローバルに事業を展開した上で、業務管理の情報化を進めることも大切です。すべての国の事業所に関して、すぐに業績が分かるシステムがなければ、安心してグローバル展開することはできません。今後のビジネスにおいてITの力は必須だと考えています。
当社が海外への進出を本格化したのは1995年です。阪神淡路大震災の年に北米に拠点を設けました。続いて、2003年にタイに工場を設立。その後、中国、マレーシアと徐々に広げ、現在23カ国に拠点があります。こうした展開を経て、究極的には「手洗いの世界No.1企業」をめざしています。まずは手洗いで世界を制覇しようと、社員を叱咤(しった)激励しています。
――最後に、事業展開に悩む中小企業の経営者にエールをお願いできますでしょうか?
人手不足の問題などもあり、最近元気がないといわれているようですが、改めて自らを見つめ直してみると、なんらかの気付きがあると思います。それと同時に、社会的な課題に対して、自社が何かできることがないかも探してはいかがでしょうか。社会的な課題のヒントがSDGsです。
繰り返しになりますが、SDGsをビジネスチャンスと捉え、社会に対して目を見開き、自分のところが何をしたいのか、自分たちに何ができるのかを明確にして旗を上げることができれば、協力者が出てくる、そんな気がします。ぜひ、みんなでSDGsを勉強して、ピカピカの地域、ピカピカの地球を次の世代に引き継いでいきましょう。

甘味料「ラカント」(右手)と、ヤシノミ洗剤(左手)を持つ更家社長。サラヤは、業務用からスタートして小売りに事業を拡大している
執筆=更家 悠介 (さらや・ゆうすけ)
1951年大阪府生まれ。大阪大学工学部卒業。1975年カリフォルニア大学バークレー校工学部衛生工学科修士課程修了。翌年サラヤ株式会社に入社。1998年代表取締役社長就任。NPO法人ゼリ・ジャパン理事長、認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン理事などを就任。2014年渋沢栄一賞、2016年食生活文化功労賞、2019年紺綬褒章など受賞多数。
【T】
トップインタビュー