
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ファミリア 代表取締役社長 岡崎 忠彦氏
グラフィックデザイナーから家業を継いで社長業に転身。デザインと経営の両方を知る岡崎忠彦社長にとって、デザインはコミュニケーションツールだという。
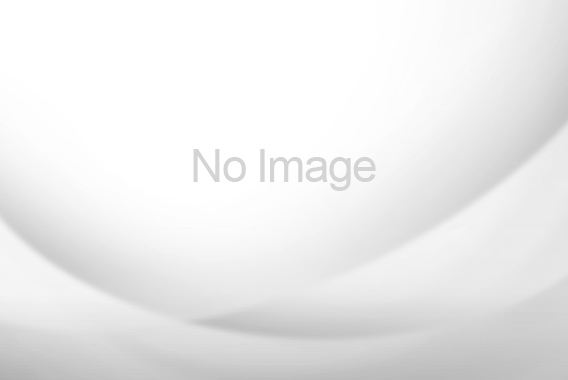 ──岡崎社長は、企業経営におけるデザインとはどういうものだと考えていますか?
──岡崎社長は、企業経営におけるデザインとはどういうものだと考えていますか?
岡崎:企業は「人」の集合体ですよね。最も大事なのは人。企業は何でできているかというと人ですし、お客さんも人、取引先も人ですから。
だから僕が企業経営で重視しているのは、経営の視覚化なんです。社員にいかに分かりやすく現状を伝えるかが大事だと考えています。ほら、野球でもサッカーでも、ルールを知っているからこそ楽しめるじゃないですか。経営も同じで、現場の社員が経営のことを分かってくると、すごく面白くなる。現場の社員が難しいと感じている経営に関することを、いかに分かりやすく伝えて、みんなを巻き込んでいくか。経営を人ごとではなく自分事にしてもらうか。つまり僕にとってデザインはそのためのコミュニケーションツールなんです。
僕はもともとアーティストになろうと思っていた人間で、会社を2011年に継いだときは経営のことはまったく分からなかった。そこで少しでも自分の得意分野を生かしたいという思いから、経営とグラフィックデザインを合体できないかと考えたんです。(アップルストア1号店をデザインした)デザイナーの八木保さんのところで教えてもらったビジュアルコミュニケーションがとても役立っています。
子ども服を中心としたアパレルメーカーであるファミリアという会社が今、置かれている状況や課題、やるべきことは何か、中期的な計画など、社員向けのプレゼンテーション資料はすべて自分で作っています。ビジュアルを使って、できるだけ分かりやすく伝えられるように。
僕は、経営者の仕事って現場からできるだけ多くのアイデアを出してもらって、さまざまな意見を聞いて、それをジャッジすることだと考えています。
僕が社長になったのは会社に一番元気がないときだったんですが、現場の社員に聞いてみると、意外にもめちゃくちゃ意見が出てくるんですよ。それを全部ビジュアライゼーションしておいたんです。2016年にオープンした代官山店は体験型ショールームであり、ネットとの親和性を重視したオムニチャネル対応店舗ですが、これは社員たちのアイデアから生まれたものです。僕が考えたわけではありません。
お客さんに共感してもらったり、新しいアイデアを得たりするのに最も必要なのはコミュニケーション能力。自分自身もそうですが、コミュニケーション能力に長けた社員を育てなければいけない。そこにどれだけ投資できるか。
うちは、幹部に社員向けプレゼンテーションをドンドンやってもらうんです。で、それがきちんと現場に浸透しているか、僕が店舗を回ってチェックします。「あなたが言っていたこと、現場に伝わっとらんよ」と。
また、リーダーシップ研修を頻繁に実施して、外部人材を招いて社員にレクチャーしてもらったりしています。大学の先生に経営の基礎を教えてもらったり、本を読んで討論してもらったり……。経営はすべての部署の人間が関わるものなので、一部の人だけが分かっていても駄目なんです。少なくても、現場にも分かる共通言語をつくらなきゃいけない。そのための取り組みです。
──デザイナーも積極的に招いているそうですが、社員に対してどんな話をしてもらうんですか?
岡崎:例えば、ヨーロッパのメゾンのデザイナーには、彼らがいかにものづくりを進化させているか、今までとは違う視点がどれだけ大事か、といったことを話してもらいました。
うちはインハウスのデザイナーでほぼすべてのデザインを賄えるんですが、外部のデザイナーとの接点も大切にしています。銀座店にあるギャラリーでは毎月、外部のクリエーターとの協業でイベントを開いているんですが、そこから常に新しい刺激をもらう。「このデザイン、いいね!」という共感を得る。お客さんに共感してもらう前に、社員同士で共感できないと始まりませんからね。
100年続くような企業になるためには、会社の中にDNAを植え付ける必要があります。社長がDNAを持っていたとしても、社長はいつか代わりますから。DNAを植え付けるって、つまりカルチャーをつくることです。我々のめざすカルチャーは「子どもの可能性をクリエートする」ということと「ベンチャーマインドを持つ」ということ。我々の創業は、いわば4人のママ友が正しい育児情報を伝えるために立ち上げたベンチャー企業だったわけですが、そのベンチャー精神がいつの間にか失われてしまった。それを取り戻さないといけない。
僕は「面白い会社」にしたいんですよ。面白い会社には面白い人材が来てくれるから。それには環境を変えることも必要で、2016年6月に本社を引っ越して新しいオフィスをつくりました。部長席も課長席もなくて、もちろん社長室もありません。社員たちのコミュニケーションを円滑にすることと、「オフィスは商売道具」という考えでデザインしました。
──「オフィスは商売道具」とはどういう意味ですか?
岡崎:取引先が「この会社と仕事をしたいな」と思ってもらえるようなオフィスにしたい、ということです。レストランでいえばオープンキッチン。中のシェフはキビキビと働いているし、おいしそうな料理は出てくるし……となれば、お客は増えますよね。いわば「オフィスのオープンキッチン化」です。
環境をデザインするのも経営者の仕事です。うちは毎月、「別品ランチ」という催しもしているんです。毎月、担当社員を決めて、おいしいランチを社内で一緒に食べる企画を提案させるんです。腕利きのシェフを呼んで社内のキッチンで特製ランチを作ってもらったり、おいしいケータリングサービスを利用したり……。人を楽しませることも一種のプレゼンテーションですよね。こんな企画を通して、プレゼンテーションの能力やクリエーティブな感覚を磨いてほしいと考えて始めました。最初はうまく行かないけど、社員の意識はだんだん変わってきています。
日経デザイン /編集長 花澤 裕二
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年5月)のものです
執筆=岡崎 忠彦(おかざき・ただひこ)
1969年生まれ。甲南大学経済学部卒業。California College of Arts and Crafts.,Industrial Design 科卒業 BFA。Tamotsu Yagi designでグラフィックデザイナーとして働く。2003年にファミリア入社、取締役執行役員などを経て2011年から現職。
【T】
トップインタビュー