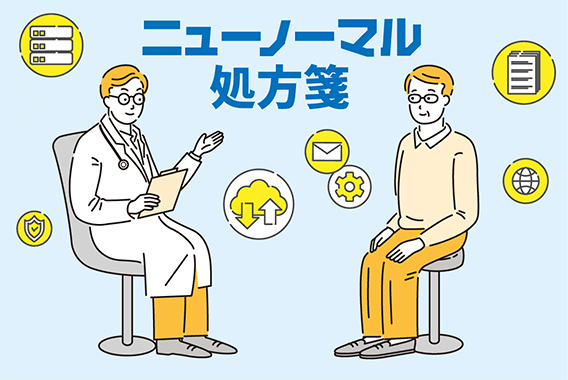
ニューノーマル処方箋(第83回)
今さら聞けない「IPv6」と「IPv4」の違いを簡単に解説。仕組みやメリット・デメリットとは?
植松電機専務 植松努氏
従業員20人弱の中小企業ながら宇宙開発に挑み、『下町ロケット』のモデルともされる植松電機。「どうせ無理」という言葉に反発、決して諦めない姿勢を貫きロケットや人工衛星開発を実現してきた。ヒト・モノ・カネが十分でなくても、工夫・改良を繰り返すことで可能になることもあると説く。
──植松電機は昨年ドラマ化され、話題になったベストセラー小説『下町ロケット』のモデルともいわれます。北海道赤平市の小さな町工場が、最先端のロケット開発に挑戦し続けることができたのはなぜでしょうか。
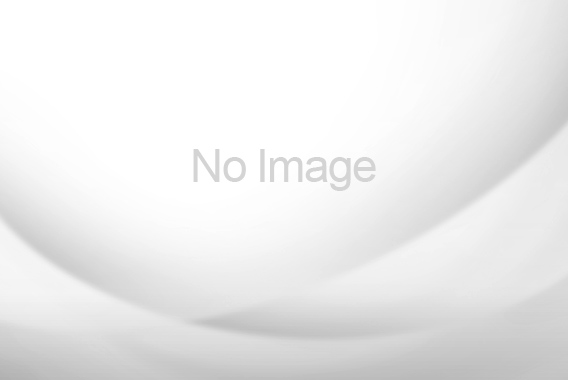 植松:植松電機はリサイクル業界などで利用される、金属をくっつける電磁石システムの製造販売が事業の中心です。一方で、2005年から宇宙開発ビジネスにも挑み、ロケットや人工衛星を開発。世界に3カ所しかない無重力実験施設の1つを持ち、他の研究機関などに貸し出しています。傍から見れば、無謀な挑戦に見えることでしょう。
植松:植松電機はリサイクル業界などで利用される、金属をくっつける電磁石システムの製造販売が事業の中心です。一方で、2005年から宇宙開発ビジネスにも挑み、ロケットや人工衛星を開発。世界に3カ所しかない無重力実験施設の1つを持ち、他の研究機関などに貸し出しています。傍から見れば、無謀な挑戦に見えることでしょう。
何年か前、小学生から「どうして諦めずにできたのですか」と質問されたことがあります。改めて「何でだろう」と考えてみましてね。「諦め方を知らなかったから」だと気付きました。
僕は子供の頃にたくさん伝記を読みました。伝記に諦めたことは書いてありません。偉人たちはうまくいかないことにぶち当たったら別の方法で乗り越えます。それが浸透していたから自分も諦めることをしなかった。
世の中には「どうせ無理」という言葉がまん延しています。子どもの頃から飛行機やロケットの仕事をしたいと思っていた僕もそういう言葉を投げかけられ続けました。でも、諦めずに夢を追っていたら夢はかなったのです。「無理」「無駄」という言葉は人間の可能性を奪う恐ろしい言葉です。僕はこういう言葉を社会から無くしたい。「だったらこうしてみたら?」に変えたいと思っています。
──宇宙開発に挑む過程ではお金の問題、人の問題などさまざまな苦労があったのではないですか。
植松:もちろん、資金には限りがありましたが、それでもロケットの部品は製造できると思いました。ポリエチレンを燃料とする安全なロケットの研究を進めていた北海道大学の永田晴紀教授と出会い、協力しながら開発してきました。
当初はロケットを造って実験しても爆発するなど失敗ばかり。コストが高いロケットエンジンを何とか安く短時間で造ろうと設計を変更したり、規格品を採用したりと工夫と改良を重ねていたら、本当にごく安い材料費でロケットエンジンが造れるようになりました。資金不足は大きなネックですが、ないならないなりに乗り越える方法があります。
──ヒト・モノ・カネに限りがある中小企業はステークホルダーと良い関係を築きながら事業を進めることも大事です。植松電機はどうですか。
植松:とにかく永田先生が取り組んでいることが魅力的だったので、「どうしたら自分たちが役に立てるだろう」ということばかり考えていました。「何をしてもらうか」ということは全く考えなかった。それが良い関係づくりにつながった気がします。
正直、それまでの僕は「この人は自分にどういうメリットをもたらしてくれるのか」「何をしてもらえるか」と考えがちでした。それで失敗することが多かった。
今の植松電機には「何でもしてあげる作戦」という必殺の戦略があります。例えば、規模の大きな会社では、現場の社員がお金を自由に動かせなかったり、フットワークが悪いことがあります。そういう場合は全部こちらで請け負う。どんどんやってしまいます。
他の人に任せていると自分の能力は失われる一方ですが、逆に自分でやれば能力が向上します。気付いたときには僕らがいないとプロジェクトがどうにも進まず、相手から「やめないでくれ」と言われる存在になります。こうなったら勝ちですよ(笑)。
──夢だった宇宙開発への挑戦ですが、「何でこんなことをやらなくてはいけないのか」と言う社員もいたと思います。納得させ、付いて来てもらうために工夫したことは?
植松:これまで社員に何かを「やってもらおう」とか「させよう」と思ったことはありませんね。まず僕自身が手を動かす。その姿を見て、社員の中に「自分もやりたい」と言い出す人が現れたら、お願いするというスタイルです。
むしろ、自分がやりたい気持ちを殺すことの方に気を使いましたね。僕が「面白い」と思うことならば、他の社員も「面白い」と思うはず。だったら、それはみんなのために取っておいた方がいいですから。かなり早い段階から僕自身が宇宙開発に直接的に関わることはやめています。
──面白いことを自分でやらず、他の社員に譲るというのは、なかなかできないことですね。
植松:大抵のことは僕がやった方がうまく、しかも早くできるでしょう。でも僕は社員より長く生きていますから、できて当たり前。若手を僕より良い環境で育てれば、もっと上手にできるようになるはず。そちらに投資した方が得だと思っています。
──植松電機は稼ぎ頭のリサイクル用電磁石事業で得た資金を、宇宙開発に投じている格好です。宇宙開発に充てるのはいくらまで、何%までといった線引きをしていますか。
植松:丼勘定ですね。ロケットでもうける気持ちはなく、それによって得られる経験や知恵、人脈こそが我々の価値だと思っていますので。社員には「経験と人脈がプラスになると判断したらやっていいよ」と伝えています。費用が数百万円にも及ぶような場合は社員と「これでどんなことができるか」と話し合いますが、基本的にはOKします。社員もコスト意識は高いので大失敗はないです。
──宇宙開発とともに、住宅コストを10分の1、食のコストを2分の1にするといった目標を掲げた「ARCプロジェクト」にも挑戦していますね。
植松:進捗状況を説明すると、人手が足りなくて当初予定より遅れ気味ですが、住宅に関しては4合目ぐらいまで到達したでしょうか。
日本の家は一代限りで解体され、社会資本が蓄積されず本当にもったいない。我々は解体しなくて済む家造りをめざし、コンテナで移動できるモジュール型の住宅を開発中です。基本モジュールは水回りを含めた生活に最低限必要なもの。家族が増えたら別の居住スペースを組み合わせます。
分野別の基礎研究はほぼ終わり、あとは実際にモジュール型の住宅を造って並べて町全体のデザインを考えていくという段階。製造業を定年退職し、その後も引き続きものづくりに携わりたいという人を住人に想定しています。自由に研究・実験できる環境を提供しながら新しいコミュニティーをつくりたい。今年中に第1次の移住者を募集するつもりです。
──この先の植松電機の展望を教えてください。
植松:宇宙開発での当面の目標は衛星の軌道投入。そのために間もなくロケットの多段化に挑戦します。会社全体としては現在、20人弱の社員数が30人ほどに膨らむでしょうか。そこから先はリサイクル用電磁石、ロケット、住宅と部門ごとに分かれていくでしょう。手掛ける事業は一見バラバラですが、「どうしたら今よりもっと良いものになるか」を追求する思想を持つ点では一貫しています。変化を恐れず「より良く」を求め続けていきたいと思います。
日経トップリーダー 構成/小林佳代
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年2月)のものです
執筆=植松 努(うえまつ・つとむ)
1966年北海道芦別生まれ。89年北見工業大学応用機械工学科卒業後、菱友計算を経て父が経営する植松電機に入社。99年に専務取締役に就任し、独自に開発したバッテリー式マグネット(電磁石)で成功を収める。2005年からロケット事業を開始。06年にカムイスペースワークスを設立して代表取締役となる。著書に『NASAより宇宙に近い町工場』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
【T】
トップインタビュー