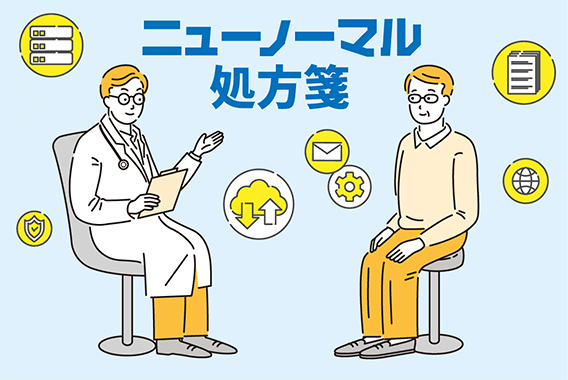
ニューノーマル処方箋(第83回)
今さら聞けない「IPv6」と「IPv4」の違いを簡単に解説。仕組みやメリット・デメリットとは?
楽天会長兼社長 三木谷浩史氏
1997年、わずか6人の従業員でスタートした楽天。2013年12月期には連結売上高5000億円を超え、日本を代表するIT(情報技術)企業になった。三木谷会長兼社長は、デフレに慣れて減点主義に陥った日本の経営に警鐘を鳴らす。
――創業して18年。業容も規模も大きく変わりました。自身が経営する上での向き合い方は変わりましたか。
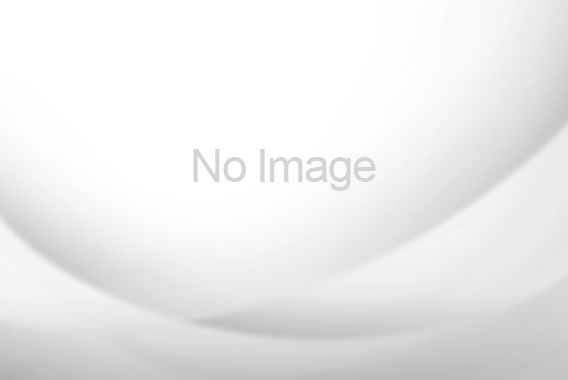 三木谷:当然6人の会社と1万4000人の会社では差が出ます。ただ、基本スタンスはほとんど変わっていません。“スピードの経営”であり、ビジョンにしている「インターネット・サービスを通じて人々と社会をエンパワーメントする(力づける)」ことは。変わった点といえば、部下に任せる仕事が増えたところです。規模と同時に社内に階層が増えます。すべてを私がコントロールすることはすでにできません。
三木谷:当然6人の会社と1万4000人の会社では差が出ます。ただ、基本スタンスはほとんど変わっていません。“スピードの経営”であり、ビジョンにしている「インターネット・サービスを通じて人々と社会をエンパワーメントする(力づける)」ことは。変わった点といえば、部下に任せる仕事が増えたところです。規模と同時に社内に階層が増えます。すべてを私がコントロールすることはすでにできません。
――これまでどのようなタイミングで権限移譲を進めてきましたか。
三木谷:明確なのは、事業が業態的地理的に広がるときです。私が掌握するのが物理的に不可能になりますから。楽天でいえば、金融やメディアといった事業は幹部に任せています。
任せられる人材を育てるために2つの取り組みを始めました。1つは若手の幹部候補を見つけ、3年ほどかけて世界中で様々な仕事を経験させる制度です。営業は強いけれど経理が苦手、人事が弱いといった課題を持つ人材を育てるのが狙いです。従来の日本型の人材育成では、何十年もかけて同じような発想で育てましたが、それでは遅いMBA(経営学修士)のように、数年ですべてを学ばせるプログラムです。
もう1つ、社費留学制度を始めました。時代に逆行しているように見えますが関係ありません。楽天にとって必要な施策です。楽天は、既存のフレームワークで表現すれば、従来の日本型と中途採用中心のシリコンバレー型のハイブリッド(混合)を目指しています。楽天は10年、20年という尺で経営を考えています。それに合わせた人材育成の戦略が必要です。
――ある大企業の元社長は、自社を長い列車にたとえました。先頭車両である自分が右に曲がっても、後続車両はまだまっすぐ走りっぱなしで、全社が曲がり始めるまで非常に時間がかかるという意味です。楽天ではそのような現象は起きていませんか。
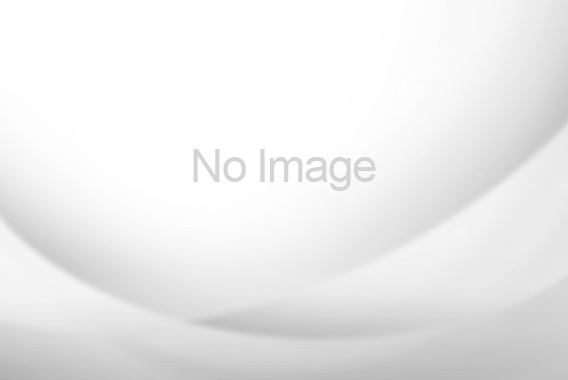 三木谷:あまり感じてはいません。それを防ぐために主に2つの策を講じています。楽天では、コミュニケーションを密にした上で、仕事の進め方についてはある程度放置するところがあります。一方、業績についてはきちんとフォローをします。
三木谷:あまり感じてはいません。それを防ぐために主に2つの策を講じています。楽天では、コミュニケーションを密にした上で、仕事の進め方についてはある程度放置するところがあります。一方、業績についてはきちんとフォローをします。
例えば、上長に対して必ず週報を出します。私にも毎週100通以上届きます。これをきちんと機能させ、現場の問題点を把握し解消します。また金曜日には、世界中に120人以上いる執行役員以上の役職者が出席するテレビ会議を実施します。これとは別に、火曜日の朝8時には、全世界のオフィスをつないだ経営会議を開きます。すべての階層に対する直接的なコミュニケーションが重要です。
もう1つ、あらゆるものの「見える化」を徹底しています。自分と関係ない部署の業績を新入社員でも見ることができます。とにかく透明性を高めることが大事です。こうした取り組みを普段からしていれば、下が付いてこないという問題は起きにくいでしょう。
――オーナー経営者の強みはどこにあるでしょうか。
三木谷:確かなのは、エージェンシーコスト(株主と経営者の利益が相反することに伴うコスト)がゼロになることです。経営者とオーナーが追求する利益が完全に一致していることは、経営にとって非常にプラスです。
もう1つは、短期的な業績とは関係しない、将来を見据えた大きな決断ができる点。2012年に実施した英語の社内公用語化は、僕がオーナー経営者だったからこそ押し切ることができました。
英語化は、一人ひとりの仕事の価値観を根底から覆すような社会的な大実験です。当時の僕は、このまま楽天が事業を続けていけば、必ずグローバル化の中でカベにぶち当たると考えていました。その考えは今も変わりません。しかし、雇われ経営者ではいくら問題意識はあっても、実際に導入することは難しいでしょう。
導入にはかなり苦労しました。最終的には、「テストで合格点に達していない社員は、朝は英語の勉強という仕事をしなさい」と言うほど。それだけ英語を重視していたのです。あと2、3年もすれば、楽天は完全なグローバル企業になれると考えています。
どういうことかと言うと、これまで楽天でビジネス戦略を担っていたのは東京大学や慶応義塾大学などの出身者が中心でした。それが、今後は米国のハーバード大学やイエール大学などの出身者になるかもしれないという話です。
英語化に踏み切れた理由には、製造業などと比べて組織がシンプルで一気通貫に取り組むことができたという点もあります。社内で「ここまでは英語、ここから先は現地語」などと線を引いてしまったらまず成功しません。
――三木谷さん自身は時間の使い方をどのように工夫しているのでしょうか。
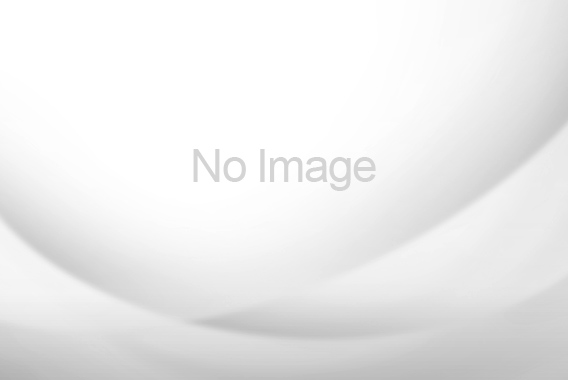 三木谷:「ものづくり」にかける時間が一番多い。これはIT(情報技術)企業の特徴といえるかもしれません。サービスの設計などが持つ重要性が、ほかの業種と比べて極端に高いと思います。その次が人事を含めた組織づくりです。
三木谷:「ものづくり」にかける時間が一番多い。これはIT(情報技術)企業の特徴といえるかもしれません。サービスの設計などが持つ重要性が、ほかの業種と比べて極端に高いと思います。その次が人事を含めた組織づくりです。
現在、ネットを通じて社会的な革命が起きています。世の中が目まぐるしく変わる中で大切なことは2つ。将来予測の精度と、それが外れたときの対応力です。その核になるのは、精緻な将来予測に基づいたプロダクトデザインと機動的な組織づくりです。
将来予測については、英語に「cut through the corner」という表現があります。リーダーには、曲がり角の向こう側にあるものをきちんと見据えられるか、もし自分で見られないなら、見られそうな人間を側に置いておけるかが問われます。僕も、米アップルのスティーブ・ジョブズさんも、ソフトバンクの孫(正義)さんも、ほかの人が「これは駄目だろう」と言ってきたことを成し遂げて会社を大きくしました。
これからの時代はますます見えにくくなるし、曲がり角の数も増えます。「こうなると思ったけど違った」という場面も当然増えます。だから周囲からは「三木谷さんはこの間はこう言っていたのに、もう違うことをやっている」と言われます。百発百中じゃないのだから当然です。
こうした失敗を許容することが、これから一番大切になります。現在の多くの日本企業では、成功の多さよりも失敗の少なさが評価されがちです。減点法から脱却しなければ、部下は誰も曲がり角の向こう側を見通そうなんてしません。
楽天も何度も組織体制を見直してきました。海外展開に当たっては、最初は国単位で組織をつくり、その後は地域本社を置きました。現在は、プロダクト軸を強化しています。硬直的な仕組みをつくってしまうと変化に対応できません。振り子のように揺れ動く事態を許容しなければいけない。それを理解しなくちゃいけないんです。前言を守り続けていたら、スピード経営なんてできませんよ。
執筆=三木谷 浩史(みきたに・ひろし)
1965年、兵庫県生まれ。88年に一橋大学商学部を卒業後、日本興業銀行(現・みずほ銀行)に入行。93年に米ハーバード大学でMBA(経営学修士)を取得。97年にエム・ディー・エム(現・楽天)を立ち上げる。現職は楽天会長兼社長。
【T】
トップインタビュー