
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
登山初心者のための番外編、先の〈peak1〉では東京都・高尾山に登りましたが、編集Kさんの登山後の様子は余裕たっぷり。それでは、と次の目標を長野県・車山に決めました。高尾山の標高が599mであるのに対して、車山の標高は1925m。一気に標高を上げたことに「いきなりハードルが高くないですか」と戸惑うKさん。きっと大丈夫だよ、となだめすかしていざ車山へ。諏訪湖の北東、霧ヶ峰高原の中心に位置する車山山頂からのパノラマビューは必見です。大絶景の高原ハイクをみなさんも一緒に体感してください。

素晴らしい展望の車山(山頂/前方に見えるのは八ヶ岳)
車山を選んだ一番の理由は、登山コースからの景色がとにかく素晴らしいことです。山の上に草原が広がり、樹林が少ないので、遠くの山々まで見渡せます。そして、岩場などの危険箇所が少なく、歩けるコースが多いので、目的に合ったプランニングができるのです。
さらには、湿原や古代の遺跡などもあり、見どころがたくさんあることも魅力です。前回(第48回/番外編peak1)は、登山の雰囲気を知ってもらうため、そしてKさんのやる気・体力を測るために高尾山を選びましたが、今回の目的は山の楽しさを体感してもらうこととしました。
5月下旬、私たちは登山口となる車山肩(標高約1800m)に到着しました。ここから車山の山頂へ向かい、蝶々深山(ちょうちょうみやま)、八島ヶ原湿原(やしまがはらしつげん)近くを通って車山肩へ戻る周回コースを歩きます。コースタイムは約4時間、日帰りハイキングの行程としても手ごろです。
肩から幅広の登山道を登っていきます。この日は運よく快晴で、空気も澄んでいました。少し歩いただけで早速北アルプスや南アルプスなど、山々の景色が広がってきます。アルプスの稜線(りょうせん)部にまだ雪は残っていますが、気候は初夏らしく、爽やかです。Kさんは「初めからこんな絶景が見られるとは想像していませんでした。感動しています」と気持ちも盛り上がってきたようでした。歩みを進めるごとに開ける山々を見渡し、約40分で山頂に到着しました。

南アルプスの甲斐駒ヶ岳や北岳、仙丈ヶ岳などを見ながら緩やかな道を山頂へ向かう
今回の山行(さんこう)のもう1つのテーマは、地図を使ってみることです。地図読みは登山に欠かせない大事なスキルの1つです。今回はその導入として、360度の展望が得られる車山山頂で、登山地図を使った山座同定(さんざどうてい)を体験してもらいました。
地図は上(地面に置いたときは奥)が北、下(手前)が南として描かれています。そこで、コンパスを使って実際の方角と地図の向きを合わせることで、山の位置関係が分かります。登山地図にある広域図と、見えている山を照合していくことで、山名を知ることもできます。慣れてくるとゲーム感覚で山を当てられて面白いですし、山の名前も覚えられます。

登山地図を使って、実際に目にしている山がどの山かを調べてみる(山座同定)
山座同定を楽しんでいると、Kさんが「スマホにいいアプリを入れてきましたよ」と言いました。見れば「YAMAP」という、登山者がよく使う地図アプリです。「YAMAP」は地形図画面の上に主要山岳の主な登山コースとコースタイムなどが表示されるアプリ。等高線が描かれた地形図で地図読みをすることは、初心者にはなかなか難しいのですが、このアプリはGPSとも連動していて、現在地が画面上、一目で分かります。操作も簡単なことから登山者に人気のようです。
山座同定に使用している紙の登山地図は昭文社刊行の『山と高原地図』ですが、実はこちらにもアプリ版(iOS/Android)があります。通常版はアプリ本体が無料で、登るエリアの地図データを有料で加えていく方式。毎年山域マップを更新するため、実態に近い登山ルートの確認ができます。また、山のSNSコミュニティー「ヤマレコ」と連携できるアプリ「ヤマレコMAP」も、上記2つのアプリのように、現在地確認のほかGPSログを表示・記録することができます。
上手に使うととても便利な地図アプリ。グループで広げて見ることができて、何より電池不要の紙の地図。現在は2つを併用する人が多いようです。地図を使うことで現在地を確認する習慣が身に付き、また頻繁に地図を見ることによって、自然と基本的な地図読みの力も付いてくるでしょう。少しずつ山のスキルを身に付けようとしているKさんの姿にうれしくなりました。地図アプリをいろいろ試して、自分の登山スタイルや好みに合ったものを使っていけばいいと思います。
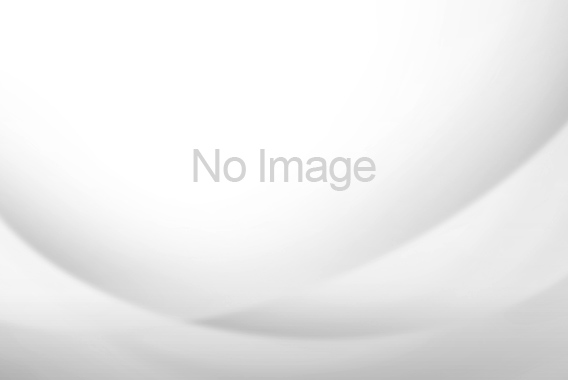
見晴らし最高の車山頂上(白い円球は気象レーダー)
山頂を後に、私たちは白樺湖や蓼科山を眺めながら車山乗越(くるまやまのっこし)へ下り、広い山頂の蝶々深山に登り返しました。途中で目を楽しませてくれたのはショウジョウバカマ(猩々袴)という変わった形の花です。花の色が真っ赤な着物を着た想像上の生き物である猩々(しょうじょう)をイメージさせ、はかまのように広がった形をしていることが名前の由来でしょうか?
その後も岩塔が飛び出している物見岩や、高層湿原(枯死した植物が腐らずに蓄積してできた湿原)である八島ヶ原湿原を見たり、鎌倉時代に流鏑馬(やぶさめ)や競馬などの武芸競技が行われたという旧御射山遺跡を見たりしながら、半日のハイキングを楽しみました。そして車山肩に戻り、山小屋の「ころぼっくるひゅって」でお茶をして帰りました。
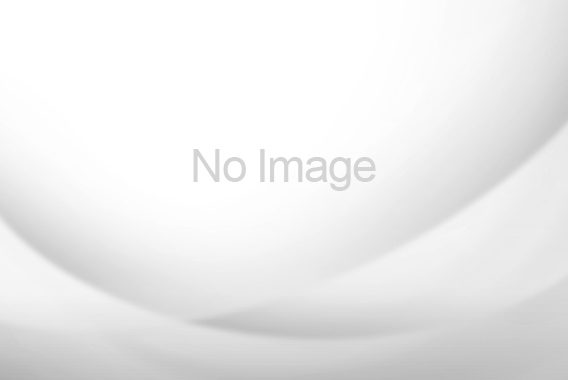
コースのあちこちで見られたショウジョウバカマ(左写真)、なだらかな地形に飛び出した「物見岩」(右写真)
今回のコースはいくつかのピークを越えるため、アップダウンはありますが、見どころが多いので、飽きることなく歩けたと思います。それほど頑張らなくても、このように登山の「いいところ取り」ができるのが車山なのです。Kさんも「景色が素晴らしいし、適度に汗が流せて、気持ち良かったです。大人の休日という感じでいいですね」と満足してくれました。そして、もう少し本格的な山登りもしてみたいという目標もできてきたようです。2回目の登山を車山にして大成功。次回の登山へ向けての期待も膨らみます。

旧御射山遺跡から、雰囲気のいいシラカバ林を抜けて車山肩へ向かう
私たちが訪れた時にはまだ雪解け直後で花は少なかったのですが、霧ヶ峰・車山は花の名山としても知られています。7月中~下旬、車山肩は一面、ニッコウキスゲの黄色い花に彩られます。また、8月に入ると、マツムシソウやワレモコウなどの花も咲き始めるでしょう。みなさんもぜひ、天気のいい日に車山へ出掛けて、涼しい高原ハイキングを楽しんでください。
▼▽Kさんメモ「車山」▽▼
「車山肩からスタートだよ」と小林さんに言われて、「肩って何ですか」と聞き返すほど登山初心者の私。その車山肩から少し上がった場所にある「ころぼっくるひゅって」のメニュー表には、山小屋創設以降の車山の歴史が簡単につづられていました。霧が濃く雪深いために、かつての車山では遭難も多かったといいます。今は車山もずいぶん整備が進んでいますが、やはり油断は禁物。トライする山の下調べと、地図の携帯は必須だと思いました。
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ