
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
初夏になり、気温が日に日に高くなってきました。今の時期は、ひと雨降るごとに高山でも雪解けが進み、残雪模様がくっきりとしてきます。そんな時期に見られるのが雪形(ゆきがた)です。雪形とは、地形や雪の溶け方によって現れる残雪の形のこと。今回はこの残雪模様にまつわる山の話をしましょう。
雪形といえば、登山者の間で最も有名なのが、北アルプス白馬(しろうま)岳に見られるものではないでしょうか?4月中旬〜6月上旬にかけて、麓(ふもと)の白馬(はくば)村から見上げると、山頂の右側斜面に左に頭を向け、尾を跳ね上げた馬の雪形が目に入ります。これは雪が解けた部分なので白馬ではなく、「黒馬」なのですが、ちょうど田んぼの代掻(しろか)きを行う時期であることから「代掻き馬」といわれています。
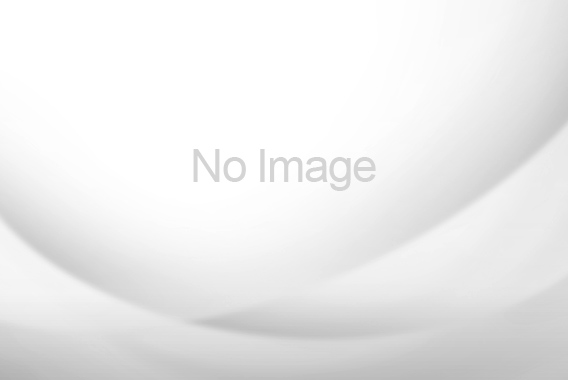
白馬岳の「代掻き馬」。左を向き、尾を振り上げている。形が分かりづらく、馬というより恐竜のよう
明治時代に地図が作られるようになると「白馬(しろうま)」に変化し、それが広まったといわれています(江戸時代からという説もある)。地元では呼びやすいことから、古くからハクバというのが一般的で、昭和31年、北城(ほくじょう)村と神城(かみしろ)村が合併した際、新しい村は「白馬(ハクバ)村」と命名されました。山が「しろうま」で、村の名は「はくば」なのは、これが理由です。ちなみに地元の人は山も「ハクバ」と呼ぶ人が多く、白馬岳にある山小屋、白馬山荘は「はくばさんそう」と読みます。
白馬岳のように、馬の雪形が現れる山は他にもあり、木曽駒ヶ岳、越後駒ヶ岳など、全国に存在する駒ヶ岳のいくつかは雪形が由来だといわれています。また、白馬岳の南側の並びにある五竜岳は4月下旬〜5月下旬、山頂直下に武田家の家紋である「武田菱」が見られます。戦国時代に武田家の支配下にあったこの地では御菱(ごりょう)と呼ばれ、後に五竜に変化したともいわれています(由来には諸説ある)。五竜岳の武田菱は形がはっきりとしていますし、比較的長い期間見られるので、雪形にあまりなじみがない人にも見つけやすいでしょう。
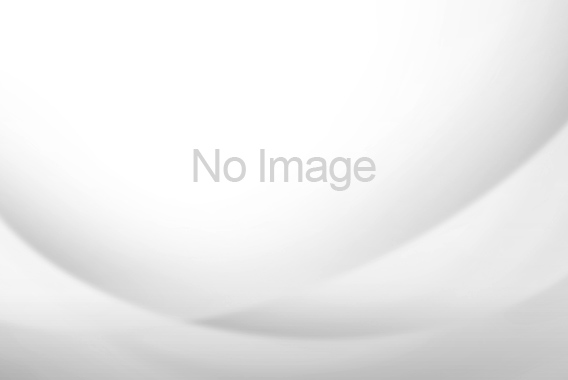
五竜岳の「武田菱」。菱形が4つ並び、武田家の家紋のように見える
他にも、雪形が由来となったのは爺ヶ岳(じいがたけ/種まき爺さん)、蝶ヶ岳(蝶)、農鳥岳(のうとりだけ/鳥)などがあります。中央アルプス、宝剣岳の南側にあるユニークな名のピーク・島田娘も、6月に伊那から見た雪形が島田髷(しまだまげ)を結った女性の横顔に見えることから名付けられました。
また、山名にはなっていませんが、身近なところでは富士山の農鳥もよく知られています。4月下旬〜5月下旬、富士吉田から見た富士山の八合目付近に現れます。初期は羽をなびかせた鳳凰のようで、時期が進むとヒヨコのようなかわいらしい形になります。
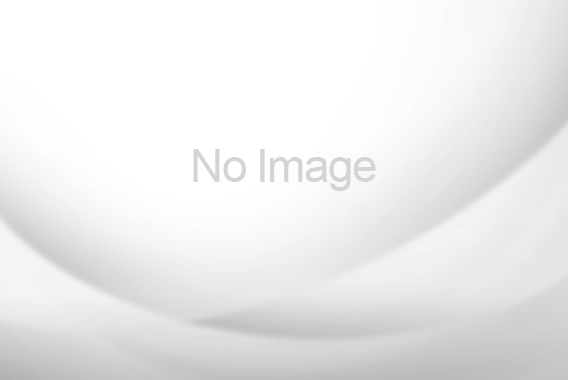
富士山の「農鳥」。小鳥が左を向いている。時期によって形が変わるのが面白い
昔は雪形を見ることで、田植えや種まきの時期の目安としてきました。代掻き馬、種まき爺さん、農鳥など、農業にちなんだ名が多いのはそのためでしょう。また、春の忙しい農作業の合間に残雪模様を見て、和んでいたのかもしれませんね。
さて、そのように麓の農民たちの間で口伝されていた雪形が登山者の間に広まったのは、1981(昭和56)年に刊行された、山岳写真家の田淵行男による写真集「山の紋章 雪形」がきっかけでした。
田淵さんは高山蝶の研究をしたことでも知られますが、「雪形マニア」でもあり、全国の伝承を調べ、取材をして写真に収めました。このとき、麓に伝わるものだけでなく、槍沢の「童子の顔」、間ノ岳の「鬼面」、大雪山の「白鳥」など、自分でも新しい雪形を見つけ、それらも写真集に収めました。
※「山の紋章 雪形」は絶版ですが、安曇野にある田淵行男記念館に行くと見ることができます
雪形は全国各地にあり、田淵さんの本によると全国に300以上も確認できるそうです。そんな中でも秀逸だと思うのが、北アルプス南部、中岳に現れる「舞姫」です。
これは田淵さんが発見したもので、着物を着た女性が、横を向き、長い髪と振り袖を揺らしながら、扇(花笠ともいわれる)を手に、しなやかに舞っているように見えます。まさに、自然がつくり出すユーモラスな芸術です。

左を向いて優雅に踊っている中岳の「舞姫」
私はこの「舞姫」を見たくて、数年前の5月中旬、この雪形が一番美しく見えるポイントの常念(じょうねん)岳に登りました。舞姫が現れる中岳の東面は山深いため、麓からは見ることができず、それを目にするには安曇野側から1泊2日の行程を歩かなければなりません。ちなみにこの常念岳も、安曇野から見ると5月中旬にトックリを手にした常念坊の雪形が現れることが由来となっています。
さて、一ノ沢の登山口から沢沿いに登ること5時間弱。全身に汗をかき、足が重くなる頃、やっと中岳が見渡せる稜線(りょうせん)に来ました。この日は運のいいことに快晴です。さあ、舞姫は見られるでしょうか?
梓川の対岸にそびえる槍ヶ岳から左へ続く稜線をたどると、中岳のピークがあり、その直下に姫が舞っているはずですが……。残念ながら、登るタイミングが早過ぎたようで、舞姫はまだ雪に埋もれ、ポニーテールをした幼い女の子のような姿でした。帰ってきてからよく調べたところ、舞姫が見られるのは6月〜7月だそうです。
その後も何度か常念岳には登っていますが、舞姫が見られるのは梅雨時ということもあって、タイミングを合わせるのが難しく、天気が悪くて見えなかったり、雪解けが進み過ぎて、ずいぶんとふくよかな舞姫になってしまっていたりと、なかなか田淵さんの本にある写真のような美しい姿を目にすることができずにいます。
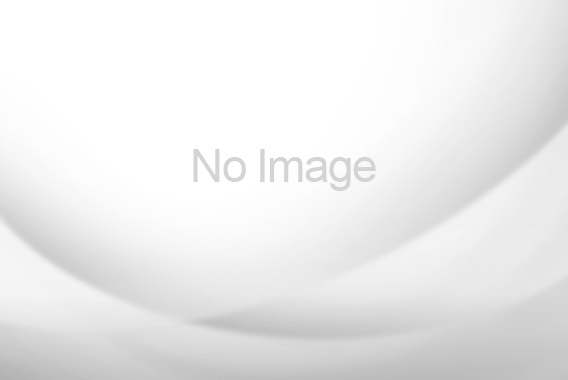
筆者が撮影した、幼い女の子のような「舞姫」。姫になるには、もう少し雪解けしないと
今回は、山に現れる雪形をいくつか紹介しました。みなさんも山へ出掛けたとき、想像を膨らませて残雪模様を観察し、古くから伝わる雪形を見たり、オリジナルの雪形を見つけてみたりしてはいかがでしょう。私も田淵さんの舞姫を見るだけでなく、それを超えるような、新しい雪形を見つけに、山へ出掛けたいと思っています。
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ