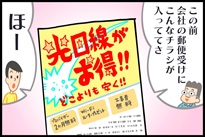
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
夏の登山シーズン、みなさんはどのような山登りを楽しみましたか?私は槍ヶ岳、穂高岳、富士山、那須岳などに登り、さらに今までにない大きな山登りをしてきました。今回はそのお話をしたいと思います。
その山登りとは南アルプスの大縦走です。南アルプスは長野・山梨・静岡の県境に、南北約120㎞にわたって連なる巨大な山脈。同じく日本の山系を代表する北アルプスや中央アルプスと比べても1つひとつの山が大きく、登るのが大変なことで知られています。
私が歩いたのは南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳(2967m)を起点に、3000m峰最南端の聖岳(ひじりだけ、3013m)まで。途中には、南アルプスの女王と呼ばれる仙丈ヶ岳(3033m)、日本第二位・第三位の高峰、北岳(3193m)と間ノ岳(3190m)があり、さらには山脈中央部にまるで兜のような岩峰を突き出す塩見岳(3052m)、悪沢岳(3141m)、赤石岳(3121m)と3000m峰が連なります。
歩行距離は約185㎞、行程内のすべての登りを合わせた累積標高差は登り約1万20m、下り約9915m(地図ソフトを使用し、2万5000分の1地形図上で計測)という壮大な縦走路を、予備日を含めて13日間、一度も山を下りずに歩き通しました。
4月に行ったマナスルのトレッキング(第23回参照)が日本からの移動日と予備日を含めて12日の行程でしたが、今回のほうが登山の難易度が高く、それこそ、気力・体力が充実していないと達成できません。長年登山を続けてきた私にとっても、今までにないどころか、一生に一度あるかないかというほどの挑戦です。また、他の仕事を調整し、それだけの日数を山にかけることは簡単ではありません。やりがいのある大きな機会を得て、まずは甲斐駒ヶ岳に向かいました。

甲斐駒ヶ岳の登山道に並ぶ石碑群
お盆最中の早朝、甲斐駒ヶ岳の登山口である竹宇駒ヶ岳神社を出発。日本三大急登の1つとして知られる黒戸尾根を登り始めました。1つ目のピークとなる甲斐駒ヶ岳の山頂まで、いきなり標高差約2200mを行く厳しい道です。前半は急坂ながら、広葉樹、針葉樹の森がキレイで、緑を楽しみながら進みますが、後半になると岩場が現れ、ハシゴや鎖場の連続で、スリップしたら深い谷底に落ちてしまうようなスリルあふれる道となります。
しかし驚くのは、そんな登山道の脇に石仏や石碑が無数に置かれていること。甲斐駒ヶ岳は修験の山で、江戸時代以降、信仰の山として登られてきました。道具が調い、登山道が整備されている今でさえ登るのに精いっぱいの険しい道なのに、数十キログラムあると思われる石碑を担いで登る人々の思いとはどんなものだったのか想像もできません。
山頂を本宮とする駒ヶ岳神社の由緒を見ると、京浜方面あるいは阪神地区にまで「駒ヶ岳講」が結成されたとあり、明治から戦前まで活動が盛んだったそう。全国に数ある「駒ヶ岳」の中でも最も標高が高い山だけに、山への信仰や憧れもいっそう強いものだったのではないでしょうか。先達の足跡に励まされるように尾根の先へと歩を進めます。
さて、2つ目のピーク、仙丈ヶ岳からは仙塩尾根という、歩く人のほとんどいない縦走路を進みます。縦走路というと、展望を楽しみながらの稜線(りょうせん)漫歩を思い浮かべる人が多いと思いますが、南アルプスではそうは行きません。稜線のアップダウンが激しく、ハイマツ帯(森林限界以上で低木が群生する帯域)から標高差で数百メートルを一気に下り、森林限界下まで達したら、また樹林帯を数百メートル登り返し、ハイマツ帯に出ることの繰り返しです。あまりの距離の長さと急坂に、ふくらはぎも、太ももの筋肉もパンプアップして悲鳴を上げそうでした。でも、そのようにして登ったことによって、今までにないほど、山との距離が縮まったように思います。
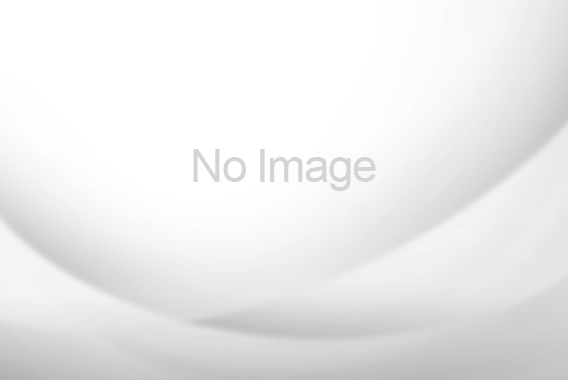
南アルプス中央部の塩見岳を見ながら縦走路を進む
天候が不順で、山々は霧に覆われることが多かったものの、要所では青空にそびえる山々の姿を拝むことができました。また、雲上の稜線で秘密の花園のような美しいお花畑に出合いました。私にとって、まさに「人生を輝かせる」山の経験です。
縦走の最中には、大規模な滝雲が目の前に現れたり、幻想的なブロッケン現象など思いがけない気象現象に次々と遭遇し、とてもエキサイティングな時間を過ごせました(気象現象の詳しい解説は第24回を参照)。

霧に写った自分の影の周りに虹ができるブロッケン現象
ほぼ2週間にわたる大感動の山旅の話は次回へつなげたいと思います。その前に、この山旅の様子はNHK BSプレミアム「にっぽんトレッキング100」で9月下旬に放送される予定です。この夏、南アルプスの山で出合った絶景の数々をぜひ動画でもお楽しみください。
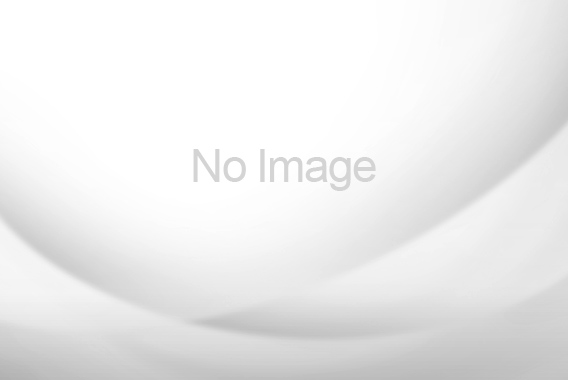
荒川岳山腹で見た朝焼けと富士山(中心よりやや右手奥)
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ