
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
海外のユニークユーザーが多い人気の旅行サイト「トリップアドバイザー」が発表した「行ってよかった!日本の城ランキング2016」で、姫路城(兵庫県姫路市)が1位を取りました。松本城(長野県松本市)、二条城(京都府京都市)といった日本人にはなじみのあるお城も、外国人観光客からの支持を年々集めているそうです。読者のみなさんの中にも城に興味があるという人が多いのではないでしょうか?
そして今、城ファンから熱い注目を集めているのが中世の「山城」です。今回は、山城をめざして山登りを楽しみます。
山城とはその名の通り、険しい「山」を利用して建てられた城のこと。日本三大山城といえば岩村城(岐阜県恵那市)・高取城(奈良県高取町)・備中松山城(岡山県高梁市)に代表され、中でも備中松山城は、天守が現存している唯一の山城です。訪れる人も多く、冒頭にご紹介した日本の城ランキングでは7位にランクインしています。残念なことに、かつては各地にあった無数の山城ですが、今では建物を残しておらず、木々に覆われ、一見はただの山に戻りつつあります。
とはいえ、当時の遺構が今もひっそりと眠り、冒険心をくすぐるものもいっぱいあります。山城は日ごろ楽しんでいる登山とフィールドは同じです。城巡りと山歩きの両方を同時に楽しめるとあって、私もそんな山城の1つ、山梨県甲府市の要害山城に行ってみました。
甲府といえば、歴史ファンならずとも思い浮かべるのが戦国時代の武将・武田信玄でしょう。その武田家が拠点としていただけに、甲府周辺には城跡が多くあります。中でも要害山城は甲府市中心部にある躑躅ヶ崎(つつじがさき)館(武田家の館)の裏山にあり、信玄の父・信虎から子・勝頼の時代まで3代にわたって、守りの要となった場所です。
甲府駅から北へ2㎞ほど行くと躑躅ヶ崎館の跡地である武田神社があります。そこからさらに北へ2㎞ほど進んだところにあるのが要害山の登山口。入り口に要害山の概要が書かれた案内板があり、それを見ながらハイキングを開始しました。

道の両側が狭くなっている門跡
初めは薄暗い杉の植林地をいく、低山歩きでよくある風景です。10分ほど登ったところで足元に「史跡境界」と書かれた小さな案内板を発見。さらに登山道をたどると「門跡」と書かれた場所に出ました。早速山城の遺構です。よく見ると、その部分だけ道が狭まり、土に埋もれた石垣が道の両側に残っていました。ここに門を築いて敵の侵入を防いだのですね。

山の尾根を断ち切って敵の侵入を防ぐ防御施設、堀切
そのすぐ先は四角い広場となっており、周りは土塁と呼ばれる土の壁で囲まれています。ふと気付けば、今、私がいる場所は周囲より数メートル低くなっています。門を突破した直後にはきっと、四方から武田方に囲まれて槍やり弓で一斉攻撃を受けることでしょう。城は「守りやすく、攻めがたい」といわれますが、攻め手の気分で想像してみると、いかに自分が不利な場所に立たされているかが分かります。
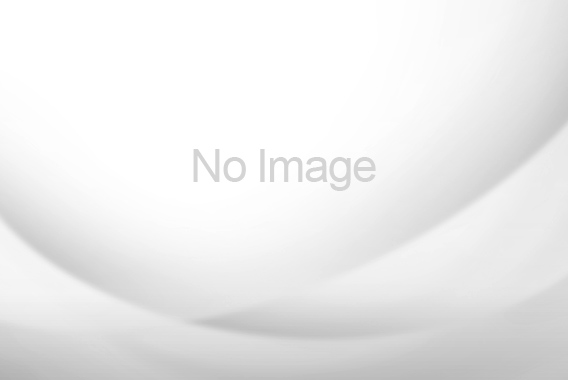
籠城戦には欠かせない井戸の跡もあった
山の斜面を谷のように縦に掘り、敵の横移動を防いだ「竪堀」の跡や、曲輪(くるわ)と呼ばれる防御施設跡の平地を見ながらさらに登っていきました。途中には、籠城戦に欠かせない井戸の跡もあります。その間にもいくつもの「門跡」があり、何重にも防御の壁が造られていたことが分かります。相当の犠牲を出さなければ、この城を攻め落とすことは困難だろうな、山の高低差も生かされていて、よくできているものだなあと感心しました。
そして、歩き始めてから約1時間後にたどり着いた山頂には東西73m、南北22mの平地がありました。ここには城でもっとも重要とされる主郭部があったとのこと。現在は木々に囲まれ、草の生えた平地の周りに土塁跡が見えるだけですが、信玄公の時代には、ここにどんな形の建物があったのだろうかと想像を巡らせるとワクワクしてきました。
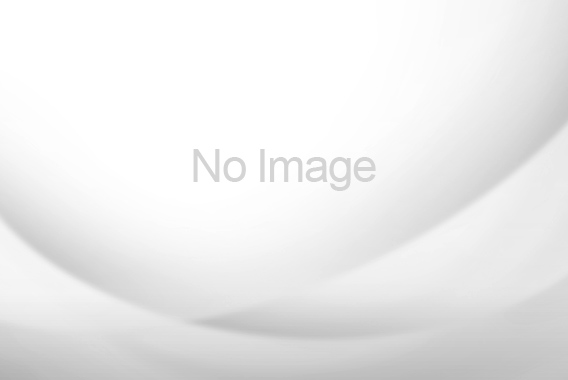
要害山の山頂に立って、昔日を想像してみる
要害山を歩いてみると、どこから攻めてもトラップにかかるように山全体に土木工事が施されていました。武田家は特に優れた築城技術を持っていたそうです。遺構の1つひとつを探し、攻め手・守り手、それぞれの視点で見てみると、いつもの山登りとはまた違った発見の連続でした。
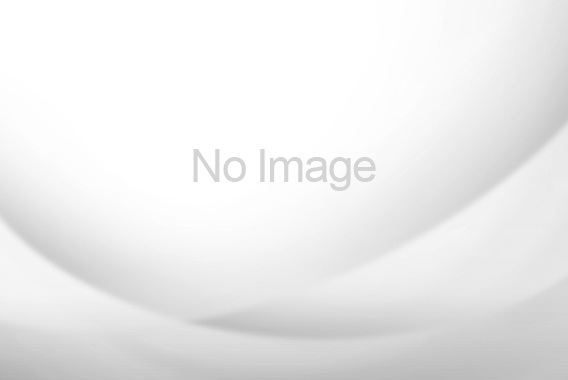
信玄公御歌とされる「人は城人は石垣人は堀……」がしのばれます
山城巡りは春までがシーズンです。なぜなら木々が葉を落とし、夏より視界がいいので、はっきりと周囲を見渡すことができます。また、樹林の下草も枯れるので、堀や土塁の形がよりはっきりと確認できるというメリットもあるからです。
2016年12月末には、城をテーマとした初の大イベント「お城EXPO」が横浜で開催されるなど、ここ数年はかつてないほどの城ブームだといわれています。日本にはかつて2万5000にも上る城が存在しており、きっと身近な場所に山城跡を見つけることができるでしょう。雪が積もっていても、それなりの装備を整えて歩きを合わせた低山歩きを楽しんでみませんか?今までとは違った魅力を発見できることでしょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年1月30日)のものです。
【関連キーワード】
トリップアドバイザー「日本の城ランキング2016」
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/castles_2016/
お城EXPO
http://www.shiroexpo.jp
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
人生を輝かせる山登りのススメ