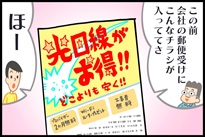
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
ナカバヤシ 代表取締役社長 辻村肇 氏
1923年に製本事業で創業したナカバヤシは国内最大シェアを持つアルバムやノートなどの文具、オフィス用品の製造販売で知られている。それに加え、近年は発電事業や農業など、コアビジネス以外にも事業領域を広げ、話題になっている。なぜ、手掛けたことのない新しい領域に挑むのか。その動機と狙いについて、代表取締役社長・辻村肇氏に話を伺った。
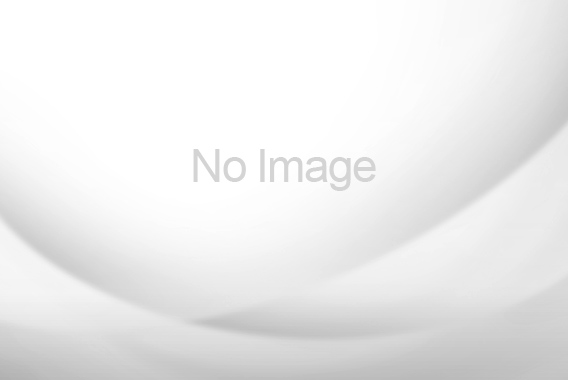
――2013年に日本紙パルプ商事、三光との共同出資で島根県松江市に松江バイオマス発電を設立。電力事業を始められました。また、2015年からは兵庫県養父市でニンニクの生産も手掛けられています。なぜ、こういった事業を始められたのでしょうか。
辻村:一言でいうと、「肩幅の広い会社」になりたいと思っているんです。今は時代の変化が激しくて、明後日から売れなくなる製品やサービスがあってもおかしくありません。今売れている当社のノートも、5年後に使われているかどうかは分かりません。そういう意味で、新しいジャンルのビジネスをたくさん持っておきたい。それがめざしている「肩幅の広い会社」の姿です。
木質バイオマスの発電所を設けた島根県は1971年に簸川郡佐田町(現・出雲市)などに工場を作って以来当社の大きな生産拠点になっており、今も5つの工場が稼働しています。約半世紀にわたって我々の事業を応援していただいているので、恩返しをしたいと思っていました。
それに私は個人的に、日本全体で見れば原子力、火力、水力、さらに太陽光、風力、バイオマスといったいろいろな発電方法を用意して、何かあっても電力の供給が損なわれない状態になっているほうがいいのではないかと思っていたんです。
震災を契機にエネルギー問題が取り上げられる中、松江市にあるずっと使われていない当社所有の遊休地の近くに中国電力の変電所があることが分かった。島根県は豊富な森林資源に恵まれた所ですから、「木質バイオマス発電ができるんじゃないか」と思って、地元の素材流通協同組合へ相談に行きました。原木の供給や発電に必要な木材チップの加工をしている業者さんの組合です。そうしたら「協力させてもらいます」という返事をすぐにいただいた。そして地元の自治体もバックアップしてくれるというのですから「これはやるしかない」と。
他の地方とも共通する課題ですが、島根県も人口が減っています。そんな中で産業振興にも悩んでいます。木質バイオマス発電事業には、林地残材をチップに加工する業者さんが必要ですし、チップの輸送も要ります。太陽光発電などと比較すると地元のさまざまな所にお金が回ります。ですから、この事業を興したことで、わずかながら島根県に恩返しができるのではないかと思っています。もちろん、当社としても、ほぼ計画通りの収益を上げさせていただいています。
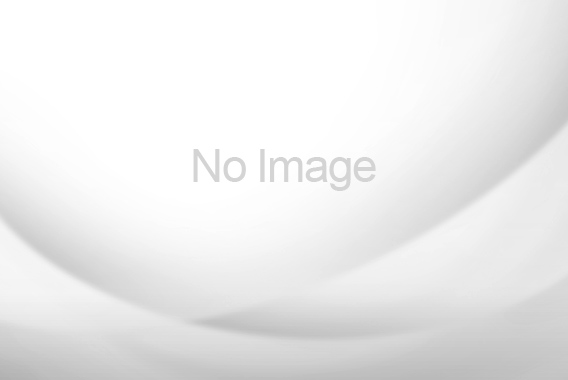
――農業を手掛けられた理由は?
辻村:こちらも当社の事業所立地と密接に関係しています。農業を開始した兵庫県養父市にある工場は、雑誌のバックナンバーの合冊製本や資料修復をメーンの業務にしています。しかし、データの電子化が普及して、製本の受注が減ってきているんです。主に大学の図書館から注文をいただいているのですが、最盛期の半分以下に受注は落ちています。でも注文をいただいている以上、事業をやめるわけにはいきませんし、養父市の拠点は維持していく必要があります。そのためには製本以外の事業で売り上げをつくる必要が出てきたのです。
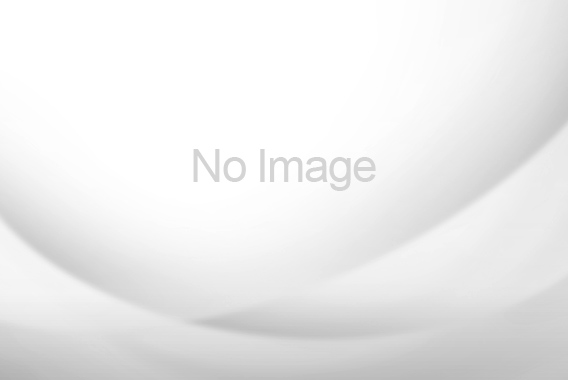 そんなとき、たまたま巡り会ったのがニンニクの生産だったんです。雑誌の合冊製本は7月から9月と12月から3月が受注・生産のピークで、4月から閑散期に入ります。一方、ニンニクは秋に種付けをして、5月下旬から7月が収穫で忙しい。繁忙期と閑散期が見事に入れ替わっているので、無理なくできるんです。
そんなとき、たまたま巡り会ったのがニンニクの生産だったんです。雑誌の合冊製本は7月から9月と12月から3月が受注・生産のピークで、4月から閑散期に入ります。一方、ニンニクは秋に種付けをして、5月下旬から7月が収穫で忙しい。繁忙期と閑散期が見事に入れ替わっているので、無理なくできるんです。
今計画的に耕作面積を増やしているところで、順調に収穫量は増えています。まだ投資が先行していますが、3年先くらいには黒字化できるのではないかと見ています。
――新しいことに挑戦する文化がナカバヤシにはあるのですね。
辻村:それは間違いありません。当社はもともと製本事業からスタートして、企業向け手帳を作るようになり、アルバム、ファイル、ノートといったステーショナリー事業に業容拡大しました。さらにシュレッダ、製本機、デジタルガジェットへと事業を広げていきました。それにとどまらず、チャイルドシートや点滴スタンドといったベビー・メディカル関連事業も展開しています。これだけ幅広い事業に取り組んでいるのは、新しいことに挑戦するスピリットあってこそのことだと思います。初代社長は「今に満足するな。新しいことをやれ」といつも言っていました。
私も若い頃は結構失敗しました。しかし、責任を取れという話は1回もありませんでした。失敗に対して上司は寛容で「しゃあないな。切り替えてやろう」と言ってもらえた。この姿勢は、私も大事にしようと思っています。押さえつけたら、新しいことをやろうと誰も言わなくなりますから。
――新しい事業は成功すれば利益が上がるかもしれませんが、リスクも伴います。そうしたリスクと利益とのバランスについてはどのように考えていらっしゃいますか?
辻村:発電や農業のようにまったくの新しい分野に取り組むのは、実はそれほど多くありません。既存事業に関して強化や新しい展開を図っていけばリスクは軽減されます。
既存事業関連でも、新規性の高いチャレンジはできるんです。例えば、従来のノートより約20%軽い「ロジカル・エアーノート」。これは紙の厚さは同じにして密度を変えることで重量を抑えた画期的な製品でヒットしています。
 印刷製本事業では、データを送ってもらえば帳票や請求書の作成・出力から封入・発送までをすべて手掛けるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のサービスを始めました。このように、既存事業において高い付加価値を持った製品・サービスの開発に力を入れています。
印刷製本事業では、データを送ってもらえば帳票や請求書の作成・出力から封入・発送までをすべて手掛けるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のサービスを始めました。このように、既存事業において高い付加価値を持った製品・サービスの開発に力を入れています。
また、既存事業とシナジー効果のあるM&Aを積極的に行っています。M&A先の基準は、「ニッチな市場で大きなシェアを持っており、収益性が高い」こと。こうした企業と一緒になり、シナジーを生むことで、既存事業の強化を図っています。
このように既存事業の領域で売り上げを確保しながら、一方ではそこに満足せず、今まで手掛けていなかった事業領域にも挑戦していく。こうしたスタンスで考えています。
――最後に、社員に伝えたいメッセージをいただけますか?
辻村:最近、若い社員から文房具に触りながらお茶が飲めるカフェを作るという提案をもらいました。面白い企画なので、今年の夏までに実現しようと思っています。しかし、こうした提案がまだまだ少ないと感じています。もっと、新しいことをやる気概が欲しい。今に満足するな、です。
とにかく、もっと野心を持ってほしい。私は、子どもの頃から社長になりたいと思っていました。今、ナカバヤシにそう思っている社員が果たしているのか。「出世すると大変そうなのでそこそこで」などと考えていないか。「社長になってやる」という気持ちを持った社員が1人でも多くいるほうが、会社は元気になれます。「社長になって会社を変えてやる」くらいの気構えを持って、仕事に臨んでください。
執筆=辻村 肇(つじむら・はじめ)
1953年大阪府生まれ。76年京都外国語大学外国語学部卒業後、ナカバヤシ(株)に入社。当時勢いのあった量販店へ文具やアルバムを販売する営業に12年間携わった後、新規事業であるオフィス家具事業部に6年間在籍。その後、世の中のコンピュータ化を背景に立ち上げたビジネスフォーム事業へ配属。伝票や納品書、送り状の印刷を請け負う営業を経て、現在主力となるDPS事業に取り組み、同事業の総責任者に。2005年取締役、2007年常務取締役、2008年専務取締役を経て2009年代表取締役社長に就任。グループ会社の社長も兼任している。
【T】
トップインタビュー