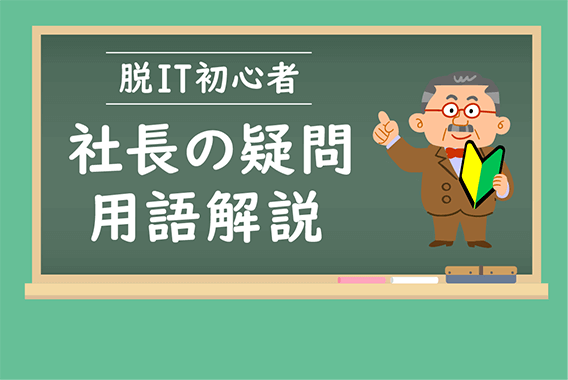
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
 人と馬が一体となって挑む馬術競技。2020年東京五輪では、7度目の挑戦で悲願のメダルを狙う杉谷泰造選手などが注目を集めている。この競技は、障害馬術、馬場馬術、総合馬術という大きく3つのカテゴリーがあり、多くの国で愛されている。
人と馬が一体となって挑む馬術競技。2020年東京五輪では、7度目の挑戦で悲願のメダルを狙う杉谷泰造選手などが注目を集めている。この競技は、障害馬術、馬場馬術、総合馬術という大きく3つのカテゴリーがあり、多くの国で愛されている。
男女が同じステージで競い合うルールで、競技者がリズムとバランスをコントロールし馬が運動するという競技特性を持っている。70歳を超えてもトップレベルで活躍できる点も人気を集める理由だ。そうした馬術競技で、日本におけるオリンピック金メダリストはたった1人。それがバロン西である。
バロン西はいわゆる愛称で、本名は西 竹一(にし たけいち)という。「バロン」とは貴族の爵位の一つで日本語に訳すと「男爵」となる。西氏は1902年、旧華族の家に生まれ、10歳になった1912年には父の死去に伴い、男爵の爵位を継承して「西男爵」となった。しかし、ここでは氏への敬意とその海外にもまたがる活躍にふさわしくバロン西と表記させていただこう。
若きバロン西の大きな転機は東京府立第一中学校在籍中に訪れた。周囲は父の跡を継ぎ、外交官になると思っていたようだが、彼は突然、陸軍幼年学校への入学を希望し、転籍する。そこで馬の魅力を知り、馬術を始めたという。
その後、陸軍騎兵学校へと進み、フランス留学で馬術を学んだ馬術課長・遊佐幸平中佐をはじめとする指導者に恵まれ、馬術のスキルを磨いていく。乗馬法は、ドイツ式、フランス式、イタリア式に分類されるが、バロン西はイタリア式馬術をベースに独自のスタイルを生み出していく。
そして次の大きな転機、それは生涯のパートナーとなる愛馬「ウラヌス号」との出合いだ。
イタリアに誰も乗りこなせない馬がいるという話を聞いたのがきっかけだった。彼は6カ月(!)の休暇を取り、現地に向かう。ちなみに、その航路で出会ったのが当時のハリウッドの大スター、ダグラス・フェアバンクスとメアリー・ビッグフォード夫妻。バロン西と銀幕のスターは意気投合し、その後も長きにわたる親交を結ぶことになる。
1930年3月、イタリアでウラヌス号を見たバロン西は、一目で魅せられてしまう。体高181㎝という大きな馬体で、額には星のマークがあり、そこから「天王星」を表すウラヌスと名付けられた。彼は、この気性の激しい馬を約2000円の自費を投じて購入した(1929年の銀行の初任給は70円)。
彼は、その背に誰一人乗せなかったじゃじゃ馬をすぐに乗りこなし、早速ヨーロッパ各地の馬術大会に参戦し、好成績を残した。
そして、その日が訪れる。1932年8月14日。第10回オリンピック ロサンゼルス大会の最終種目として「大賞典障害飛越競技」が開催された。この競技には4カ国、11組の人馬が参加。コースの難度は非常に高く、完走したのはわずか5組。その難関レースをバロン西とウラヌス号はほとんどノーミスで走り切り、金メダルの栄冠を勝ち取った。
レース後、新聞記者に囲まれ、インタビューされたバロン西は一言、こう答えた。
「We won」
日本人記者はその言葉を聞き、「我々、日本は勝った」と打電したが、それは間違いだ。「わたしとウラヌス号が勝った」と、バロン西は言ったのである。
日本のオリンピック馬術参加選手たちは、大会2カ月前にロサンゼルス入りしている。バロン西は現地で金色のスポーツカーを購入し、毎日、その車に乗ってパーティー会場に通った。恐らくダグラス・フェアバンクスの紹介もあったのだろう、喜劇王チャップリンをはじめ、映画スターたちとの交流も話題になった。
しかし、帰国後のバロン西は冷遇された。派手な行動が次第に陸軍に疎まれ、また騎馬から戦車へという時代の変化も相まってのことだったのだろうと想像する。そして、第二次世界大戦では硫黄島に出兵し、1945年3月22日、戦死した。
近年の企業の求人広告に、「出るくいを歓迎」といったキャッチコピーを時折見かける。組織に新鮮な風を吹き込むとがった人材に期待し、優遇するという訴求だろう。
陸軍とバロン西の関係を考えると、とがった人材を迎えるときには、迎える側にそれを生かす覚悟や力量が必要だということが分かる。とがった人材によって組織に吹き込まれる風は、和を乱す原因にもなり得る。それでも他のメンバーにはない能力や個性を備えた人材の突破を評価し、使いこなす組織の懐の深さが試される。
当時の陸軍は活用できなかったかもしれないが、バロン西の語学力、豊富な海外体験、海外の人脈は、情報収集や戦略立案の貴重な財産になった可能性もある。また、第二次大戦後も存命であったなら、日本の復興に力を発揮したかもしれない。とがった人材の生かし方は簡単ではないかもしれないが、その適性を見極めれば、得られるものは大きい。
バロン西は戦死するまでウラヌス号のたてがみの一部をポケットに忍ばせていたという。
「自分を理解してくれる人は少なかったが、ウラヌスだけは自分を分かってくれた」
バロン西の言葉だ。
彼が戦死して1週間後、東京で余生を過ごしていたウラヌス号も主(あるじ)の死を感じたのか、静かに息を引き取ったという。なんという哀切、なんという絆だろう。
東京オリンピックでも馬術では「馬場馬術」「総合馬術」「障害馬術」の3競技が実施される。競技者と馬の絆の一点に絞っても、心動かす場面に出合えそうだ。
執筆=藤本 信治(オフィス・グレン)
ライター。
【T】
アスリートに学ぶビジネス成功への軌跡