
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
今年5月に開催された木南道孝記念陸上競技大会(大阪市)において、女子やり投げの北口榛花選手が64m36の日本新記録で優勝。陸上競技のフィールド種目としては、東京五輪の参加標準記録を突破した最初の日本人選手となった。
こうしたニュースに接して思い出されるのが、日本におけるやり投げ競技の歴史の中でもひときわ異彩を放つ溝口和洋氏の名前だ。
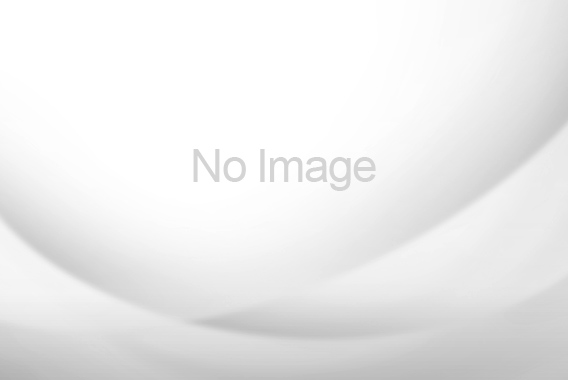 彼が出場したオリンピックのロサンゼルス大会、ソウル大会は、共に予選落ちを喫しているものの、1989年にはWGP(ワールド・グランプリ)に参加し、日本人初の総合2位に輝いている。その1989年のWGPシリーズの初戦、米カリフォルニア州サンノゼで5月に開催されたブルース・ジェンナー・クラシックで大記録が生まれた。
彼が出場したオリンピックのロサンゼルス大会、ソウル大会は、共に予選落ちを喫しているものの、1989年にはWGP(ワールド・グランプリ)に参加し、日本人初の総合2位に輝いている。その1989年のWGPシリーズの初戦、米カリフォルニア州サンノゼで5月に開催されたブルース・ジェンナー・クラシックで大記録が生まれた。
1投目の記録は80m24。2投目は84m82。続く3投目はファウル。そして4投目。勢い余ってあわや左足がファウル・ラインを越えるかと思われたほどに全速力で助走した後に投じられたやりは大きな弧を描くと、はるか前方の芝生に突き刺さった。計測結果は87m68。これは当時の世界記録であった87m66を2㎝更新した世界記録だ。
しかし、その記録は不可解ともいえる再計測によって8㎝も縮められ、87m60に修正されてしまうのである。一度は世界記録とたたえられた記録が取り消されたときの落胆は察するに余りあるが、溝口氏の次のような言葉に救われる思いがする。
「世界記録はもちろん最大の目標ではあった。しかしそれ以上に、私はそこに至る経過を大事にしたかった」(『一投に賭ける~溝口和洋、最後の無頼派アスリート』 上原善広著)。
本のタイトルに“無頼派アスリート”とあるように、同著では溝口氏が「オリンピック代表選手のくせにタバコを吸う」とマスコミからたたかれていたことや、お酒や女性にまつわる無頼派伝説が紹介されている。同時に、監督やコーチに頼らず、アスリートとしての可能性をすさまじいまでのいちずさで自ら切り開き、本来の意味での「無頼」を貫いた、その経緯も詳しく取り上げられている。
溝口氏は、まず自分が取り組む競技を「やり投げ」と捉えることをやめた。「やり投げ」と考えると、従来の「やり投げ」の常識にとらわれてしまう。例えば、トップ選手のフォームのいい所や自分に合いそうなことを取り入れるなど、影響を受ける。そこで溝口氏がたどり着いた結論は、この競技は「全長2.6m、重さ800gの細長い物体をより遠くに飛ばす」ということだったという。
そしてその細長い物体をより遠くに飛ばすために、肩は強いもののやり投げ競技者としては比較的小柄である自分に合った投擲(とうてき)スタイルを考えた。当時は、すべての選手が投擲動作に入る前に軽く跳び、着地の反動を利用して投げていたが、そのスタイルに決別し、世界でただ1人、跳ばないやり投げを実践してみせたのだ。
また、欧米選手に比べて劣るパワーを手にするため、練習はほぼウエート・トレーニングに絞るという決断もする。そのトレーニングも1日に10時間以上に及んだという。溝口氏は現役引退後、ハンマー投げの室伏広治氏のコーチをボランティアで引き受けているが、当時の練習を室伏氏は「自分も厳しい練習をこなしているほうだと思っていたが、溝口さんは、誇張でもなんでもなく、私の10倍以上の練習内容をこなしていた」と振り返る。
人は、自分が選んだ道にそれほどまでに誠実に向き合い、ひたむきに進めるものなのか。その姿勢には感動すら覚える。ビジネスという闘いに臨む私たちもその誠実さ、ひたむきさを見習いたいものだ。
そして、もう1つ、すぐにでも取り入れたいのが、常識を疑い自由な発想で自らのスタイルを完成させていく柔軟さだ。自社の事業、商品、業界の慣例などを一度解体してみることも大事だろう。自社の強みを生かした考えもしなかった新しい展開、新しい販路、新しい強みが見えてくるかもしれない。
そうした試みが、あの日、カリフォルニアの青い空の下、溝口氏がそうであったように、世界の頂点を見せてくれるかもしれない。
執筆=藤本 信治(オフィス・グレン)
ライター。
【T】
アスリートに学ぶビジネス成功への軌跡