
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
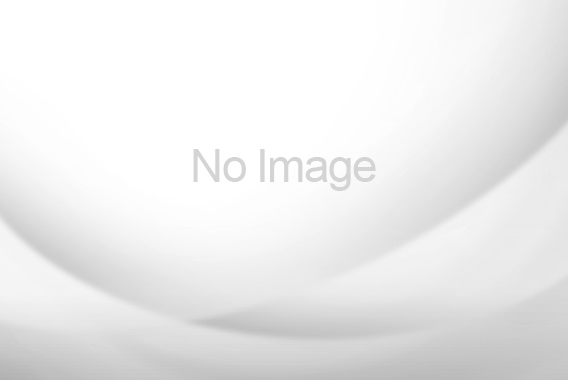 タイトルの“英雄”という表現には、多少違和感を覚える方もいるかもしれない。中野浩一氏は1975年に競輪選手としてデビューし、いきなり18連勝。1980年には日本のプロスポーツ界で初の年間賞金1億円突破を実現するなど、トップ選手として競輪史上に残る活躍をしてきたことは広く知られている。つまり、名選手であったことは間違いない。それをさらに“英雄”と持ち上げるのはなぜなのか。
タイトルの“英雄”という表現には、多少違和感を覚える方もいるかもしれない。中野浩一氏は1975年に競輪選手としてデビューし、いきなり18連勝。1980年には日本のプロスポーツ界で初の年間賞金1億円突破を実現するなど、トップ選手として競輪史上に残る活躍をしてきたことは広く知られている。つまり、名選手であったことは間違いない。それをさらに“英雄”と持ち上げるのはなぜなのか。
中野氏には、以下のようなエピソードがある。
| ●中野氏がフランスでエールフランス機に搭乗する際にはレッドカーペットが敷かれた。 | |
| ●ヨーロッパで現地の人と話をしていて、相手が中野浩一だと分かった途端、驚きのあまりその人が硬直してしまった。 | |
| ●テレビ局の解説者として世界的に有名な自転車ロードレースのツール・ド・フランスを取材に行った際、関係者の休憩所に中野氏が入っていくと、そこにいた全員が立ち上がり、敬意を表して中野氏に挨拶をした。 | |
| ●同じく中野氏がツール・ド・フランスの1997年の優勝者に「僕のことを知ってる?」と聞くと、その選手は「あなたを知らない自転車競技の選手がいるのですか?」と返したという。 |
他にも残されたいくつものエピソードが、日本に比べてはるかに自転車競技の人気が高いヨーロッパにおいて、中野氏が特別な存在として多くの人の尊敬を集めていることを伝えている。
中野氏の存在をレジェンドの領域にまで高めたのは、世界選手権自転車競技大会(以下:世界選手権)個人スプリントにおいて、1977年から1986年まで実に10連覇という前人未到の偉業を成し遂げたことによる。
初開催が1893年という世界選手権は、ヨーロッパではサッカーのワールドカップと肩を並べるほどの人気だという。極東から来た青年がその歴史ある大会に参戦し、名だたる名選手を次々と撃破していく姿を見たヨーロッパの人たちはまずブーイングで応え、驚き、そしてその圧倒的な実力を前にして喝采を送るようになったのだ。
競輪選手の収入の大半を占めるのはレースの賞金だ。世界選手権に出場するようになり、1年のうち2カ月を海外でのレースに費やすようになった中野氏は、収入がかなり減ったという。それでも世界に挑戦しようと思った背景を『気分はいつもブッチギリ』(中野浩一 著/日本文芸社)で次のように述べている。
“はじめて世界選手権に出た頃も、ボクは期待を一身に浴びましたね。お金こそかかっていないけれど、競輪界全体の動きが、ボクの世界選手権制覇によって、一挙に、暗いマイナーのスポーツイメージから脱却できる、といった雰囲気があった。”
世界選手権で勝てば自身の名誉になるのはもちろんだが、マイナーなイメージが強かった競輪のイメージアップにつながる。そのような思いが鬼の形相でペダルを踏む中野氏の背中を押したのだろう。
「力強さは、使命感を持つところから生まれる」。経営の神様とうたわれた松下幸之助氏の言葉が思い出される。
自社にそのような使命感を持ったメンバーがいれば、どれだけ頼もしいことだろう。使命感を持ち、自分から積極的に動く人材を育成するためにも、会社の事業の目的や存在意義、それが社会にもたらす影響、そうした会社の一員として仕事をする意味を普段から共有することの大切さに改めて目を向けたい。
中野氏の世界での活躍が評価され、競輪は「ケイリン」として2000年のシドニーオリンピックからオリンピック正式種目に採用された。そして2020年の東京オリンピックには、日本発祥の「ケイリン」が誕生の地に凱旋を果たすのだ。遅まきながらその功労者である中野浩一氏に心からの賛辞を送りたい。
執筆=藤本 信治(オフィス・グレン)
ライター。
【T】
アスリートに学ぶビジネス成功への軌跡