
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
最近のビジネスにおいては、新たなニーズを掘り起こし、商品を次々に開発して市場に投入していかないとなかなか生き残れません。製菓業界も例外ではなく、新たな味、新たな食材の組み合わせ、新たなパッケージで新商品が次々に開発され店頭に並び、そして日々淘汰されています。そんな中、発売開始から120年以上たっても店頭に並び続けるお菓子があります。森永製菓のミルクキャラメルの発売は1899年。人々に愛され続けている、製菓業界の超ロングセラーです。
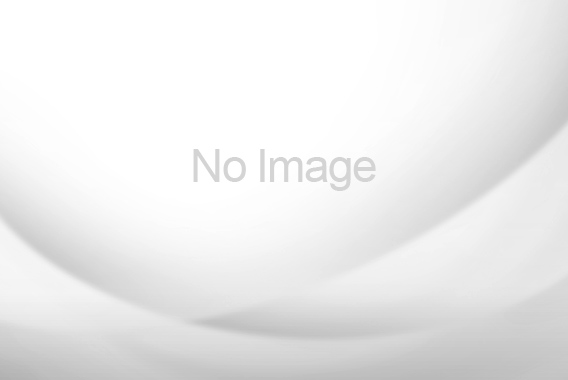
森永製菓の創業者・森永太一郎は、もともとは陶器を扱う商人でした。ある時、陶器を販売するために渡米し、そこで西洋菓子に出合いました。太一郎は一度帰国しますが、西洋菓子の製造法を身に付けるために再渡米。そして11年にわたる滞米の後に帰国し、1899年、東京・赤坂に森永西洋菓子製造所を設立しました。
製造所でまず製造・販売したのは、マシュマロ、チョコレートクリーム、そしてミルクキャラメルでした。しかし、ミルクキャラメルは外国人や海外からの帰国者には好評を得たものの、当初、日本人にはなかなか受け入れられませんでした。キャラメルの製造には、バターやミルクを多く使います。日本のお菓子に慣れていた舌にとって、キャラメルは味が濃過ぎたのです。
また、品質についても問題がありました。一般的に太一郎が修行した米国よりも日本は気候が多湿です。原材料も、日本で手に入るものと米国で使われているものとでは品質が異なります。そうしたこともあり、キャラメルがすぐに溶けてきたり、糖化して口当たりがざらざらになったりと品質が変わってしまったのです。
味以外に包装にも問題を抱えていました。衛生上の観点から、当初ミルクキャラメルは1粒ずつワックスペーパーで包み、1粒5厘でバラ売りしていました。しかし、バラ売りしていては、大量販売は見込めません。ここから品質、そして包装の改良が始まりました。
まず、品質に関しては、原料を煮詰める温度や配合の割合などを見直し、溶けにくく、日本人の好みに合う味をめざし、苦労の末、改善に成功します。そして、包装についてはワックスペーパーで包むやり方は変えずにバラ売りではなく、持ち運びのできる容器に入れて販売する形を採用することにしました。
こうして1908年、ブリキの小さな缶に入ったミルクキャラメルが発売になりました。しかし、ブリキ缶は品質の維持には効果があるものの、コストがかかり、値段が高くなってしまいました。10粒入りで10銭と1粒当たりではバラ売りの倍の値段にしなくてはならなくなったこともあり、人気を博すまでには至りませんでした。
そこで太一郎は、ブリキ缶に代わる容器の研究を進めます。材質、形、品質の安定度、コストなど、さまざまな観点から最適な容器を探し求めました。そうしてできたのが、現在でも販売されている包装の形、箱の上下に差し込み式のフタが付いた紙サックの箱です。この形だと密封度が高まって品質が守れるとともに、紙を材料にするためコストを抑えることができたのです。
こうして、ポケットサイズの紙サック入りキャラメルが完成しました。1914年に東京・上野公園で開催された第5回大正博覧会でテスト販売を実施。値段は、20粒入りで10銭です。つまり、博覧会が開幕した3月20日が、私たちがよく知っている黄色の紙の箱に入った森永ミルクキャラメルがデビューした日ということになります。販売を開始すると、ミルクキャラメルは博覧会の土産として大人気となり、前代未聞の売り上げを記録しました。
この好評を受け、一般販売を決定。品質保持の観点から商品の回転を早めることが大事と考えて、新聞などでの広告宣伝を大々的に打ちました。その結果、生産が追いつかないほどの大ヒット商品となりました。その後、当初は手作業で行っていた包装と製造の両過程に機械を導入して大量生産の体制を整え、ミルクキャラメルは全国に広く行き渡ることになりました。
ミルクキャラメルが成功した要因としては、ミルク、バターが日本で普及し、その味に日本人が慣れてきたことが指摘されています。またその栄養価が認められたことも一因と思われますし、日本では一般的でなかったミルクキャラメルという菓子を売り出した先見性もその1つでしょう。
しかし、経緯を振り返ると「受け入れられるための工夫」に力を入れたことが大きな要因であったことも分かります。最初、1899年にミルクキャラメルを発売した時、日本人からはほとんど相手にされませんでした。買い求めたのは、ほとんど海外からの帰国者のみ。しかし、そこから太一郎は工夫を重ね、味を日本人に合うように改良し、バラ売りからブリキ缶入り、そして持ち運びのしやすい紙サックの箱へと入れ物にも改良を加えました。こうした一連の工夫がベースとなり、第5回大正博覧会での大ブレークにつながったのです。
私たちは、ミルクキャラメルといえば現在の形であることが当たり前だと思っているため、その形にたどり着く苦労の積み重ねに思いが及びません。しかし、1899年に売り出しても評判を呼ばなかった時点で、「キャラメルは日本人には合わない」と切り捨てて、別の西洋菓子に注力するという選択もあり得たのです。そうした決断を太一郎がしていたら私たちが知っているミルクキャラメルはなかったかもしれません。
選択と集中、そしてスピードも求められる現代では難しいことではありますが、発売しても反応が芳しくない商品でも改良すれば売れるようになるポテンシャルがあるケースがあります。こうした見極めが非常に重要なケースがあることを、ミルクキャラメルの事例は語っているのかもしれません。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所