
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
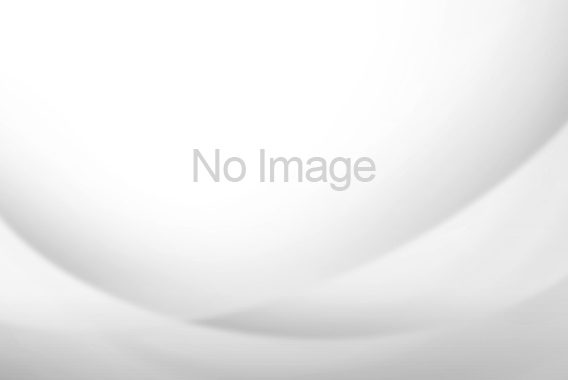
各地が続々と梅雨入りし、夏も間近。汗ばむ日も多くなり、氷菓子がよりおいしく感じられる季節の到来です。暑さを感じると手を伸ばしたくなるのが、赤城乳業の「ガリガリ君」。ガリガリ君は1981年に発売されて以来、40年以上にわたって愛されてきた氷菓のロングセラーです。
赤城乳業の前身である広瀬屋商店は、埼玉県深谷市で1931年に創業。天然氷を扱う商店として事業をスタートしました。戦後の1949年に冷菓の製造を始め、1960年に赤城乳業に商号を変更します。乳製品は製造していなかったにもかかわらず「乳業」と付けたのは、冷菓業界に多かった「〜乳業」という名前の大手諸企業に追い付くという決意の表れでした。
そして、1964年にカップタイプの氷菓子「赤城しぐれ」を発売します。当時、かき氷などの氷菓子は大衆食堂などで皿に盛られたものを食べるのが主流で、プラスチック製のカップに入れたものは一般的ではありませんでした。「赤城しぐれ」は駄菓子屋などで手に入り、カップで食べられる手軽さが人気を呼び、年間4000万個を売り上げる大ヒット商品になります。
赤城乳業は新工場を設立するなど、赤城しぐれの売り上げを軸に業容を拡大していきましたが、1970年代になるとその売り上げに陰りが見えるようになります。2度のオイルショックの影響でカップの価格が高騰したことに加え、大手アイスメーカーがカップ氷菓子市場に参入し、厳しい価格競争にさらされたのです。
また、1970年代半ば頃からコンビニエンスストアが日本でも普及し始め、販売環境も変化します。店舗数が拡大するコンビニ向けの商品で大手メーカーが市場シェアを伸ばす一方、「赤城しぐれ」の中心的な販売チャネルだった駄菓子屋は店舗数を減らし、赤城乳業は苦境に立たされます。
赤城しぐれに匹敵するようなヒット商品を作ろう――。会社の新たな柱となる商品の開発が始まりました。
新商品の主なターゲットとなるのはコンビニのユーザーなので、その層に向けた新しい商品形態が必要になります。コンビニのユーザーは、買ってすぐ、歩きながらでも、子どもなら遊びながらでも氷菓を食べます。そのニーズに合わせ、「赤城しぐれ」はかき氷をカップに入れる発想でしたが、かき氷に棒を刺して片手でも食べられるバータイプを考案しました。
ただ、そのままだと棒がすぐに抜けてしまいます。そこで、かき氷をアイスキャンディーでコーティングし、抜けにくくしました。実用面から生まれたアイデアでしたが、結果として、商品に独特の食感を加えることにもなりました。
「赤城しぐれ」のフレーバーは、いちご、白みつ、あずきでしたが、新商品ではフレーバーも一新します。採用したのは、飲料の売れ筋であるソーダ、グレープフルーツ、コーラの3種類。ソーダとグレープフルーツは特別な着色をしないと色が似ているため、差別化を図りソーダ味は子どもが外で遊ぶときの空の色をイメージした水色にしました。これが、新商品の強い個性の一つとなります。
氷菓を食べるときの「ガリガリ」という音に「君」を付けた新商品「ガリガリ君」は、1981年に発売。コンビニでの取り扱いに重点を置いた「ガリガリ君」はコンビニの店舗数拡大とともに順調に売り上げを伸ばし、売上本数は10年で3倍、年間1000万本に達しました。
「ガリガリ君」の躍進は、これにとどまりません。2000年には売上本数が年間1億本を突破。現在は年間4億本を売り上げるメガヒット商品になっています。
「ガリガリ君」がこれほどまでのロングセラーになったのには、親しみやすいネーミング、インパクトのあるパッケージ、飽きのこない味、手軽な価格などさまざまな要因があると思われますが、見逃せないのが多様なフレーバーです。
「ガリガリ君」は発売当初からの定番であるソーダ、グレープフルーツ、コーラに加えて、次々と新しいフレーバーの商品を発表。これまでに発売したフレーバーは150種類を超えています。2012年に発売されたコーンポタージュ味の「ガリガリ君リッチ コーンポタージュ」はその意外性で評判を呼び、生産が追い付かずに販売中止になるなど、大きな話題となりました。
数十年といった期間で売れ続けるロングセラーでは、発売当初からの定番に派生商品を加えていき、定番を中心とした商品群を構成することは珍しくありません。しかし、同じブランドでここまで多くの種類の商品をそろえた例は決して多くありません。
新しい商品を次々と開発するには、社内で頻繁に商品企画が上がる必要があります。これまでにない新鮮なアイデアの商品企画が出るよう、赤城乳業は特に若手社員の声を拾うように気を配っています。
そのキーワードが「言える化」です。若手も意見を言える風通しのいい風土というのは、多くの企業が意識していることでしょう。しかし、若手社員が役員にダメ出しできる、社長に反対意見を言えるような会社はそれほど多くはないはずです。赤城乳業は「仕組み」と「場」を整え、年齢・役職に関係なく意見が言えるようにしています。
また、ユニークなのが、会社に大きな損失をもたらす商品に携わった社員にペナルティーを課すペナルティー制度です。これは一見損失をもたらした社員に対する罰のように見えますが、性質が異なります。ペナルティーは注意から1万円ほどの罰金だけで、それ以上責任を問われることも、人事評価に影響することもありません。大きな失敗をしてもこれだけのペナルティーで終わり、社内でそれ以上とがめられることがない仕組みが、チャレンジを促します。もちろん、赤城乳業は単に若手の新奇なアイデアを見境なく取り上げているわけではありません。企画の可否は社内で厳しく判断されています。
声を拾うのは、社内の若手に限りません。実は、「ガリガリ君」のパッケージのイラストは1981年の発売当初のものから大きく変わっています。1990年代に売り上げが伸び悩み始め、市場調査を行った結果、当初のイラストが「歯茎が汚い」「田舎臭い」という声が上がり、特に女性からは不評だったことが分かったのです。そこで、2000年にイラストをリニューアルしました。
「時代に合ったイラストを」という方向性を軸に当時ゲームやアニメではやり始めていた3Dのテイストを取り入れて、社外のアートディレクターによってリニューアルされたのが、現在のパッケージに印刷されている「ガリガリ君」なのです。
経営陣、マネジメント層は経営に関する判断を下す役割と責任を負っていますが、その発想には限界がありますし、自分たちでは気付いていない視点や、自分たちとは異なる年齢層が感じている時代感覚などが必ずあるものです。
そうしたことを自覚し、若手社員やユーザー、外部の関係者の声に耳を傾け、柔軟に取り入れる企業風土が、「ガリガリ君」をロングセラーにしている大きな要因の一つだと思われます。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所