
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
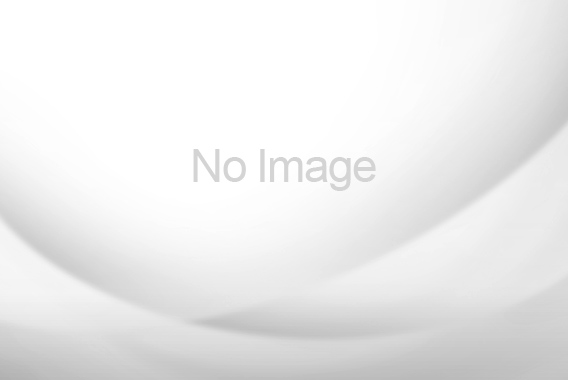
「『サッポロ一番』は何味が好き?」。雑談にこんな話題が出たりするほどおなじみなのが、サンヨー食品の「サッポロ一番」です。第1弾「サッポロ一番 しょうゆ味」が発売されたのは1966年。50年以上にわたって愛され続けている、即席麺のロングセラーです。
1953年、酒類販売業を営んでいた井田文夫と長男の毅が、事業の多角化のため群馬県前橋市に「富士製麺株式会社」を設立したのが、サンヨー食品の歩みの始まりです。富士製麺の麺は品質が高いと評判になりましたが、乾麺の世界は少量生産だったため、毅は事業拡大のきっかけを模索していました。
そんな折、毅はお湯をかけるだけで食べられる即席麺が関西でブームになっていると聞きつけます。サンシー殖産(現・日清食品ホールディングス)の「チキンラーメン」です。即席麺に将来の可能性を見いだした毅は1961年、社名を「サンヨー食品株式会社」に改め、即席麺の製造を本格的に開始します。
1963年に発売した「ピヨピヨラーメン」は会社として初めて打ったテレビCMの影響もあり認知度が一気に高まりました。翌年には「長崎タンメン」を発売します。即席麺といえばしょうゆ味一色だったところ、塩味の「長崎タンメン」は新鮮に受け止められ、生産が間に合わないほどの売れ行きでした。
小売店の棚からすぐなくなり「幻のラーメン」とまでいわれた「長崎タンメン」を見て他社も追随し、塩味の即席麺が大量に出回るようになりました。中には名前もパッケージも「長崎タンメン」とほとんど同じようなものがあり、訴訟を起こさざるを得ないほどでした。
「長崎タンメン」はあまりにも多くの類似品が出回ったため、他社がまねできないオリジナルのブランドを育てる必要性を毅は痛感します。そこで頭に浮かんだのが、札幌出張の度に口にしていたしょうゆラーメンでした。おいしくて現地の若者にも人気がある札幌のしょうゆラーメンの味を即席麺にしたら、ヒットするのではないか−−。こう考えた毅は、すぐさま開発にとりかかりました。
他社のしょうゆ味の即席麺と差異化を図るため、毅は徹底的に味にこだわりました。スープは鶏ガラをベースとし、ニンニク、ショウガなどの香味野菜を加えました。さらにコショウをベースとしたトッピング用スパイスの小袋を添えます。当時の即席麺のパッケージは湿気を吸って麺の品質が落ちるものもありましたが、味が劣化しないようにパッケージのフィルムも厳選しました。
こうして1966年に発売した「サッポロ一番 しょうゆ味」はヒットを記録し、小売店から注文が殺到します。
しかし、毅はこの成功に飽き足りていませんでした。「サッポロ一番」ブランド定着のため、次は味噌味に目をつけます。今でこそ味噌ラーメンは一般的ですが、当時、北海道以外では味噌ラーメンはなじみが薄く、地域の名物ラーメンという位置付けでした。味噌味の即席麺もほとんどありません。味噌味で成功すれば、「サッポロ一番」ブランドを確立できます。
札幌の名店の味をヒントに、毅は開発室のメンバーと味噌味の即席麺づくりにとりかかります。ただ、それまでにない味噌味の即席麺の実現は容易ではありませんでした。試行錯誤を繰り返し、100種類以上ものパターンを試します。
こうしてたどり着いたのが、赤味噌や白味噌など7種類の味噌に野菜エキスをブレンドしたスープ。トッピング用には七味唐辛子の小袋をつけて、味のアクセントにします。「サッポロ一番 みそラーメン」は1968年に発売後すぐ大ヒット商品になり、日本中のラーメン店が味噌ラーメンをメニューに加えるきっかけになったともいわれています。
そして1971年には「サッポロ一番 塩らーめん」を発売します。毅がめざした通り、「サッポロ一番」は袋入り即席麺の代表的なブランドに成長しました。
「サッポロ一番」がロングセラーになった要因には、もちろん味があります。こまやかな味のこだわりはスープだけでなく、麺にも及んでいます。スープとの一体感を持たせるため、「しょうゆ味」の麺にはしょうゆ、「みそラーメン」の麺には味噌、「塩らーめん」の麺には山芋の粉が練り込まれています。それだけではありません。スープとの相性を考え、「しょうゆ味」は四角、「みそラーメン」は楕円、「塩らーめん」は円形と、麺の断面の形をそれぞれ変えています。
興味深い話があります。「サッポロ一番」は麺にもスープにもこだわって作られていますが、ただおいしさを追求したわけではありません。飽きがこないよう、おいしくし過ぎないようにしたというのです。札幌ラーメンの味と「サッポロ一番」の味は違うのではないかと聞かれた毅は、「当たり前だ。あんなにおいしくてはたまにしか食べたくならないだろう」と答えたというエピソードが残っています。
一度きりの利用では、ロングセラーにはなりません。何度もリピートして使ってもらうのが、ロングセラーの条件です。ゲストが非日常的な体験を楽しむテーマパークなどでは、想像を超える感動がリピートのために必要かもしれません。しかし、日常的に利用する食品はそれとは方向性が異なり、強い感動ではなく、飽きのこない満足感の提供がロングセラーにつながると「サッポロ一番」は示唆しています。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所