
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
外箱に牛のマークが印刷された「牛乳石鹸」を、子どもの頃から使い続けている人も少なくないのではないでしょうか。牛乳石鹸共進社の代表的な商品である「カウブランド赤箱」(以下:「赤箱」)や「カウブランド青箱」(以下:「青箱」)を目にした経験は誰も持っていると思います。「赤箱」は発売から90年以上、戦後に発売された「青箱」も70年以上愛され続けている、せっけんのロングセラー商品です。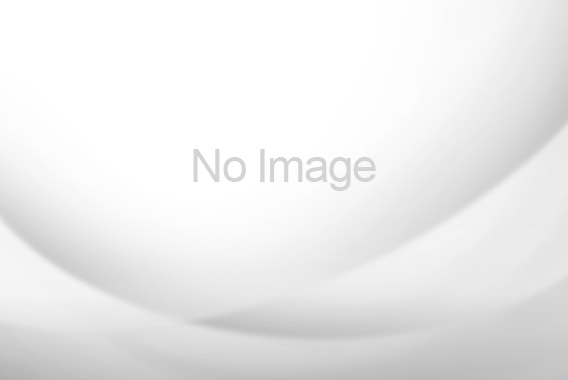
牛乳石鹸共進社の創業は、1909年。宮崎奈良次郎が大阪で共進舎石鹸製造所を立ち上げたのが始まりです。当時はせっけんが日本の輸出産業に育っており、大阪はせっけん製造の中心地でした。その頃のせっけんビジネスでは問屋の力が強く、多くのせっけん業者が問屋から生産を請け負っていました。
奈良次郎も、問屋の商標による生産を請け負っていました。今でいうOEM(Original Equipment Manufacturer)です。その中の1つに、佐藤貞次商店の牛乳石鹸がありました。そして、奈良次郎は1928年、佐藤貞次商店から牛乳石鹸の商標を譲り受け、自社ブランドとしての製造販売をスタートさせます。これが「赤箱」の始まりです。
太平洋戦争で工場は全焼してしまいますが、戦後、社員一丸で工場再建に乗り出し、生産を再開。1949年には「青箱」の販売を始めました。スクワランといううるおい成分を配合した「赤箱」がしっとりとした洗い上がりなのに対し、「青箱」はさっぱりと洗い上がるせっけんです。「青箱」は特に関東エリアで人気商品となり、今でも関西では「赤箱」、関東では「青箱」の販売数が多くなっています。
そして、牛乳石鹸の知名度を大きく上げることに貢献したのがラジオとテレビの広告です。1951年に始まった民間ラジオ放送で、共進舎は「歌謡50年史」という番組のスポンサーになりました。牛の鳴き声で始まるこの番組は人気番組になり、全国に牛乳石鹸の名を広めます。
さらに、1961年からはテレビの「シャボン玉ホリデー」のスポンサーになりました。民放初のカラーミュージカルとして大ヒットしたこの番組は共進舎の一社提供だったため、牛乳石鹸が強く印象付けられることになります。この番組は11年続く長寿番組となり、牛乳石鹸を、日本人なら誰もが知っているブランドに押し上げました。
1967年に牛乳石鹸共進社株式会社に商号変更。以降、日本の経済成長を背景に売り上げを伸ばしていきました。しかし、そんな順風な経営環境にも変化が訪れます。生活習慣の変化に伴ってせっけんを取り巻く環境も変わり、90年代以降はボディーソープなどに押されて、固形せっけん市場は縮小傾向となってしまいました。そんな中、牛乳石鹸共進社は多様な商品に手を広げたことで業績が悪化してしまいました。
そこで、当時の宮崎仁之社長(現・会長)は、創業製品であるせっけんとボディーソープに経営資源を集中し、せっけんで日本一をめざす決断を下します。そうした苦境でも守り続けたのが牛乳石鹸伝統の製法でした。牛乳石鹸は「鹸化塩析法」と呼ばれる釜炊き製法で作られています。一般的に行われている「連続中和法」だと40分間に約40万個のせっけんを作れるのですが、同じ数を作るのに5日間かかるという非常に手間のかかる製法です。その代わり、出来上がったせっけんには天然保湿成分が多く含まれ、肌に優しい洗い上がりになります。
せっけんへの原点回帰により、業績は回復。固形せっけんの国内シェアで1位になるなど、「せっけんで日本一」を現実のものとしました。そしてここ数年、牛乳石鹸はレトロコスメブームの代表的な存在となり、女性たちの間で人気を集めています。新しいブランドが次々と新商品を発表するコスメティックスの中で昭和から続くレトロコスメが注目を集めており、「肌に優しい」「洗顔せっけんとしてコストパフォーマンスが高い」と牛乳石鹸が人気なのです。
ロングセラーとなった商品でも、いつまでも良好な売れ行きを保てるとは限りません。商品を取り巻く環境の変化、社会状況の変化などによって、売れ行きに陰りが出る局面が訪れます。そうしたとき、商品に手を加える企業努力は大切です。しかし、そんな場合でも、商品の核となる部分は守り続ける方が合う企業もあります。同社の場合、守るべきものや守るべきことを明確にしたことで、再上昇を果たしたわけです。
牛乳石鹸は、釜炊き製法による肌に優しい、しっとりとした洗い上がりが特徴で、それが商品の核です。ですから、経営が危機を迎えたときにも、手間と時間がかかる(=コストがかかる)この製法を変えてコスト削減を図るような道は選ばず、当時伸びていたヘアケア製品などからせっけんに経営資源を集中して、商品の核となる部分は守り続けました。
そのことが商品の信用を高めることにつながり、再評価に道を開いたのではないでしょうか。ロングセラー商品がなぜ、長期間支持され続けているのか、企業自身がそれを認識し、大切にしなければなりません。それを怠ったとき、ロングセラー商品は寿命を迎えます。変わらない価値を持ち続けること。これがロングセラーをロングセラーたらしめる秘訣の1つなのでしょう。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所