
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
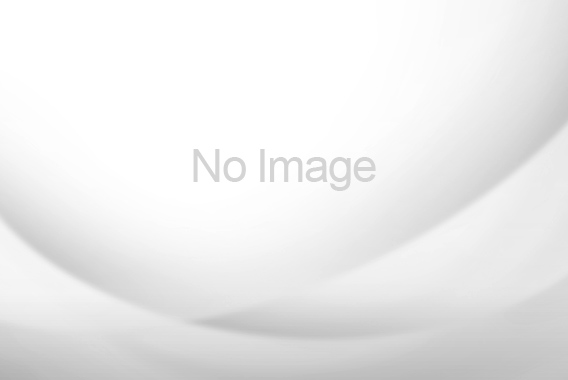
おやつに、ビールのつまみにと大活躍なのがカルビーの「かっぱえびせん」。豊かなエビの風味で、テレビCMのフレーズさながら、食べ始めると「やめられな」くなってしまうこともあるのではないでしょうか。かっぱえびせんは1964年に発売され、50年以上にわたって愛され続けているスナック菓子のロングセラーです。
かっぱえびせんが世に出るまでには、前史があります。カルビー創業者である松尾孝は、戦前から食料の生産に携わっていました。そして、戦争が終わると団子やキャラメルなどの製造を始めます。孝の菓子は好評を博しましたが、キャラメルなどの甘い菓子は競争が激しく、やがて経営難に。1955年、孝が再起を期して立ち上げたのがカルビー製菓でした。社名は、カルシウムの「カル」とビタミンB1の「ビー」を組み合わせたものです。
社名にも表れているように、「健康にいい、栄養のあるお菓子をつくる」が孝のモットーでした。当時は、まだ戦後の食糧難が続いている時代。そんな中、栄養のある菓子で人々のおなかを満たしたいという願いを抱えていたのです。
栄養があり、腹も膨れる菓子といえば、米を原料とするおかきが挙げられます。しかし、当時は戦中に定められた食糧管理法が続いており、米は政府の統制下にありました。入手が難しく、値段も高くなっています。手に入れておかきをつくったとしても、値段を高くせざるを得ません。
自身のモットーにのっとりながら、広く人々の手に渡る商品が何とかできないものか――。そこで目をつけたのが小麦でした。米国産の小麦は食糧管理法の統制から外れており、自由に手に入れることができました。また、たんぱく質を主としながらさまざまなビタミンを含んでおり、栄養価もあります。小麦を原料としたおかきへの挑戦が始まりました。
当時、小麦粉からおかきをつくる製造法はなく、試行錯誤を繰り返し、ようやく小麦あられの製造に成功。1955年、「かっぱあられ」を発売します。
当時、週刊誌に連載されていた「かっぱ天国」という漫画が人気を集めていました。孝はこの人気にあやかろうと、「かっぱ天国」の作者・清水崑にパッケージのイラストを依頼しました。かっぱあられのパッケージにかっぱのイラストが入り、名前にかっぱが付いているのも、これが由来です。そして、このかっぱの名前が後のかっぱえびせんに受け継がれることになります。
満を持して送り出したかっぱあられですが、大ヒットというわけには行きませんでした。「鯛の浜焼きあられ」「いかあられ」「かっぱあられ味大将」「かっぱの一番槍」など小麦あられのシリーズ商品を次々に開発しますが、どれも会社の看板商品にまでは育ちません。
そんな中、孝が思い出したのが子どもの頃に食べていたエビです。孝は「エビ獲り名人」とあだ名がつくほど川エビを捕るのがうまく、持ち帰った川エビで母親がつくってくれるかき揚げが大好物でした。エビ味のあられをつくれば、喜ばれるのではないか――。新たな試行錯誤が始まりました。
小エビをゆでたり、粉末にしたものを生地に混ぜたりしましたが、めざすエビのおいしさが感じられません。そこで小エビの頭から尾までを殻ごとすりつぶし、小麦粉の生地に混ぜるようにしました。すると、エビの風味がしっかりとあられから感じ取れるようになりました。
こうして完成したかっぱえびせんは、1964年に発売を開始。手軽に食べられるエビ味のスナック菓子は評判となり、会社で一番のヒット商品になります。そして、「やめられない、とまらない」のフレーズのテレビCMで火がつき、国民的な菓子へと育っていきました。そして、その後売り出した「ポテトチップス」や「じゃがりこ」などと並んで、かっぱえびせんは今でもカルビーの主力商品の1つであり続けています。
かっぱあられに続いて「鯛の浜焼きあられ」などシリーズ商品をいくつも出したという話をしましたが、かっぱえびせんは実にシリーズ27番目の商品でした。26種類の商品を出し、ようやくたどり着いたのがかっぱえびせんだったのです。そして大ヒット商品かっぱえびせんは、シリーズ最後の商品になりました。この後、小麦あられのシリーズはかっぱえびせんに集約していきました。
その後、かっぱえびせんは、味付けを変えた期間限定商品を販売したり、乳幼児用の「1才からのかっぱえびせん」を発売したりするなどバリエーションを増やし、同社の基幹商品という位置付けを不動のものとしています。
ロングセラー商品は、まず大ヒット商品となり、それを磨き続けることによって、長い間愛されるようになって誕生したケースが珍しくありません。かっぱえびせんもそうしたプロセスを経ていますが、まずは、大ヒットに至るまでの執念をぜひ参考にしたいところです。さまざまな商品を開発した中で、ようやく見つけ出した“原石”に力を集中して、大ヒットに結び付けたのは見事な経営手腕といえるでしょう。
経営の手法として、特定の領域を選び、そこに資源を集中させる「選択と集中」があります。資源を集中させるべき領域がある場合にはこれは有効ですが、実際には、集中させるべき領域がまだないケースも少なくありません。その場合には、選択の前にまずは集中すべき分野を見つけることに全力を注ぎ“原石”を発掘する。そして、“原石”を磨き続けることが安定した経営につながる。そうしたプロセスの有効性を、かっぱえびせんから学べるのではないでしょうか。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所