
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
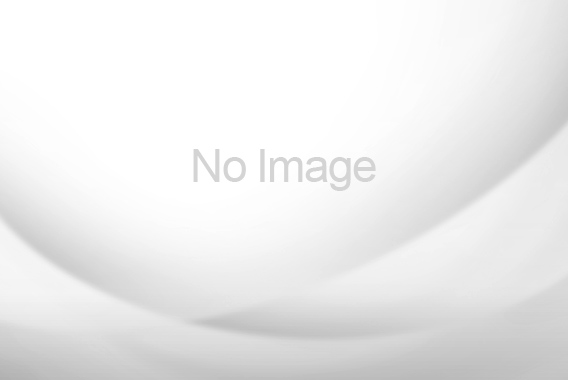
コンビニエンスストアや自動販売機ではさまざまな種類の飲料が売られていますが、弁当のお供に、外での一服に、気持ちが落ち着くのが日本茶。中でも定番になっているのが、伊藤園の「お~いお茶」です。「お~いお茶」は1989年に発売され、30年以上にわたって愛され続けている緑茶のロングセラーです。
伊藤園の前身であるフロンティア製茶が静岡県静岡市に設立されたのは、1966年のこと。それまで茶葉は量り売りされるものでしたが、フロンティア製茶は茶葉を包装し、パック茶として販売しました。量り売りだと特別な売り場が必要ですが、包装されたパック茶だとスーパーなどで他の食品と同じように扱うことができます。
この戦略が功を奏し、フロンティア製茶は1968年に茶業界で売上高トップの企業となりました。量り売りもパック茶も、売るのは同じ日本茶の茶葉です。しかし、提供形態を変えたことで消費者に広く受け入れられるようになりました。この「提供形態を変える」ということが、後の「お~いお茶」にまでつながっていくのです。
フロンティア製茶は1969年に称号を伊藤園とし、1974年に静岡相良工場を建設。従来の販売会社から日本茶メーカーへと、本格的に移行しました。
メーカーである伊藤園の課題となったのは、日本茶の新しい提供形態への挑戦です。それまで、日本人が飲むものといえば日本茶が一般的でしたが、経済成長とそれに伴うライフスタイルの変化により、さまざまな種類の飲料が飲まれるようになりました。
それに拍車をかけたのが、缶入り飲料の普及です。日本で初めて缶入り飲料が発売されたのは1954年で、明治製菓が発売した缶入りオレンジジュースが始まりです。そして1969年にUCC上島珈琲が世界初の缶コーヒーを発売し、万博を契機に大ブームとなったのは、本連載の第8回でご紹介した通りです。
そして、1975年頃から缶入り飲料の自販機が全国的に普及しはじめ、缶で飲料を飲むのが当たり前という時代になりました。急須で日本茶を淹れるという習慣が生活から徐々に失われていき、日本茶の売り上げは頭打ちになりました。
そこで伊藤園が着手したのが、缶入り緑茶の開発です。ただ、缶入り緑茶を作るのは容易ではありませんでした。缶の中に入る微量の酸素により、緑茶が褐色に変色してしまうのです。また、加熱殺菌処理によって香りが変質し、不快臭を発することも分かりました。
これに対して、缶にふたを付ける直前に窒素ガスを噴射して酸素を追い出す特殊な技術を考案。併せて茶葉のブレンド、抽出時間などを細かく調整することにより、香りの問題も解決しました。
そして、約10年の開発期間を経て1985年に世界初の缶入り緑茶「缶入り煎茶」が発売になりました。この「缶入り煎茶」の名前を変えて1989年に誕生したのが、「お~いお茶」です。
「お~いお茶」という名前は、伊藤園が1970年代から茶葉のテレビCMで使っていたフレーズから取ったもの。商品名を、堅い印象で若い世代では読めない人もいるような「煎茶」から、読みやすく親しみやすい「お~いお茶」とし、缶の色も濃い緑から、古来水筒として用いられてきた竹をイメージした明るい緑に変えたことで、広く受け入れられるようになりました。それまで家で飲むのが主流だった緑茶が外で気軽に飲めるようになり、緑茶飲料の市場が一気に広がります。
しかし、飲料の容器は新たな時代に入りつつありました。ペットボトルの登場です。日本でペットボトルは1977年にしょうゆの容器として使われたのが最初で、1982年に食品衛生法が改正されて清涼飲料用にペットボトルの使用が認められて以降、炭酸飲料などに使われるようになり、急速に広まっていました。
緑茶にもペットボトルの時代が来ると読んだ伊藤園は、今度はペットボトル入り緑茶の開発に着手。緑茶の成分が沈殿してオリとなって底にたまる問題を、マイクロフィルターでろ過することで解決。1996年、世界初のペットボトル入り緑茶「お~いお茶 500ml」を発売します。
さらに2000年には、冬場に温められるホット対応ペットボトルをいち早く開発し「お~いお茶 ホットPET」を発売。このように、進化を続ける「お~いお茶」はギネス世界記録に「最大のナチュラルヘルシーRTD緑茶飲料(最新年間売り上げ)」販売実績世界一として2018年から3年連続で認定されるなど、緑茶飲料を代表するブランドであり続けています。
こうして流れを振り返ってみると、量り売りされるものだった茶葉を包装してパック茶にし、急須で淹れるものだった緑茶を缶入り緑茶にし、さらにペットボトル入り緑茶にして、と、販売形態を積極的にアップデートしてきたことが分かります。提供するものは緑茶のまま変わっていませんが、時代を先取りして販売する形を変えることで「お~いお茶」はトップブランドの地位を築きました。
私たちは、ともすると「何を提供するか」という「中身」に意識を向けがちです。しかし、「どうやってお客さまへ届けるか」を試行錯誤することが大きな価値を生み得ると、「お~いお茶」の事例は教えてくれているように思われます。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所