
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
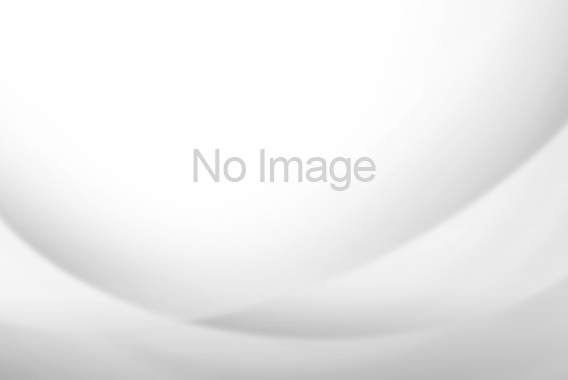
温かいご飯によく合うのが、海苔佃煮の「江戸むらさき」。江戸むらさきがあると、おかずに手を伸ばさなくても箸が進むという人も多いのではないでしょうか。「ごはんですよ」などの姉妹品でおなじみ、桃屋の「江戸むらさき」は1950年の発売。70年以上にわたって日本の食卓の友となっているロングセラーです。
桃屋が創業したのは1920年。創業者の小出孝男は上海の商業学校に留学したのち、銀座の高級食品問屋で働いていました。そこで、顧客に食品を届けて非常に喜ばれるという経験をします。「良い食品を届けることは非常に価値があり、意味のあること」と実感した小出は独立し、東京・京橋区南鍛冶町に桃屋商店を開きました。
現在に続く桃屋のロゴマークには桃と矢が描かれていますが、これは上海に留学中、中国では桃が吉兆や長寿のシンボルであることを知った小出が、「吉兆を射る」ようにと願いを込めたものです。
桃屋商店は当初、「野菜みりん漬」や「福神漬」などの漬物を中心に扱っていました。その後白桃缶詰、ビワ缶詰などフルーツの缶詰を売り出すと人気を博し、「盆暮れのフルーツは桃屋」との評判を取るまでになります。
第二次世界大戦中は空襲で工場が全焼するなどの苦難に遭いましたが、空襲をまぬがれた工場を借りて操業を続けました。しかし、1945年に戦争が終わると時代は大きく変わっていきます。
戦中は戦時統制によりアメリカとの貿易は途絶えましたが、終戦により貿易が再開しました。そこで小出は、「フルーツ缶詰は、欧米の食品メーカーの得意とするところ。今後、安いフルーツの缶詰が大量に入ってくるだろう」と予測します。そして、看板商品となっていたフルーツ缶詰から撤退する決断を下します。
外国にはまねできない日本独自の食品を作らなければならない――。そこで小出が目を付けたのが、ノリのつくだ煮でした。
戦後の物不足で砂糖やしょうゆは相変わらず入手しにくい状況にありましたが、「良い食品を届ける」という小出の信念は変わりません。原材料にこだわります。当時はサッカリンなどの人工甘味料を使った食品が多かった中、そうしたものは使いません。使用するノリは、国産の伊勢湾産のアオノリが中心。ノリに付いているごみを、手間をかけて取り除き、本醸造のしょうゆ、砂糖、水あめと一緒に釜に入れ、じっくり煮詰めます。
こうして、1950年に「江戸むらさき」が発売されました。人々が本物の味に飢えている中、さっそうと登場した江戸前の本格派海苔佃煮は人々に大いに受け入れられました。すぐにヒット商品となり、会社の売り上げが倍増します。
戦後の混乱を脱し、1950年代半ばに日本は高度成長期に入りました。人々の生活にも少しずつゆとりが出始め、よりおいしいものを求めるニーズが高まります。そこで、桃屋は1963年に「江戸むらさき特級」を発売しました。かつお節のだしをふんだんに使い、みりんも加えたぜいたくな海苔佃煮でした。
1960年代半ばから1970年代にかけて、日本の経済成長が続きます。暮らしにさらに余裕ができると、子どもに使うお金が増えます。江戸むらさきは主に大人向け商品でしたが、子どもがよりおいしく食べられる江戸むらさきの開発を桃屋は始めました。それまでの江戸むらさきは固形感がある口触りでしたが、子どもが親しめるよう、甘く、トロッとした食感を目指します。
新しい味、食感を求め、製法も一から見直します。昔から一般的なノリのつくだ煮は乾燥した板ノリで作られてきましたが、柔らかい食感の生ノリを使うことにし、機械も一新しました。とろみを付けるには小麦粉や片栗粉のでんぷんが手っ取り早いですが、冷めると固くなる性質があります。冷めてもとろみが失われない食材を求めた結果、熱帯アジアの常緑樹・タマリンドの実に行き着きました。タマリンドの実だと、冷たくなってもとろみが保たれます。
こうして1973年、「ごはんですよ!」が発売になりました。トロッとした食感の新しい江戸むらさきは子どもたちだけでなく大人からも受け入れられ、親しみのあるテレビCMとともに大ヒット商品になります。
その後、時代の移り変わりとともに人々の嗜好も変わっていきますが「お客さまをがっかりさせないため、一度出した味付けは変えない」が会社の哲学。「ごはんですよ」を始めとしたロングセラーとなった江戸むらさきの諸商品は、発売当初の味を守り続けます。時代の変化には、「ごはんですよ!しいたけのり」「梅ぼしのり」など姉妹品の発売で対応しました。大人になってから食べても、子どもの頃に食べた江戸むらさきと同じ味が味わえます。
実は、この姿勢は江戸むらさき以外の桃屋の商品にも共通しています。一度出したら味付けを変える必要がないよう、開発時には徹底的に味にこだわり、必要なだけ時間をかけます。新製品が出ない年があっても、関係ありません。納得できる味になるまで世に出さないため、食べるラー油ブームの先駆けになった「辛そうで辛くない少し辛いラー油」の開発には10年、「麻辣香油」も10年、「トムヤムクンの素」は最初の提案から発売まで15年ほどかかったといいます。
桃屋には、1972年発売の「梅ごのみ」、1975年発売の「キムチの素」など江戸むらさき以外にもロングセラーが多くあります。「花らっきょう」は1920年発売と100年以上のロングセラーです。それも、同じ開発姿勢から生まれています。
「良い食品を届ける」ために、徹底的にこだわって作り、作った後は変えない。これが、江戸むらさきというロングセラーを生んだこだわりと哲学でした。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所