
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
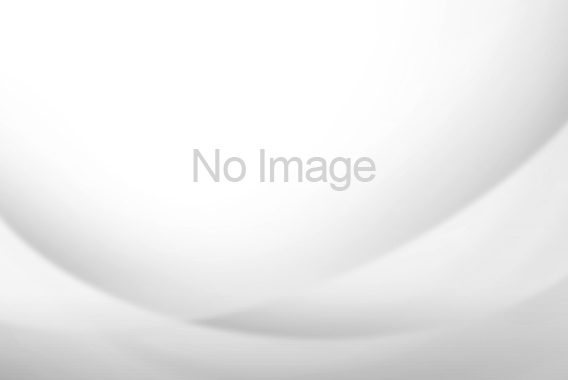
仕事から家に帰った後の大きな楽しみといえば、やっぱりご飯。食の西洋化が進んでいるとはいえ、夕食に温かいお米を食べて明日への英気を養っているビジネスパーソンは多いことでしょう。電気でご飯を温める電子ジャーは、1970年に世界で初めて象印マホービンが発売。日本の食卓を変え、同社の方向性も大きく変えたロングセラーです。
象印マホービンの創業は、1918年。市川銀三郎と金三郎の兄弟が大阪で立ち上げた市川兄弟商会が、その歴史の始まりです。兄の銀三郎はそれまで繊維問屋で働いており、弟の金三郎は電球に使う白熱電球を加工する職人でした。金三郎がヨーロッパから輸入されていた魔法瓶に興味を持ち、商人である兄と魔法瓶の製造・販売に乗り出したのが市川兄弟商会です。
当時の魔法瓶は高価なもので、日本での需要は多くありませんでした。しかし、市川兄弟が魔法瓶に目を付けたのは第一次大戦が終わったばかりの時期でヨーロッパでの生産が滞っており、東南アジアの植民地に住む欧米人の需要は大きいものがありました。そこで、市川兄弟の魔法瓶も東南アジア向けの輸出で売り上げを伸ばしていきます。
時がたち第二次大戦が終わると、魔法瓶はそれまでの携帯用から卓上用に主な用途が移っていきます。1948年には、頭部の形がペリカンのくちばしに似ていることから「ポットペリカン」と呼ばれるようになった卓上用ポットを発売。1961年に象印マホービンと組織を改称しました。1963年にはポットを傾けるだけでお湯が注げる、オート栓の「ハイポットZ型」を発売し、これが大ヒット商品に。会社は魔法瓶のトップメーカーに成長します。
そして1968年に創業50周年を迎えた象印マホービンは、さらなる飛躍のため、新たな商品の開発を経営目標のひとつに掲げます。そこで目を付けたのが、ジャーでした。
今でこそご飯を炊いた炊飯器で保温するのが当たり前になっていますが、当時は鍋や炊飯器でご飯を炊くと、保温用のガラス魔法瓶であるジャーに移し替えて保存していました。象印マホービンもそれまでの魔法瓶製造で培った技術を生かし、1953年にジャーを発売。ヒット商品となりますが、次第に人気に陰りが見えてきていました。保温力が低く長時間の保温ができないこと、またガラス製品で割れやすいことが大きな理由でした。
そこで新商品の開発スタッフが考えたのが、ジャーの電化でした。1950年代後半には白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機が「三種の神器」ともてはやされ、1960年代半ばにはカラーテレビ、クーラーが登場し、家庭に電化の波が押し寄せていました。ジャーも電化すれば、長時間の保温が可能になることが見込まれました。
しかし、象印マホービンはそれまで電化製品の製造を行ったことはなく、ノウハウはありません。また電化製品市場にはすでに多くの家電メーカーがひしめいており、そこに参入するのは大きな挑戦でした。
社内に、電化製品に関する技術は蓄積されていません。どのように作ればいいのか――。開発スタッフの中で試行錯誤が続きます。
技術上のブレークスルーになったのは、村田製作所のサーミスタ(セラミック抵抗体)「ポジスター」との出会いでした。ポジスターには、温度を上げるとともに、一定の温度になれば自動的に止まる働きがあります。発熱と温度制御というジャーに欠かせない機能が、この電子部品で実現できることになります。
ポジスターにより製造への道筋は見えましたが、銀三郎の長男である2代目社長・市川重幸は強豪ひしめく家電業界への参入にためらいを感じていました。しかし製品に自信がある開発スタッフが試作品を社長の家に持ち込み、試用を勧めます。試食した社長の家族は、電気で温められたご飯の味に太鼓判を押し、ついに社長も製品を市場に出す決断を下します。
1970年、電気によりご飯を長時間保温する世界初の電子ジャー「象印電子ジャー」が発売になります。ガラスのジャーの価格が5000~6000円だったのに対し、象印電子ジャーは1万円。価格の高さがネックになることが懸念されましたが、結果は爆発的な大ヒット。販売代理店の社長が工場に乗り付けて商品の引き渡しを直談判するほどでした。
象印マホービンが切り開いたジャーの電化の流れは止まらず、その後、炊飯と保温の両方の機能を持つジャー炊飯器、IH(電磁誘導加熱)を利用したIH炊飯ジャーと発展を続けました。その中でも、「象印のジャー」はトップブランドとして広く愛されています。
象印マホービンは、元々ガラス製の中瓶を用いた魔法瓶のメーカーで、家電製品の製造はまったく手掛けたことがありませんでした。そのため、前述の通り、当初は家電業界への参入に慎重な姿勢を見せていました。電子ジャーには熱伝導に優れるアルミを使いましたが、これはそれまでに培ってきたガラス保温の技術から離れることにもなります。
しかし、社会で家庭用品の電化が進む中、良質な製品ができたことで最終的に電子ジャーの発売を決断。家庭でのジャーの電気化を推し進めるともに、会社の未来を切り開くことにつながります。
この後、それまで電気を使っていなかった魔法瓶も電化を進め、現在は会社の売り上げの8割近くを家電製品が占めるまでになりました。
象印マホービンは、1960年代の半ばにはすでに魔法瓶のトップブランドでした。しかし、電気を使わないガラス製の魔法瓶、ジャーだけを作り続けていたら、象印マホービンの現在のような発展は難しかったでしょう。
挑戦こそが会社の未来を開くとよくいわれますが、このことの重要性、真実性を象印電子ジャーの事例は見事に見せてくれているように思われます。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【T】
ロングセラー商品に学ぶ、ビジネスの勘所